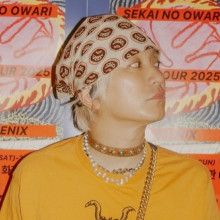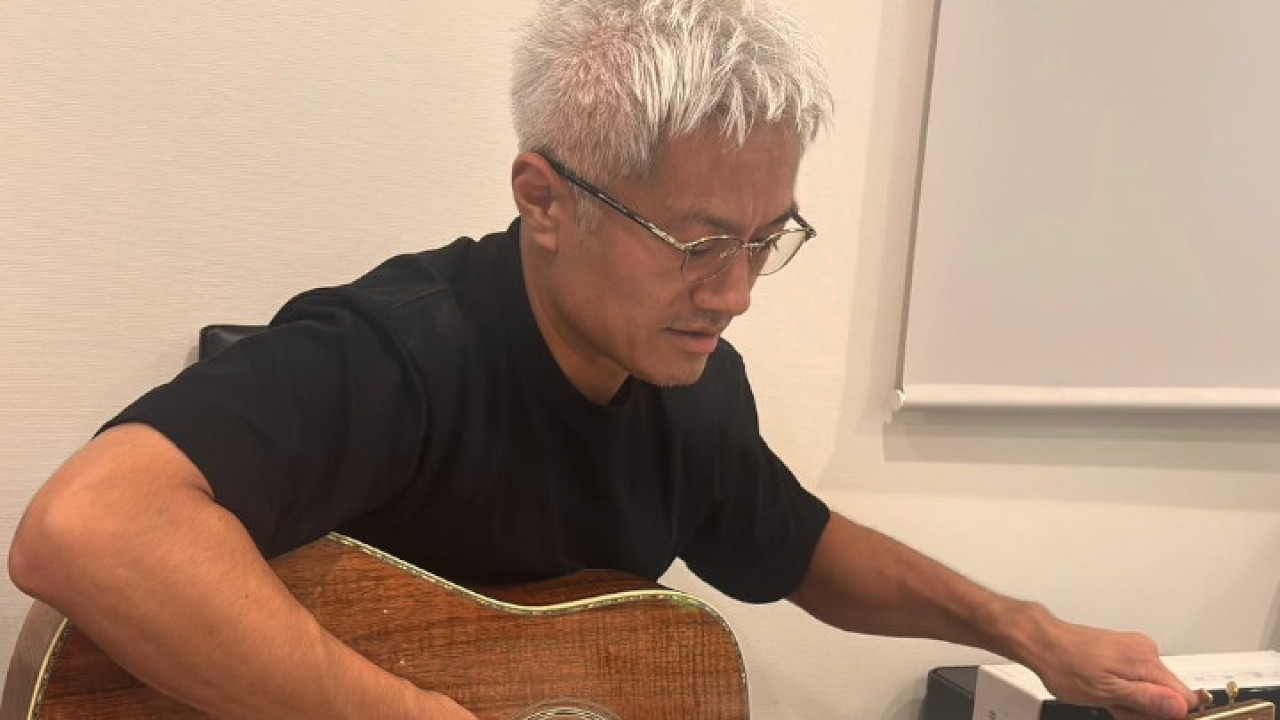というわけで、日本政府がやるべきことは、
(1)中間層拡大政策に転じる。特に、逆累進性が高く、格差拡大型の消費税は増税凍結、もしくは減税する。
(2)生産性向上のための投資である「交通インフラの整備」及び将来の首都直下型地震、南海トラフ巨大地震に備えた耐震化投資の財政拡大を行う。
(3)国民の実質賃金を引き下げる移民受入は、むしろ制限を強化する。
この3つでいいのである。
ところが、大変残念なことに、2018年6月15日、安倍政権は、これらとは「真逆」である『骨太の方針2018』を閣議決定してしまった。
●2019年10月に、消費税率を予定通り10%に引き上げる。
●投資系支出まで制限するプライマリーバランス(基礎的財政収支、以下PB)の黒字化目標は、達成時期を2025年に先送りした上で残す。
●移民受入の新たな在留資格を作る。
見事に「逆」だ。結局、安倍政権は「財務省」に勝てず、同時に「安い人件費」を求める経済界(経団連の企業など)におもねる政権だった、という話だ。PB黒字化目標が残った以上、
「何らかの支出を増やす場合、別の支出を減らすか増税する」
という「考え方」が政府の予算の足を引っ張り続けることになる。
もっとも『骨太の方針2018』では、
『2019〜2021年度を「基盤強化期間(仮称)」と位置づけ、持続可能な経済財政の基盤固めを行う』
と、来年度からの3年間について「基盤強化期間」と名付け、「持続可能な経済財政の基盤固め」を行う期間として設定されている。「基盤強化期間」の定義がよく分からないが、要するに'19年10月の消費税増税による需要縮小、再デフレ化、景気後退に対し、財政拡大で対処するという話であろう。
そもそも、需要縮小や再デフレ化を恐れるならば、消費税を増税しなければいい、が正論なのはもちろんだが、増税と同時に政府支出を削減するよりは「マシ」である。
また、'21年度に財政の「中間評価」がなされ、そこでは、
『PB赤字の対GDP比については、2017年度からの実質的な半減値(1.5%程度)とする。債務残高の対GDP比については、180%台前半、財政収支赤字の対GDP比については、3%以下とする』
と書かれている。財政赤字対GDP比3%は、PB黒字化よりは緩い目標になる。つまりは、財政拡大の余地が残されている。
さらに、これまでの骨太の方針に明記されていた予算拡大の「枠」はなくなった。
'18年度予算(本年度予算)までは、骨太の方針により「一般歳出の目安5300億円」という「増加分の枠」が設定されていたのだ。正直「狂気の沙汰」としか表現のしようがない政策方針だったのだが、今回の骨太の方針で「枠」は消えた。
つまりは、これまでは予算拡大の「枠」を設定された上で、PB黒字化を達成するという、過酷な「無理ゲー(※クリアが不可能なゲーム)」を要求されていたことになる。何しろデフレから脱却し、名目GDPが増えていけば税収も増え、PB黒字化は達成される。そしてデフレ脱却のためには政府が予算を増やし、デフレギャップを埋める必要があるのだ。
その「デフレ脱却のために必要な予算拡大」に「枠」をはめられていたわけで、まさに無理ゲーである。
今回の骨太の方針では、デフレ脱却やPB改善というゲームを無理ゲーと化した「枠」は撤廃され、
『2019年10月1日に予定されている消費税率引き上げの需要変動に対する影響の程度や経済状況を踏まえて、当面の予算を編成する』
『中長期の視点に立ち、将来の成長の基盤となり豊かな国民生活を実現する波及効果の大きな投資プロジェクトを計画的に実施する』
と、一応、デフレ脱却に向けた真っ当な政策も謳われている(そもそも、消費税増税が「デフレ化政策」で、真っ当な政策ではないが)。
ということで、『今回の骨太の方針2018』は、
「前よりもマシで、デフレ脱却の【可能性】はあるものの、結局は財務省の緊縮路線に屈した」
との評価になる。少なくとも、以前までよりは「無理ゲー色が薄まった」というのが、わずかに残された希望である。
日本政府は6月12日、科学技術について日本の基盤的な力が急激に弱体化しているとする、'18年版の科学技術白書を閣議決定した。
'00年度を100とし、直近の科学技術関係予算を比較すると、中国が11倍、韓国が4.7倍、アメリカ、ドイツ、イギリスといった先進国ですら1.5倍強。それに対し、わが国は1.06倍。予算を全く増やしていない。日本が科学技術大国から凋落したのは、PB黒字化目標に代表される緊縮路線が主因なのだ。
『骨太の方針2018』では、政府の研究開発投資を対GDP比1%に拡大する目標が謳われた(現在は0.6%程度)。もっとも、政府研究開発投資拡大の項には「第3章の新計画との整合性を確保しつつ」という怪しい文言が入っている。「第3章の新計画」には、問題の、「2025年度の国・地方を合わせたPB黒字化を目指す」が含まれているのだ。
つまりは、PB黒字化目標を達成できない状況になれば、またもや科学技術関係予算は「抑制」されることになりかねない。
政府の負債が100%日本円建てのわが国にとって、PBなど「どうでもいい」目標だ。どうでもいい目標を守るために、すべての基盤である科学技術関係予算を抑制し、日本は技術大国から凋落した。
まさに、緊縮路線が日本を亡ぼそうとしていることが分かる。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。