Bが国道を走っていた時だった。その場所は高速道路の終点とつながっており、高速道路から降りた自動車と、国道を走っていた自動車が合流する地点があった。
Bは高速から降りた自動車と合流して、国道をしばらく進むと、Bの視線上では道路が事故渋滞に遭遇した感じがした。目の前が急に自動車の列で渋滞しだしたのだ。しかもその自動車の数は半端な数ではない。二車線の道路が延々と自動車の列になって渋滞していたのだ。しかも、先が見えないくらいの渋滞だった。その先数百メートルにも及ぶような自動車の数だった。その中には、警察署の事故応対用の車両が、ライトを点滅させながら二台ほど止まっていた。
この状況では、この道を通れるようになるのに、何時間掛かるか分からない。その時Bは、国道から脇道に逸れて走った方が、まだ家路に近いだろうと判断をした。Bは隣の自動車の男性運転手が、渋滞に苛ついた顔をしているのを見た。
Bは左に曲がる道へと自動車を進め、裏道に出ようとした。だが、道を間違えてしまい、自動車が入った道路は先が見知らぬ方向に伸びていた。そこでBは途中で自動車をUターンさせた。元来た道に戻って事故渋滞に遭うのも仕方ないと、半ばあきらめて走っていた。
やがて国道に差し掛かると、事故渋滞どころか自動車の数は僅かであり、先ほどまで数百台が渋滞で止まっていたという場所には、それこそ事故用の警察車両の一台も見当たらなかったのだ。
Bが脇道からUターンして戻ってくるまでの時間は、僅か1、2分であった。Bはまるで自分が狐にでも化かされたような気分になり、あのまま間違えた道を進んでいたら、大きな事故に出遭った気がした。彼は思わず背筋に冷たいものが走るのを感じた。その後家まで無事に到着できたようだが、彼はこんな奇妙な体験は初めてだったと言う。
(藤原真)







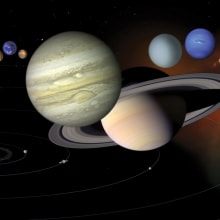




















 芸能
芸能








