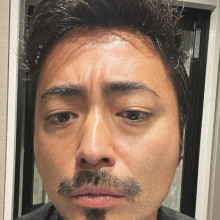リクシルといえば、TBSが横浜ベイスターズを身売りする際に、候補になっていた会社の一つ。その後も球団身売り関係の報道が出るたびに名前が挙がる企業である。
「リクシルが球界参入に再挑戦するとの噂もありました。パ・リーグの球団が標的されているとかで、具体的な球団名が報じられたこともありました」(スポーツ紙デスク)
リクシルが旧横浜ベイスターズの買収に乗り出し、失敗したのは2011年オフ。当時を知る関係者によれば、準備不足が原因だったとのこと。NPB内部には「ペナントレースの地方興行など、詳細を知らなすぎた」との声も聞かれた。しかし、その後に身売り報道が巻き起こった西武やロッテといった球団は、リクシルからの接触を完全否定している。
リクシルが球界参入へ再挑戦することがあるのならば、以前の準備不足を補い、それ相応の準備を整えてくるはずだ。
「リクシルが横浜買収を進められなかった原因に横浜スタジアムと球団の契約がありました。旧経営陣との間で使用契約年数を残しており、翌12年にDeNAが買収に成功したのはその契約が満了する年でもあったことが幸いしました。そして、リクシルがドイツの水栓金具大手のグローエ社を買収したのが13年。この時点でリクシルの球界参入の話は終了したとの見方もされていました。同時に、企業規模拡大の意味でグローエ社買収の次は球界参入だと予測する向きもありましたが」(同)
球団買収の動きに関する真偽はともかく、リクシルのターゲットとしてパ・リーグ球団の名前が出たのにはそれなりの理由があった。まず、交流戦の試合数が減少傾向にあったこと。そもそも、交流戦は旧オリックスと近鉄バファローズが合併した04年、同時審議された経営改革案だった。当初はホームとビジターで3試合ずつ、1球団あたりセの球団との試合は36試合あった。パ6球団は交流戦で実力を存分に発揮し、それに絡めたイベントやファンサービスも行い、交流戦で収益を増やしてきた。これに対し、セ・リーグ側は遠征先が増えるなどの出費面のほうが大きくのしかかり、かつ試合成績自体もパに押されることが大半だったため、交流戦の規模縮小を推し進め、現在の18試合制にすることに成功した。この規模縮小はパにとっては大きな損失だった。
「交流戦は開始当初の半分の試合数になり、将来的に交流戦そのものがなくなる可能性も否定できない状況になりつつあります。となれば、パ・リーグの収益アップで期待できるのはCSしかありません」(同)
プロ野球全体で見ても、オールスターゲームや日本シリーズですら地上波放送権の売買では苦労させられている。12球団共有の新収益として侍ジャパンの常設も始めたが、「ベストメンバーを揃えたことがない」などの理由から、放映権料が伸び悩んでいる。
プロ野球界の収益モデルは全体で右肩下がり。中でもパ・リーグはさらに危機になってきている。リクシルはそのパ・リーグの起爆剤になれるかもしれない存在だっただけに、水面下で歯ぎしりをしている関係者がいるかもしれない。















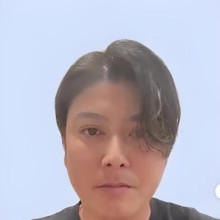









 社会
社会