昭和50〜60年代の前半にかけて、そんな美男力士の称号を欲しいままにした力士の1人が、蔵間(本名・蔵間竜也、時津風部屋)だった。相撲協会を退職後、タレントとして活躍していたから、まだ記憶に残っている読者も多いに違いない。
蔵間は滋賀県野洲郡野洲町(現・野洲市)で、昭和27年12月16日に生まれている。父は、ある全国紙の地方記者。体力に恵まれ、また運動神経も抜群だったため、八幡工業高時代はラグビー部で活躍し、またホンの片手間にやった柔道でも2段を取得している。
まさに、力士に打ってつけ。そんな少年が大相撲界のスカウト網にひっ掛からないはずがない。
「野洲にいい子がいる」
高校2年の時、当時、理事長だった時津風親方のもとに連絡が入ると、すぐさま代理で枝川親方(元大関北葉山)が飛んでいき、入門が決まった。時津風親方はあの69連勝を記録した大横綱の双葉山で、蔵間が入門して4カ月弱の12月16日に劇症肝炎のために亡くなっている。ちなみに、この命日は蔵間の誕生日と一緒だった。奇妙な縁で結ばれていたと言わざるを得ず、のちに蔵間は、次のように吹聴し、自慢していた。
「オレは双葉山最後の弟子だ」
初土俵は昭和43年秋場所。早くから大器と目されていたが、出世は遅く、ようやく十両に昇進したのは8年後の昭和50年夏場所のことだった。幕下に4年近くもいたのだ。淡泊な性格に加え、腰痛の持病があったことが災いしたと言われている。
昭和51年名古屋場所で新入幕。滋賀県からは大正11年春場所の伊吹山以来となる幕内力士誕生で、地元はもちろんのこと、「スケールの大きな新人現る」と、注目を集めた。
★昭和天皇も気にかけた逸材
大の相撲好きで知られた昭和天皇も、そんな1人だった。入幕して間もない頃、天覧相撲の折りに説明役だった春日野理事長(元横綱栃錦)に、
「蔵間はどうなの?」
とお尋ねになると、
「あれは(いずれ)大関になります」
と、春日野理事長は自信たっぷりにお答えした。
ところが、大関候補に名前が挙がるものの、いっこうに射止める気配がない。このため、昭和天皇も天覧相撲のたびに、
「蔵間は(なかなか)上がらないねえ」
と残念そうにお話しになり、春日野理事長はいたく恐縮。あとで蔵間を理事長室に呼んで、こう叱責したという。
「俺は天皇陛下にウソを申し上げてしまった。しっかりしろ」
どうして蔵間は“善戦マン”と呼ばれ、横綱、大関と力の入った大相撲を取るものの、ついに大関の壁は破れなかったのか。
これは、相撲があまりにも左四つがっぷりの正攻法だったことが大きい。自分は十分の体勢だったが、相手はそれ以上の十二分。その上、攻めが遅いこともあって、いいところまで攻め込むものの、あと一歩のところで力尽きるのだ。
横綱との生涯対戦成績はなんと2勝44敗。昭和53年夏場所には自己最高位の西関脇まで上がっているが、3勝12敗と大敗している。
しかし、美男で会話も軽妙だったため、その周りはいつもにぎやかで、様々な面でバックアップしてくれるタニマチも多かった。なにしろ横綱、大関でもないのに、あの横綱輪島の向こうを張るようにピカピカのリンカーン・コンチネンタルや高級車のベンツを乗り回し、千葉県市川市に“蔵間御殿”と呼ばれる豪邸を建て、昭和57年6月には女優の渡辺やよいと結婚しているのだ。
「相撲はそんなに強くならなくていいから、ああいう生活をしたい」と、当時の若い力士が憧れる力士ナンバーワンになり、
「最近の新弟子は、蔵間を見習って稽古をしようとせず、女の子の尻ばっかり追いかけまわしている」
と、親方たちは渋い顔をしたものだった。
当時の蔵間がどのくらい羽振りがよかったか。付け人の1人は、こんな証言をしている。
「財布の中には、いつも300万円は入っていましたね。散々、散財してサイフが凹むと、いつの間にか、また元の厚みに戻っているんですよ。そんな財布でしたから、遊びも豪快そのもの。1晩に100万円使うこともよくありました」
こんな力士生活を謳歌していた蔵間に思いもよらない病魔が襲ったのは、平成元年の秋場所初日のことだった。
「場所前の身体検査の結果で気になるところがあるので、来てください」
両国国技館内にある相撲診療所から、このように呼び出されたのだ。そして、再度の血液検査の結果、唯一の完全治癒法が骨髄移植しかないという難病の「慢性骨髄性白血病」に侵されていることが判明する。しかも、骨髄移植の成功率は5割以下。失敗すれば即、死に至ることもある。大変な事態に陥ったのだ。
このため、とりあえず秋場所は4日目まで出場したものの、5日目から休場。場所後、慌ただしく引退することになるのだが、この突然の休場理由は「脾腫により、1カ月の加療を要す」となっていた。本当のことを明かせば、
「かわいそうに、あの蔵間も先は短いのか」
と、ファンの同情を買うのは目に見えている。蔵間はそれを嫌ったのだ。美男力士ならではのダンディズムだった。
蔵間が選択した治療法は、危険をはらんだ骨髄移植ではなく、最先端の化学療法だった。最新の薬を注射しながら慢性状態を保ち、奇跡が起こるのを待つという方法だ。
★病を隠して人気タレントに
こうして、表面的には平穏を装いながら、蔵間は引退して「錣山」を襲名。親方になったが、その親方暮らしも1年とは続かず、まるで何かに追い立てられるように、平成2年6月には相撲協会を退職。やがて、甘いマスクや持ち前の明るさ、軽妙なトークを生かした大相撲をネタにするタレントに転身したのだ。
これなら比較的、自由に治療の時間も取れる。
この思い切った職場転換は当たった。ちょうど若乃花、貴乃花の“若貴”が台頭し、空前の相撲ブームが起き始めたときだった。蔵間は、つい最近まで現役だったキャリアを活かして、ほかのキャスターや記者らが立ち入れないところまでやすやすと潜入。面白い談話やカメラの映像を次々にゲットしてきたのだ。
このため、たちまち様々なテレビ番組から引っ張りだこ。TBS系の『ブロードキャスター』などの情報バラエティー番組にも進出するなど、元力士としては異例の活躍を始めたのだ。“第2の蔵間フィーバー”の始まりである。ただ、それらの番組内の優勝予想では的中したことがなく、
「蔵間さん、今場所の優勝予想ではボクの名前を挙げないで」
と、力士たちから真顔で懇願されたこともあったという、笑えないエピソードも残っている。
しかし、このフィーバーも、そう長くは続かなかった。周囲には伏せ、投薬により懸命に抑えていた白血病が、次第に頭をもたげてきたのだ。
平成5年頃から次第に痩せ始め、平成7年1月5日、ついに入院。病状がどうにもならないところまで進行していた。このため、それまではためらっていた骨髄移植に踏み切る決断をし、その準備も始まった。このとき、成功率はすでに30%以下にまで落ちていた。
そんな矢先の1月26日の夕方、ベッドの横に付き添っていたやよい夫人が一時帰宅した留守中に病状が急変。病院からの一報で、やよい夫人が慌てて病院に駆け戻ったとき、すでに蔵間の呼吸は止まっていた。息を引き取ったのは午後8時16分。引退からわずか5年余り。まだ42歳だった。
「早く(2人の子どもたちの待つ自宅に)帰ってやって」
やよい夫人が最後に聞いた蔵間の言葉は、家族を想ったものだったという。希代のモテ男も、立派な家庭人だったのだ。
この死から8カ月後、やよい夫人は蔵間との16年にわたる結婚生活を綴った『永遠の千秋楽』(ザ・マサダ刊)という本を出版。翌年、それがTBS系でドラマ化されてヒットした。
蔵間役は渡辺徹、やよいさん役は名取裕子だった。
相撲ライター・大川光太郎






















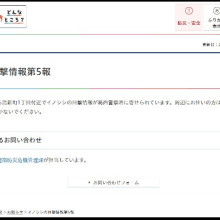
 社会
社会








