女子競輪はB級戦の代わりに行われていたが、選手同士に力の差があったために、高い配当を求めるファンには評判が悪かった。これは女子競輪をしっかりした自転車競技の中の競輪という位置づけにしなかったことが原因だろう。それなりの訓練もされていなかったということもある。
最初から女子競輪は際物だったという認識がある。昭和39年10月に、かつて1016人いた女子選手は登録消除された。その後も復活の話はたびたび出ていた。だが、訓練施設の問題や、施行者が売上向上につながらないなど「過去の実績」で乗り気でなかったこともあって、当時なら十分な施設を作る資金も再養成する機構もありながらも、アイディアの段階で終わってしまった。
最近では女子のスポーツ能力の高さが改めて認識されているが、そんなことは戦後のスポーツ競技での女子の活躍をみれば分かることで、古くは東京五輪の日本女子バレーボールの金メダルが証明していた。だが、国家的というか組織的な女子選手の強化は、男子ほど行われていなかった。
競輪で女子競輪を復活させるチャンスがあったのは、26期生から行われた伊豆の競輪学校のオープンの時だったと思う。この時、せめて男子生徒の半分でいいから養成する機関を作っていたら、女子競輪は復活していただろう。
スケートから自転車競技に転向し、世界選などに出場した橋本聖子さんは、その後、参議院議員として活躍しているが、それ以上の活躍をする選手が出てきていたかも知れないと予測できる。
組織的にものを考え将来の設計をしないのは、競輪が常に通産省(いまの経産省)の監督下にあって交付金が莫大な金額で流れていたことで、近未来を見つめた競輪施策など関係者のほとんどが考えもしなかったためだろう。
競輪に携わった人たちの取り組み方にも問題はあった。競輪を監督する経産省の担当課長は3年で変わる。いかに優秀な官僚でも3年で改革は出来まい。その下の課長補佐もキャリアだから3年ごとに変わっていく。
決定権をもった人たちが基本的な競輪運営の未来図を作る時間がなかったこと、またほかの団体も擬似官僚化して、この事業の将来に対して真剣に取り組まなかったことが原因だ。その現象は平成に入ってから20年続いている。
女子選手の身体能力が向上した今、どうしたら女子レースを「きわもの」で終わらせないか考えて欲しいものだ。






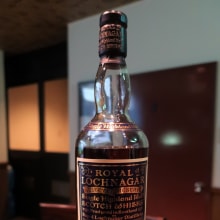














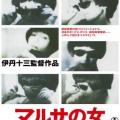







 芸能
芸能








