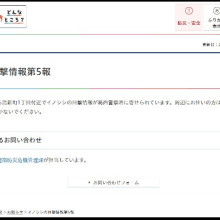日本チェーンドラッグストア協会の統計によれば、ドラッグストア業界の市場規模は6兆5000億円、前年比較で5.6%増加('17年)している。店舗数も前年比2%増で、全国では約2万店に達する勢いだ。
「ドラッグストアは、約10年前は市場規模約5兆円。そこから10年間で1兆5000億円ほど売上が拡大している。業界では'25年までに10兆円市場を見据えており、そうなると13兆円のスーパー市場とほぼ肩を並べる。中長期的に見れば、逆転の可能性さえ出てきているのです」(業界関係者)
ドラッグストアに勢いがあるのは、いくつかの要因がある。
「その一つが食料品販売です。新興住宅地などのメーン道路沿いに大駐車場を有した店舗を構え、消費者に入りやすさを提供し、薬、衛生雑貨、化粧品はもちろん、ついでに食料品も手に取ってもらう。主にパンやインスタント麺類、飲料水などで、魚や肉などはまだ少ないが、最近はジャガイモや玉ねぎなどの生鮮食品も展開するところが出てきている」(同)
それに加えて、調剤薬局を置く店舗が増加しているのも特徴だ。
「高齢者が病院に行き、ドラッグストア内で薬を処方して、そのついでに食料品や日用品を買う。一つの店ですべてが完結するワンストップショッピングが可能で、これが売上増の要因にもなっているのです」(薬局関係者)
逆に大手スーパーは、ここ最近、厳しい状況に陥るケースが多くなり始めており、そうしたドラッグストアに顧客を食われる現象も起きている。
「業界トップのイオングループのイオンリテールは、'15年2月期に営業損失16億4600万円と赤字に転落。'18年2月期第3四半期決算では215億9700万円の営業損失。モールで巨大な売場面積を持つイオンにして、やはりドラッグストアの影響をジワジワと受けている」(業界紙記者)
例えばイオンモールは、大半が郊外型で車での来客を想定しており、これはドラッグストアと重なる部分もある。
「ただし、モールの場合は周辺道路が大渋滞し、巨大駐車場があっても駐車を待たされることもある。最初こそ物珍しさもあり客は入るが、そうした混雑に巻き込まれてまで買いだめしなくても、地元で事は足りるというところに落ち着く。食料品の面でそれを埋めてきたのがスーパーやコンビニだったのですが、その隙間にドラッグストアが入り込み攻勢をかけているのです」(同)
そんな中、スーパー業界も対抗策に出ている。
「約8000億円近い売上高で業界3位のユニー(2位はイトーヨーカ堂)は、愛知、静岡などに約200店舗を展開しているが、総合ディスカウント業で好調のドン・キホーテに株式の4割を譲渡し、業務提携で活路を探っている」(小売業界関係者)
一方で、ドラッグストア業界内では、生き残りをかけた熾烈な争いが起きている。'17年時点で見れば、『マツモトキヨシ』を展開するマツモトキヨシHDが売上で首位から3位に陥落し、トップに『ウエルシア薬局』のウエルシアHDが躍り出た。
「'17年2月期売上高6231億円で前年比17.9%増という勢いのウエルシアは、食品の売上は全体の21.2%。医薬品・衛生介護品・ベビー用品・健康食品の22.2%とほぼ同じで、やはり食料品の充実によって成功している」(前出・業界関係者)
2位は『ツルハドラッグ』のツルハHD。'17年5月期の売上高は5770億円、前年比9.4%増だ。
「マツキヨは'17年は5161億円で対前年比0.2%減と3位に転落した。マツキヨの場合、店舗の大半が繁華街にあって面積が狭いため、食料品まで拡大できていない。それが、売上減に表れているのではないか」(同)
しかもトップの座を窺っていたツルハは、昨年9月に静岡県を中心に店舗展開する杏林堂HDを子会社化。売上高も単純計算で6665億円に達し、一気に業界トップとなる見込みだ。
「ただし、そのツルハの大株主はイオンで、ウエルシアもイオングループ。イオンは今後、スーパーの先行きを考慮しつつ、次の手を打つと見られている」(同)
全国的に見れば、スーパーでは、中国、九州地方の『ゆめタウン』などで売上を伸ばすイズミが'17年1月の営業利益が対前年比11.8%増など、中規模スーパーの地元密着型での健闘が目立ち始めているという。ドラッグストアがスーパーを飲み込むか、スーパーが巻き返すか。激しいサバイバルは今後も続きそうだ。