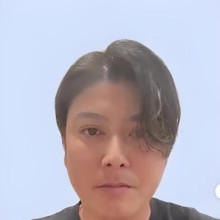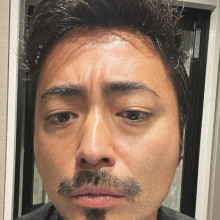『株式会社美匠』(奈良県橿原市・中西あざみ代表取締役)が三重県名張市内に設置する「永代供養安置所」にたどり着いた。
「ここには4000基ほどの墓石が安置されています。これらは何らかの事情で墓地を解体撤去したいという、いわゆる“墓じまい”を希望された施主様から引き取った墓石が集められています。僧侶による魂消しを執り行った後、一定期間保管しています」
同社の西向友也営業部長はこう説明する。
時代の変化と共に墓の在り方も変わり始めている。不要となった墓石が集められ、解体作業を待つ“墓の墓場”が全国に増えているのだ。
遺族との縁を断ち切られて無縁化した墓石はもはや“ゴミ”となり、鉄くずや紙くず同様、やがて産業廃棄物として処分される運命にある。墓じまいは年々増加傾向にあるというが、一体どのような墓が不要とされるのだろうか。
「永代供養安置所」に運び込まれた墓石を見てみると、人間同様、同じ墓というものは一つもなく、さまざまなものがあることが分かる。旧日本軍の陸軍軍曹、陸軍兵長、あるいは特攻隊で戦死したと思われる海軍飛行兵と刻まれたものもあれば、安政4年と、江戸時代から代々続く旧家の墓石、一方で「平成二九年七月」と建立してから1年足らずというものもある。4000基には4000分の墓じまいの理由があるのだ。
「弊社の場合、近畿、東海、北陸、山陽方面を主要エリアに、石材店など800社と取引しており、重量にして年間約2万トンの墓石解体を行っています。こうした墓じまいの傾向は10年ほど前から顕著になってきましたね」(西向部長)
増加する墓じまいだが、どのような背景があるのだろうか。一度埋葬した遺骨などを他の墓に移す“改葬”が、墓じまいに大きな影響を及ぼしているようだ。『社団法人全国優良石材店』の吉田剛代表理事はこのように説明する。
「墓じまいとは改葬のことですが、これには二つのケースがあります。一つはA墓地からB墓地に移転させるケースで、これは利便性を考慮した対処法です。もう一つは完全に墓地を放棄するケース。現在問題になっているのは後者で、実際この傾向は数字でも裏付けが出てきています」
東京都が2005年に実施した都民の墓所に対する意識調査では、墓地が必要と答えたのは約61%、不要は約28%、分からないは約11%だった。10年後の'15年、同調査では必要約35%、不要約35%、分からない約29%と、必要と不必要が同率となった。都民の墓地というものの必要性が大きく変化している結果が浮き彫りとなり“墓ばなれ”が年々増えている傾向が調査結果からも明らかになった。
墓ばなれは墓じまいに比例する。厚生労働省の調べによると、'15年度における改葬は全国で約9万1567件に達する。
「墓ばなれも墓じまいも理由はほとんど同じです。つまり少子化による墓地の継承問題、家や帰属意識の希薄化、簡素化の一環、利便性重視の社会風潮、伝統文化の無関心などが挙げられます」(吉田理事)
葬儀の多様化も墓地不要に拍車をかけている。葬儀の多様化とは散骨、樹木葬、水中葬、合葬墓、ロッカー式納骨、いまでは遺骨を特殊なカプセル容器に詰め、打ち上げロケットに搭載して宇宙に撒く宇宙葬なども出てきている。
一方で、都立霊園などは合葬墓や樹木葬など墓地の簡素化を推奨している。東京都は青山墓地や多磨霊園、八柱霊園など8カ所の霊園を運営している。樹木葬とは芝生や樹木の根の下に遺骨を埋葬するものであり、合葬墓もほぼ同じものだ。八柱霊園には約10万体が合葬墓に埋葬され、小平霊園には1万7000体が樹木葬だという。都が供給する墓地の8割強がこうした合葬墓や樹木葬で、墓石を建てるといった一般的な平面墓地は2割強にすぎないという。
墓地の簡素化を推進する理由にスペースに限りがあること、管理運営費の増加が背景にある。都が勧める墓地の簡素化は地方にも影響を及ぼし、公営墓地だけでなく民間の霊園でさえも合葬墓や樹木葬が次第に浸透しているという。
都心部に比べ地方は地域や住民、あるいは寺とのつながりが濃密で、墓地問題などないものと思われがちだが、集落の過疎化や荒廃化により、むしろ地方のほうが深刻な墓地問題に陥っている。こうした要因が地方の霊園でも合葬墓や樹木葬の需要を高めているのだ。
だが、合葬墓は文字通り不特定多数の遺骨を一括埋葬するため身内の遺骨がどこにあるか特定できない。散骨も、海中などに散布するので跡形もないため、問題になることもあるという。
「合葬墓や散骨を利用したのを後悔しているといったケースもあるんです。お孫さんに、おじいちゃんのお墓はどこにあるの、と聞かれ、答えに困ったといった方もいらっしゃいました」(吉田理事)
前述の「永代供養安置所」に運び込まれた約4000の墓は、無縁墓として処分されるその日を待つ。解体作業は愛知県内の3カ所で行っている。実際に施主が石材店などに墓地の解体撤去を依頼した場合、どのような手順を踏んで解体されるのだろうか。
まず一般的に、墓地の解体撤去に取り組む前段として、墓地の移設なら移設先の管理者(寺院もしくは霊園)に「受入証明書」を発行してもらう。次に現在墓地がある管理者に埋葬証明書を発行してもらうことになる。さらにその証明書を現在の墓地が所在する市町村役場に提出し、改葬許可申請書を発行してもらう。
これらの行政手続きをすませたところで実際の解体工事に着手する。この工程は石塔、カロウド、石垣などの解体、運搬車両への積み込みと搬出、墓地の整地および原状復帰、永代供養安置所搬入、僧侶による魂消し供養、一定期間の保管、産業廃棄物処理業者による中間処理場への搬出、砕石などのリサイクル化―といった流れになる。
では、これらに伴う解体撤去費用はどのくらい掛かるのだろうか。工事の難易度や使用機材の違いによって多少の差はあるものの、大体40〜50万円が相場と考えていいようだ。
墓地の解体撤去ビジネスは墓ばなれ、墓じまいの増加に比例して今後さらに需要が伸びる可能性を秘めている。新たな隙間産業として石材業界は注目している。だがその反面、新規業者が隙間に割り込み、それが新たなトラブルの原因にもなっているという。いわゆる墓地ブローカーである。ブローカーとは、つまり墓石を売ったり建てたりはするがその後は売りっぱなし、建てっぱなしの“我れ関せず”の業者をいう。
「いま問題になっている墓石の不法投棄もブローカーに多いんです。引き取った墓石は産廃処理の許可を得た業者に有償で委託しなければならないので、そのカネが惜しいから山林などに捨て去っていくのです」(吉田理事)
実際に茨城県、熊本県、京都府などで墓石の不法投棄が発覚し、業者が逮捕されている。そのため経済産業省は'11年4月の廃棄物処理法の改正で、無許可業者に産廃処理を委託した場合、5年以下の懲役または1000万円(法人は1億円)以下の罰金にするなど、罰則を強化した。
墓地を必要とするものと不要とするものが拮抗し、墓ばなれ、墓じまいの時代に突入している。それに伴う新たな社会問題も生まれてきている。
先祖を弔う形式も大きな転換期にきているようだ。