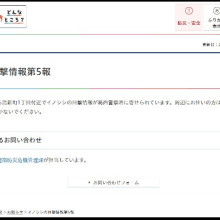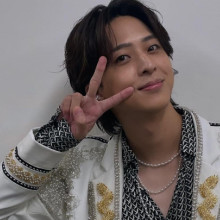そんなシューカツの実態を反映するのが「就職率」だが、これが人生に何の不安もない“官僚”の仕事だから、言ってみればテキトーな産物と言える。
8月28日の日経新聞は「新卒ニート3万人」なる見出しを掲げ、記事中には「就職率63.9%」という数字が躍った。だが同じ日経は、今年5月には「大卒就職率93.6%に改善」と、極めて高い数値を報じたのだ。いったい、どちらが本物なのか?
「前者は文科省の『学校基本調査』からはじき出したもの。後者は、文科省と厚労省が共同で行っている『内定・就職状況に関する調査』による就職率です。ざっくり言えば、両調査は時期が違うし、そもそも就職率を算出する際の分母が異なっている。どちらも現実を細かに把握しているとは言えず、両者の中間くらいというのが実態です」(就職コンサルタント)
さらに問題点を挙げると、両省の調査の依頼先だ。国立大21、公立大3、私大38(すべて校名は未公表)となっており、国立大学の数が多いのだ。
「全大学数に占める国立大の比率は11%にすぎないのに、調査対象校では約34%を占めており、いまだに官僚社会に根強い国立>私立指向がそのまま反映されている。私立大より就職率の高い国立大比率の高さは、そのまま全体の就職率を押し上げるということです。そして、就職率算出の分母となる『就職希望者』に細かな規定はなく、その選定は調査対象大学の担当者に“丸投げ”されているため、政府による対策を最も必要としている学生層が分母から外れて、統計上の数値から消えている可能性が高いのです」(同)
“シロアリ官僚”の作る適当な数値に、一喜一憂させられる学生はかわいそうだが、それ以上に、大学と一部企業の“イベント”と化している今の「シューカツ」が、本来の就職活動の姿だと思わされていることのほうが哀れな気もする。