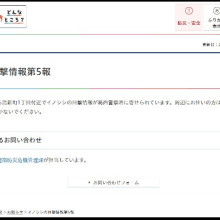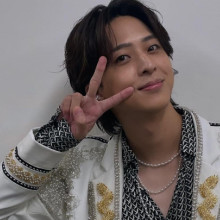Demographia World Urban Areasの「LARGEST BUILT-UP URBAN AREAS IN THE WORLD:2016」によると、世界最大の都市圏は東京圏(東京-横浜)で、推定人口は3790万人である。2位はインドネシアのジャカルタ圏で、推定人口3170万人。
東京圏とジャカルタ圏では大きな違いがある。何が違うのかといえば、交通渋滞の深刻さだ。
今や世界一の渋滞都市と化してしまったインドネシアのジャカルタ。自動車の所有台数が東京の2倍であることに加え、膨大な数のバイクが走り回り、時に逆走し、交通全体が混乱に陥っている。'15年以降、ジャカルタは「世界最悪の渋滞都市」の不名誉を負い続けているのだ。
インドネシアの国民所得は、いまだ日本の10分の1程度である。とはいえ、200万円前後の乗用車を買う高所得者層や、15万円程度のバイクまでなら購入可能な中低所得者層が拡大。ジャカルタの車両登録台数は、過去7年間で自動車が100万台から200万台へ、バイクが200万台から700万台へと激増した。
それに対し、道路整備はほとんど進んでいない。結果、ジャカルタの道路という道路に自動車やバイクが溢れかえる状況に至った。しかも、バスがタクシーのごとく客待ちをし、バス停ではない箇所に停車する。ジャカルタには、バス停と無関係にバスを走らせる業者が多数あるのだ。
さらには、あまりにもひどすぎる交通マナー。多くの人々が、運転免許を持たないにも関わらず、平気でバイクや自動車を走らせる。無免許運転が警官に見つかったとしても、賄賂を渡せば見逃してもらえる。強引な車線変更、日本では考えられないバイクの「逆走」、急停車、信号を無視した交差点への突入(そもそも信号機が極端に少ない)、頻発する交通事故。東京の2倍の自動車、そして何百万台ものバイクが、マナー無視で行き交うわけである。交通渋滞がひどくなって当たり前だ。
交通システム自体も相当にひどい。5車線がいきなり2車線になったりもする。合流のための標識なども未完備だ。もっとも、標識を整備したところで免許を持っていないドライバーたちにとっては、馬の耳に念仏であろう。さらには、車検制度がないため、時速50キロ程度しか出せない大型トラックなどが現役で走っている。低速でしか走れない車両が高速に乗ってくると、途端に渋滞だ。
複数の要因で大渋滞が常に発生しているのが、現在のジャカルタなのである。
インドネシア政府はバイクを減らすために地下鉄を建設し、高速道路環状線の整備も進めているが、バスに規制をかけ、交通マナーを強制し、車検制度を完備するなどの施策も、渋滞解消のためには必要となるだろう。
ジャカルタではバイク版のウーバーとでもいうべきGojekが大流行している。慢性的に渋滞に苦しむジャカルタでは、小道や小回りの効くバイク・タクシーの需要が大きいのだ。というわけで、スマートフォンで自分が指定した場所へバイクを呼べるGojekが普及していった。
Gojekのドライバーたちは、地方出身者が多い。仕事はなく、インドネシア語もしゃべれず(インドネシアで話される言語は500を超える)、バイクの運転だけはできる若者が、緑色のGojkeのジャケットを身に着け、ジャカルタ中を走り回る。現在はGojekのドライバーは「客」のみならず、宅配サービスも担っている。レストランなどからの料理の宅配までもが、スマホ一つで可能となっているのだ。
Gojekのサービスは確かに便利なのだが、だからと言って「道路」というインフラストラクチャーが拡張したわけではない。不十分な道路インフラはそのままに、Gojekのバイクが走り回るため、渋滞は悪化した。正直、ジャカルタの渋滞が解消される日は、筆者が生きている間には訪れないのではないかと思う。
ところで、インドネシアは日本と真逆で、若者が「余っている」。インドネシアは全体の失業率('16年)は4.1%だが、若年層失業率は14.9%であった。経済学者などは高齢者が少なく、若年層が多い国について、「美しい人口ピラミッド」であるとして、経済成長と絡めようとする。「美しい人口ピラミッド」が、今後の消費拡大云々という話なのだろうが、本当にそうなのか。冷戦期はともかく、現在は技術発展で生産性が上昇し、需要に対し供給能力が過大になりがちだ。しかも、グローバリズムにより、仕事が「外国」に移る懸念が常にある。その状況で、「美しい人口ピラミッド」の場合、若年層が「余る」環境にならざるを得ない。実際、ジャカルタの町では、日本では1人でこなすべき仕事場に2人、3人と「若者」が働いていた。彼らの生産性は極めて悪く、給与水準も低い。だからこそ、Gojekドライバーの成り手には事欠かない。
完全雇用が成立していない状況で、人口ピラミッドが「美しいピラミッド型」の場合、本当に中長期的な経済成長が実現できるのか。何しろヒトが余っているため、生産性向上が「不要」になってしまう。
生産性といえば、ジャカルタの渋滞は生産性を思いっきり引き下げている。政府が交通インフラに大々的に投資しない限り、生産性は低迷したままだろう。生産性が高まらなければ、国民は豊かになれない。生産性が向上しやすいインフラ環境を作った上で、若年層が増えていくというならば、まだ理解できる。生産性向上で実質賃金が上昇し、「豊かになる若い世代」を中心に中長期的な経済成長を実現できるだろう。
インドネシア政府は問題を認識しており、東京に倣いジャカルタ中心部や周辺の交通インフラを整備している。とはいえ、何しろ日本は歴史的に、道路に2輪車が満ち溢れる「バイクの時代」を経験したことがないのだ。東京圏がここまで膨張した最大の理由は、公共交通機関が異様なまでに発達しているため、人々が基本的には「徒歩」で動いていることだ。
現地に赴くとジャカルタのインフラ整備は「手遅れ」の可能性が高いのではないかと考えるようになった。東京の人口はいまだに伸び続けているが、ジャカルタは交通インフラがボトルネックとなり、都市圏の拡張が終わるのではないかと予想している。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。