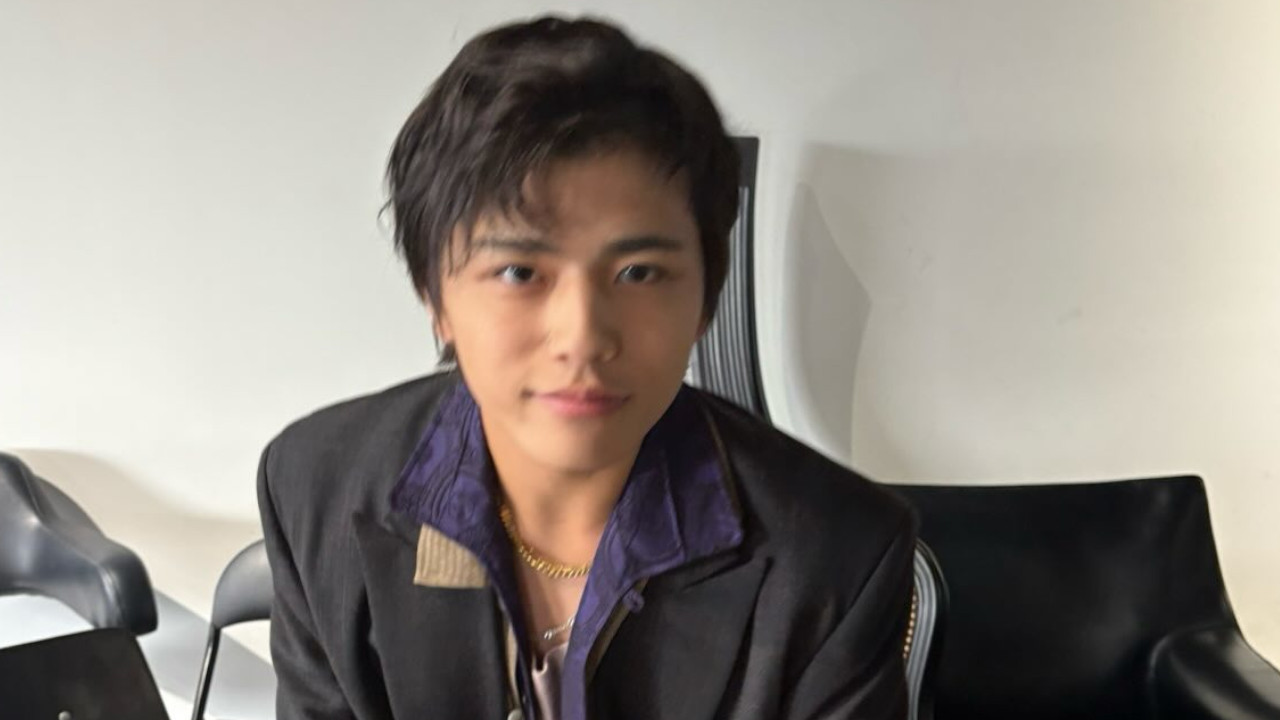やや難しい話ではあるが、経済学者やエコノミストがどれほど奇怪な存在であるかが如実に分かる事例であるため、本稿でご紹介する。
潜在成長率とは潜在GDPの成長率を意味する。そして、潜在GDPとは、日本の労働力や資本がフル稼働した際に生産可能なGDPだ(これを最大概念の潜在GDPという)。
例えば、失業者は「稼働していない労働力」になる。失業者が雇用され、生産活動に従事するようになれば、当然ながらGDP(国内総生産)は増えるはずだ。すなわち、潜在GDPは完全雇用環境下におけるGDPと言い換えることもできる。
ところが、不思議なことに内閣府や日本銀行は、「労働力や資本のフル稼働」の値について、なぜか過去のリソース稼働の「平均」で設定する。最大ではなく平均の稼働率で見るため、潜在GDPが小さくなってしまうという弊害が生じている(これを平均概念の潜在GDPという)。
平均概念の潜在GDPを使用すると、デフレギャップ(総需要の不足)が小さく見える。結果、デフレ対策を打ちにくくなる。
さて、潜在成長率であるが、潜在GDPは以下の三つの要因によって決定されると考えられている。
○労働投入量
○資本投入量
○TFP(全要素生産性)
例えば、労働投入量が増えるならば、論理的に日本の生産量は増えるはずだ。あるいは資本投入、言い換えれば投資の拡大もまた、日本の生産力を強化する。ここまでは分かる。
不思議なのはTFPだ。TFPとは何なのか?
TFPとは、技術革新や技術の活用法の進歩、労働や資本の質向上などによる潜在成長率への寄与として定義される。果たして、「技術革新」「技術の活用法の進歩」「労働や資本の質向上」といった抽象的な概念を、数値データ化することができるだろうか。不可能だ。
例えば、日本の経済が5%成長したとしよう。その期間、労働投入量の増加によるGDP成長への寄与度が1%、資本投入量増加分の寄与度が2%とする。労働投入量や資本投入量“だけ”がGDPを決定するならば、日本の経済成長率は3%のはずだ。ところが、現実の成長率が5%だった場合、2%分、大きくなってしまう。
この“乖離分”について「TFPの向上によるもの」と考えるわけだ。
実は、TFPは事前には決定できない。あくまで、経済成長率が確定し、そこから労働投入量と資本投入量の寄与度分を差し引いたものがTFPであると計算されるわけである。
例えば、労働投入量と資本投入量に変化がなく、それでも実質GDPが拡大した場合、
「TFPが高まったため、潜在成長率が増えた」
と解釈されるのだ。
さて、内閣府のGDPの算出方法の見直しに伴い、日本経済の中長期の実力を示す潜在成長率が、これまでの0.4%から0.8%へと跳ね上がった。
GDPが統計手法の変更により成長したものの、労働投入量と資本投入量が劇的に変わるわけではない。労働投入量や資本投入量が変化していないにもかかわらず、いきなりGDPが31兆円も増えてしまった。というわけで、内閣府は、
「全要素生産性(TFP)の伸びとして潜在成長率の推計に反映された結果」
と、潜在成長率が倍増した理由を説明している。
ポイントがお分かりだろうか? 式で書くと、
【TFP=経済成長-労働投入量の寄与度-資本投入量の寄与度】
なのである。そして、
【潜在成長率=労働投入量の寄与度+資本投入量の寄与度+TFP】
である。
経済成長すれば、TFPは自動的に高まる。TFPが高まれば、潜在成長率は伸びる。労働投入量と資本投入量が伸びなかったとしても、経済成長しさえすれば、潜在成長率は上昇するのである。
逆に、経済成長しない場合、潜在成長率は低下する。わが国はデフレーションにより、1998年以降、経済が成長しない状況が続いている。結果的に、潜在成長力は下がって当たり前なのだ。
日本は経済成長していないために、潜在成長率が低い。ただそれだけの話なのだが、経済学者やエコノミストたちは低い潜在成長率を構造改革に利用してきた。
「日本の潜在成長率は低い。潜在成長率を高めるためには、労働投入量を拡大すればいい。そのためには、雇用の流動性を強化し、外国移民を受け入れるべきだ」
「日本の潜在成長率は低い。潜在成長率を高めるためには、資本投入量を拡大すればいい。そのためには、各種の規制を緩和し、企業の投資を促せばいい」
と、日本国内で構造改革が推進され、さらに緊縮財政でデフレが深刻化すると、経済成長率は低迷する。すると「潜在成長率が低い。構造改革が必要だ」という話になり、またまた構造改革が…。
現実には、日本がデフレから脱却し、経済成長率が上昇すれば潜在成長率もまた高まる。実際に内閣府が統計基準を変更し、GDPが約31兆円増えた結果、潜在成長率が倍増したわけである。
ところが、経済成長すればTFPが向上し、潜在成長率は高まるという単純な事実を、経済学者やエコノミストは認めようとしない。どれだけ頭が悪いのか。
繰り返すが、日本は潜在成長率が低いため経済成長しない、のではない。デフレで経済成長していないから、潜在成長率が低いのである。
この当たり前の話を国民が理解し、潜在成長率の低迷を構造改革に利用させないようにしなければならない。日本がデフレから脱却し、GDPが堅調に成長を始めれば、TFP向上により潜在成長率も勝手に上がっていくのである。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。