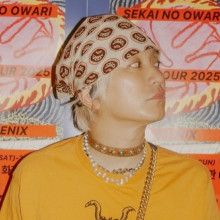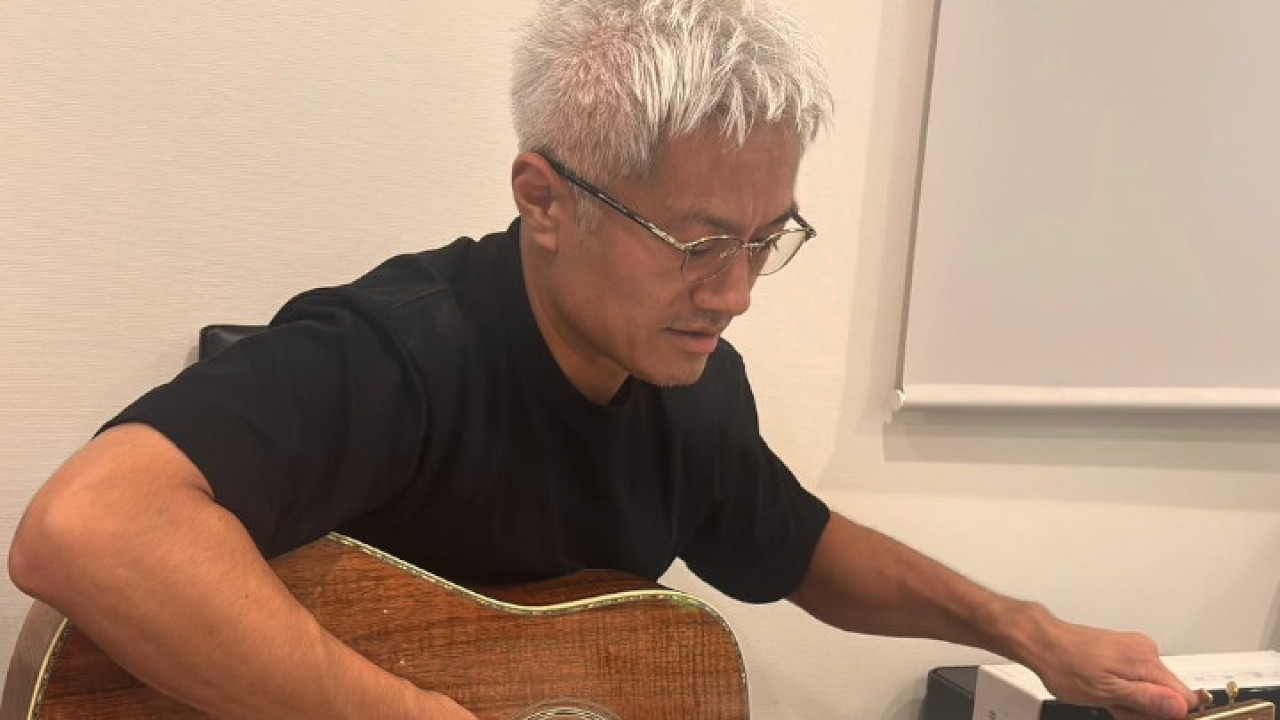消費税増税とは、要するに「消費に対する罰金を強化する」ことを意味する。罰金を増やされた国民は、消費を「実質の量」で減らしていく。分かりやすく書くと、今まではパンを100個買っていたのを、95個に減らす、という話だ。
実質消費の減少は、生産数量が減ることそのものである。国民の実質賃金は、生産性、つまりは生産者一人当たりの生産数量(及び労働分配率)で決定される。消費税増税で生産数量が減ると、国民の実質賃金は下落。実質的に所得が減った国民は、さらに消費“量”を減らすという、悪循環に突入する。
信じがたい話だが、’14年4月の消費税増税は、日本をデフレに叩き込んだ’97年4月の増税以上に、日本国民の実質消費を減らしてしまった。いや、正しくは“減らしていっている”のである。
図では、X軸(横軸)が四半期となっている。Q20とは、つまりは「20四半期後」であるため、消費税増税前後から5年間の値を見ているわけだ。
また、図では実質の消費として、実質GDPの「持ち家の帰属家賃を除く家計消費支出」を採用した。理由は、持ち家の帰属家賃を含むと、実態が見えなくなってしまうためである。
ご存知ない読者がほとんどだろうが、GDP統計や消費者物価指数では、持ち家に対する「架空の家賃」が帰属家賃としてカウントされている。帰属家賃とは何かといえば、実際には家賃を支払っていない住宅(持ち家など)について、通常の借家や借間と同様のサービスが生産され、消費がされたものとみなし、市場価格で評価した計算上の家賃のことである。つまりは「架空家賃」だ。
というわけで、実際には支払われなかった帰属家賃を除き、二度の消費税増税期の駆け込み消費“前”の四半期、つまりは’96年10―12月期、’13年10―12月期を1とし、その後の実質消費の推移を比較したのが図になる。
図からも分かる通り’97年よりも’14年の方が、駆け込み消費の規模も、「駆け込み消費後の落ち込み規模」も、共に大きくなっている。ここまではまあ、いいとしよう。
問題は、’97年増税期は実質の消費が12四半期後、つまりは3年後に増税前の水準に回復し、さらには増税前の駆け込み消費の水準を上回るところまで「拡大」したにも関わらず、’14年時は全く見られないという点である。
信じがたい話だが、’14年増税時は、5年後(’18年10―12月期)に至っても、増税前の駆け込み消費“前”の水準(’13年10―12月期)にすら戻っていない。
’97年時は、実質の消費が4年以上かけたものの、一応、元の水準に戻っているため、「U字型」と表現し得る。それに対し、’14年は明らかに「L字型」だ。
実質消費の落ち込みは、’14年時の方が’97年時よりも酷い。ところが、’97年の消費税増税は日本をその後、長期のデフレに叩き込んだ。その’97年時よりも、’14年の方が実質の消費の落ち込みは激しい。
この状況で、もう一度、増税を強行するというのか。
実質の消費が減るということは、目の前の「販売数量」、「生産数量」の減少そのものである。現在の日本は、少子高齢化に端を発する生産年齢人口比率の低下を受け、人手不足が深刻化している。
直近の失業率は2.5%であるが、これは完全雇用に近い水準だ(日本の完全雇用の失業率は2%強)。それにも関わらず、実質賃金が上昇していない。つまりは、企業が生産性向上の努力をしていない。
理由の一つが、’14年4月の消費税増税による販売数量、生産数量の落ち込みであることは疑いない。実際に、日本の実質賃金は、’14年第2四半期以降、急激な低下を示した。目の前で販売数量が減っている以上、経営者は生産性向上に前向きにはならない。その反対側で、人手不足は人口構造の変化の影響により容赦なく進行する。
結果的に、雇用の改善と実質賃金の下落が“同時”に起きているのが、現在の日本だ。
ところで、半年後に迫った消費税率の引き上げに向け、外食や小売業界において、商品の価格表示を見直す動きが相次いでいる。つまりは、値上げだ。
生産性が低迷し、実質賃金が上昇していない(=販売数量が増えていない)状況での値上げは、単にさらなる実質消費の減少を引き起こすだけである。
しかも、各社の値上げは需要増によるものではなく、消費税増税に備えてのものなのだ。つまりは、オイルショック期と同じ、コストプッシュ型インフレである。コストプッシュ型インフレは、実質賃金のさらなる低下を引き起こす。
そもそも、’14年の消費税増税により実質消費が減少してしまったことこそが、安倍政権下の実質賃金の低迷の主因なのである。このまま’19年10月に増税を強行すると、さらなる実質消費の縮小、生産性の低迷、実質賃金の低下という悪循環に“確実に”突っ込む。
安倍政権が少しでも国民のことを考えているならば、消費税増税の凍結(せめて延期)を決断しなければならない。
消費税増税の根拠は、財務省の「PB至上主義」である。
財務省は、とにかく計画通りにPB赤字幅を圧縮できれば、国民の生活はどうでもいいのであろう。さもなければ、デフレ期のPB黒字化など、目標に設定できるはずがない。
我が国は早急に諸悪の根源であるPB黒字化目標を破棄し、財政健全化を目指すならば、せめてグローバル標準の「政府の負債対GDP比率の引き下げ」に切り替えなければならない。さもなければ、デフレ期の消費税増税が繰り返され、国民の貧困化と国家の小国化が継続してしまう。
********************************************
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。