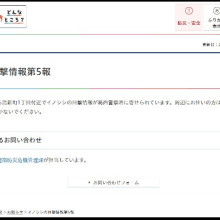その妻・庸子は、早稲田大学教授だった伊地知純正の次女で東京女子大学英文科卒業、こちらも学生時代から才媛として知られていた。英語はもとよりペラペラで、「大蔵省内でも“達人”で知られていた宮澤よりむしろ堪能」とも言われたくらいだった。ためか、かつての宮澤派担当記者のこんな証言が残っている。
「記者懇談会で宮澤邸へ行くと、たまにだが夫人の姿を見かける。すると、突然、宮澤と夫人の間で英語でのやりとりが始まるんです。要するに、他人に聞かれたくない話は英語でやる。ちょっとイヤ味だったが、われわれのことなんかまったく意に介さなかったな」
宮澤の父親は元代議士。長男の喜一以下3人の兄弟は東京帝国大学法学部卒の「秀才3兄弟」として誉れ高く、次男は自治省(現・総務省)事務次官を経て広島県知事、参院議員。三男は外交官と一族はエリートの“集団”だったことも手伝ったか、宮澤の気位は一貫して高かった。こうしたことから、他人を見下すふうに取られることも少なくなかったのである。
ために、かつて宮澤と一度だけ酒席をともにした田中角栄元首相のこんな“宮澤評”が残っている。宮澤は酒が入ると顔が青くなり、論理ますます冴え渡って持説を譲ることがなかったのである。
「角栄は言っていた。アイツは食えんなあ。秘書官なら第一級だが、政治家としてはまだまだだ。二度と一緒に酒を呑もうとは思わんな』と。叩き上げの角栄とエリート臭さプンプンの宮澤とは、終生、まったく合わなかったのです」(元田中派担当記者)
その宮澤は前任の海部俊樹と同様、最大派閥・竹下派の“意向”で首相に担ぎ上げられた。当時、竹下派会長代行として「剛腕」を振るっていた小沢一郎(現・自由党代表)が、宮澤を含めた渡辺美智雄、三塚博の三者と面談、竹下派として宮澤を支持することを決めたのだった。背景は、頭は切れるが政治力には難があると見ての「ミコシは軽くてパーがいい」という海部のときと同じ“論法”からであった。
ちなみに、小沢によるこの“三者面談”は、自民党内から「若造がナニ様だと思っているんだ」という罵声とともに、「竹下派支配による“モロの権力二重構造”が明らか」との批判の声が渦巻いたのだった。
そうした中で、宮澤内閣は発足した。宮澤は自らの“体質”を具現させるように、「政治改革」を掲げ、「品格ある国家」を内閣のキャッチフレーズとした。
しかし、この宮澤政権は海部政権同様、竹下派の“掌の中”でキリキリ舞いに終始した。決断力の甘さも手伝ってコメを中心としたウルグアイ・ラウンド(新多角的貿易交渉)で迷走、掲げた「政治改革」も竹下派の“ドン”金丸信が佐川急便事件にひっかかり、脱税などが重なって議員辞職、逮捕でそれどころではなかった。「品格ある国家」のキャッチフレーズは、むしろ逆行した。そのうえで“一発逆転”を策した解散・総選挙も敗北と、ズタズタになって退陣を余儀なくされたのであった。
ために、この総選挙敗北を機に、昭和30年(1955年)11月15日の自民党と民主党による「保守合同」で誕生した自民党は、一度として手放したことのなかった長期政権に終止符を打つことになった。時に、平成5年(1993年)8月である。宮澤は徳川幕府最後のランナー慶喜になぞられ、「徳川十五代将軍」と揶揄されてもいる。
一方、こうした宮澤を支えた妻・庸子はというと、一般的な政治家夫人とはいかにも一線を画したそれだった。当時の宮澤派幹部のこんな証言がある。
「庸子夫人は体があまり丈夫でなかったこともあるが、表舞台はもとより舞台裏でも一貫して“政治”に首を突っ込むことはなかった。宮澤の選挙の応援に顔を出したのも、昭和28年に初めて参院選に名乗りを上げたときだけで、以後、一度として後援会への出席なども含めて姿を見せていない。
また、我々が宮澤邸に行っても夫人はまず顔を見せない。酒や肴の用意などは、すべて3人の書生がやっていた。これは、宮澤夫妻の“暗黙の了解事項”で、政治をやるのは自分、妻はタッチしなくて結構、束縛はしないという徹底した“欧米流合理主義”に徹していた」
ナルホド、夫妻の結婚の経緯からして、芸人のタカアンドトシならぬ「欧米か」というものだった。実は意外、宮澤の“ナンパ”から始まったそれだったのだ。
=敬称略=
(この項つづく)
小林吉弥(こばやしきちや)
早大卒。永田町取材48年余のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『決定版 田中角栄名語録』(セブン&アイ出版)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。