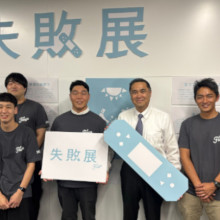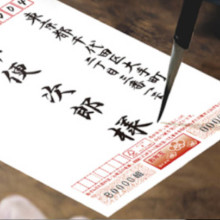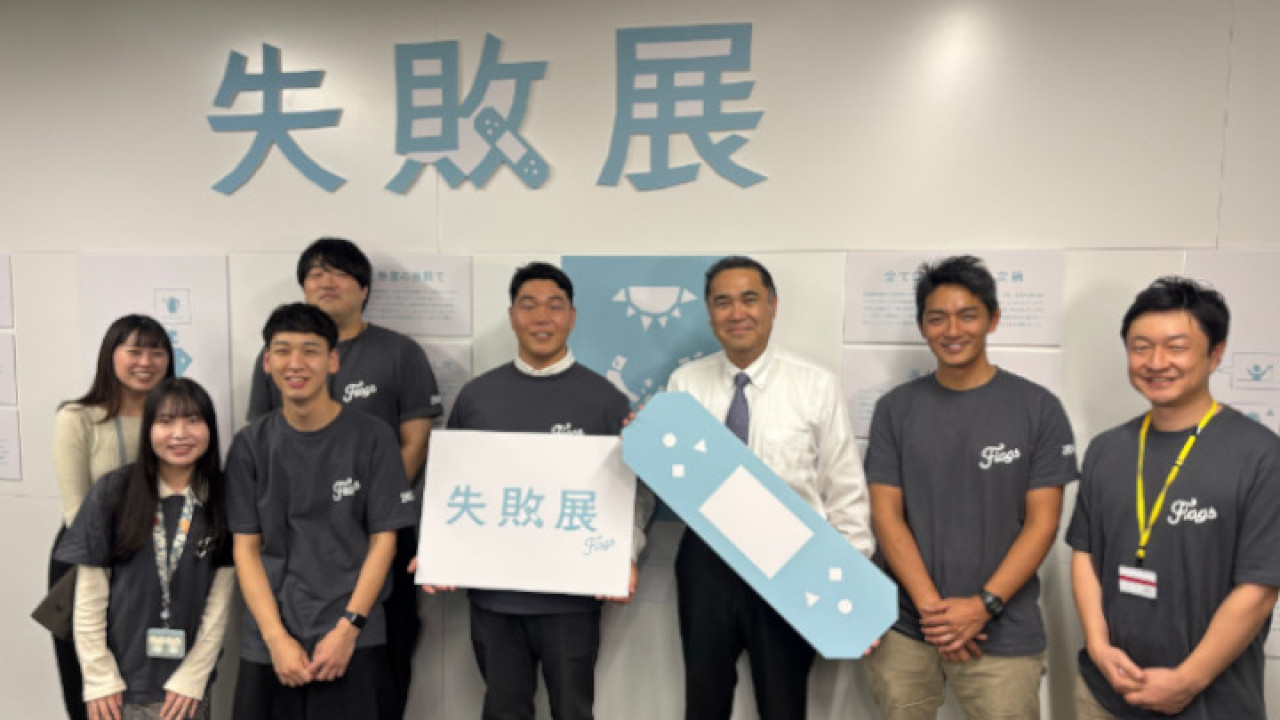「田中の映画好きは昭和29年ごろのまだ副幹事長時代からで、『政界一の映画好き』の声もあった。田中自身から高峰秀子の『二十四の瞳』を観て、涙が止まらなかったとも聞いている。蔵相時代でも、ちょっと時間ができると、よく記者や秘書官に『おい、みんなヒマか。映画へ行こう』と声を掛けていた。有楽町や日比谷にはよく出掛けた。そんなときの田中のいでたちは、お忍びのつもりか大きなマスクをかけソフト帽を目深にかぶってたから、かえって目についたものです。時には、どこからかフィルムを借りてきて大臣室の隣の部屋で、皆で“映画鑑賞会”をやったこともある。そのときは、『局長を全部呼べッ』と“号令”を掛けていましたね。下駄ばき、ナニワ節の田中のイメージとは異なり、特にロマンチックな映画が好きだった」
年配の映画ファンならご存じであろう『哀愁』『嵐が丘』『心の旅路』、中でも『オーケストラの少女』の主演女優、可憐な姿を見せたディアナ・ダービンには入れ込んで、つくづく「こんな女を女房にしたいなぁ」などとも言っていたそうだ。
すでに有名女優だったこのディアナ・ダービンのブロマイドは戦地でも忍ばせており、上官に発見され「国賊」としてビンタをくらったこともあったのだった。
ちなみに他で好きな女優はデボラ・カー、グリア・ガースン、ヴィヴィアン・リー、国内では吉永小百合、佐久間良子のファンでもあった。「外見は穏やかそうでポッチャリ型が田中の好み」(前出・元大蔵省担当記者)で、なるほど佐藤昭子、辻和子の愛人2人もこのタイプに属する。その上で、田中は「オレは旅の泥足をタライで洗ってくれるような女がいい。女房は家のことをしっかり守り、オレに外で存分に仕事をさせるような女が好きだ」との“田中語録”もある。一方、佐藤、辻ご両人とも、例の大きなマスク、目深な帽子のお忍び姿でやはり有楽町、日比谷での“映画デート”はやっていた。時にはクライマックスシーンのさなか、隣座席の佐藤に、「なっ、分かるだろう。オレにはお前が必要なんだ」と囁いたこともあると、これは佐藤自身が述懐しているのである。
さて、そうした中で、昭和40年6月、田中は第1次佐藤栄作改造内閣発足とともに自民党幹事長に就任した。47歳1カ月にして党のナンバー2、大番頭として国会運営から党の人事、選挙を取り仕切る立場に立った。その多忙ぶりは蔵相時代とは比較にならないものである。同時に、天下取りへの視界は、蔵相時代からさらに開けてきたようであった。田中は佐藤昭子に対し、それまでは「政治の醍醐味は首相になることではなく、政権政党の幹事長になることだ」が口癖だったが、「おい、これでオレは天下を目指せるかも知れないぞ」と口にしたのだった。
とともに、その体制を固めた。蔵相政務秘書官だった佐藤昭子を当時の「砂防会館」内の個人事務所を総括する秘書とし、党の政策担当に後にロッキード事件で逮捕された自民党職員歴のある榎本敏夫、マスコミ担当に共同通信記者から転身の麓邦明、東京タイムズからの早坂茂三を配した。麓は明晰な頭脳と政策能力に富み、早坂は文章も弁も立った。天下取りに、スタンバイの布陣を敷いたということだった。
一方、田中は毎日、夕方になるとこの事務所に立ち寄り、執務室に陣取ると好きなオールド・パーの水割りを口にした。秘書たちの報告を聞きテキパキと指示を出す一方、大部屋に移っては国会議員、新聞記者たちと談論風発することも少なくなかった。当時の田中幹事長番の記者たちが言っていた。
「元来、人との関係には几帳面だった田中は、秘書ら事務所スタッフには口を酸っぱくしてこう言っていたそうです。『実るほど頭の下がる稲穂かな、ということだ。来客には誰あろうとも丁寧な言葉を使え。お前たちの評判が悪いとオレの評判が悪くなる』と。ために、国会議員の使いで来たその秘書や警衛の人たちにも、決してぞんざいな言葉が飛び交うことはなかった」
事務所スタッフたちの緊張感も伝わってくる。すでに、自民党内はもとより野党からも一目置かれる実力者になっていた田中には、「日の出の勢いの幹事長」との声が聞かれ始めていた。
(以下、次号)
小林吉弥(こばやしきちや)
早大卒。永田町取材46年余のベテラン政治評論家。24年間に及ぶ田中角栄研究の第一人者。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書、多数。