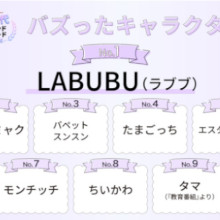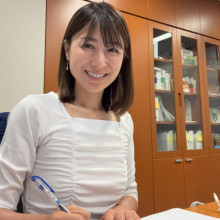では、なぜ、そこまであのケロリン桶は全国に広まったのか。テレビ朝日「ワイド!スクランブル」の特集で解説した。
製造元の内外薬品(現:富山めぐみ製薬)は一般の薬局で販売開始する際に、宣伝に力を入れた。1958年(昭和33年)にはCMソングを制作してラジオで流したりもしたが、広告費の高さなどで社内からは批判の声が上がったという。
その時、ある広告代理店から「銭湯の桶に広告を載せませんか」という提案を受け、1963年(昭和38年)にケロリン桶が誕生した。当時は木製の桶が主流だったが、東京オリンピックを控えて衛生面からプラスチック製の桶への切り替えが進んでいたときで、そのタイミングにこの桶を全国の銭湯に安く販売することでケロリンの宣伝をしたのである。赤い「ケロリン」のロゴが目立つデザインも、広告効果を高めた。ケロリン桶は、全国の銭湯や温泉、ゴルフ場などに広まり、現在も多くの場所で見られる。
実は、製造されて1年間は黄色ではなかったという。日本銭湯文化協会の町田忍理事は「登場した時は白だったんですけど、白は汚れが目立つというので、すぐ黄色に変わりました」と話す。また、ケロリン桶には、関東サイズと関西サイズがあり、関西サイズは、かけ湯を湯船から直接くみ取る文化があるため、小さめに作られている。
昭和30年代は、家に風呂がある一般家庭はまだ少なく、銭湯や共同浴場が日本各地に多くあった時代だった。銭湯の桶に広告を出すという目のつけどころはマーケティングとして先見の明があったと言える。
銭湯は1968年(昭和43年)をピークに減少し、それに伴い、桶の製造量も伸び悩んだが、現在も年4~5万個のペースで納入が続けられているという。また、ケロリン桶は銭湯文化の象徴として、レトロなデザインが人気を集め、現在はヴィレッジヴァンガードなどの雑貨店やオンラインでも販売されている。