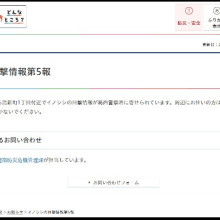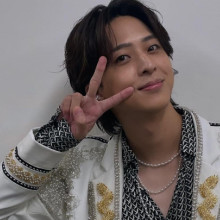財政破綻論と「改革」の組合せは、要注意である。なにしろ、彼らが推す「改革」を実施したとき、必ず「誰か」が得をし、別の「誰か」が損をすることになる。そして、大抵のケースで、損をするのは一般の日本国民だ。
要するに、彼らが求める「改革」は、後ろにいる誰かのレント・シーキング(自らに都合よくなるよう規制を設定、または解除させることで超過利潤を得ようとする活動)を実現するためである場合が多いのだ。
彼らは、実際には財政などどうでもいいというか、日本の財政が破綻しないことなど理解している。単に、誰かの得となる「改革」を実現するために、財政問題を持ち出しているに過ぎない。
典型的な例が、混合診療を巡る議論である。
日本政府は6月12日に発表した成長戦略に、保険診療と保険外診療(いわゆる自由診療)の併用を「例外的」に認める混合診療の拡大を盛り込んだ。
今秋をめどに、まずは抗がん剤の分野に混合診療が適用される。もっとも、経済界や一部の政治家が求めている「混合診療の全面的解禁」は見送り、あくまで例外的適用という立場を崩していない。
過去にも、厚生労働省は先進医療の分野において、混合診療を認めている。とはいえ、いずれ自由診療を「保険適用にする」ことを前提としていることに変わりはない。
さらに、成長戦略の中には、医薬品や診療の「保険適用」のための審査を迅速にするために、外部機関による専門評価体制の新設を盛り込んだ。
これまでは、1件当たり半年以上を必要としていた審査期間を、3カ月程度に短縮することを目指す。特に保険適用が望まれている抗がん剤の分野において、新薬を迅速に認可し、保険適用とし、医師や患者が金銭的に使いやすくすることが目的だ。
現在も、自由診療を保険診療と併用することはできる。
とはいえ、日本政府は混合診療を原則的に認めていないため、両診療を併用すると、保険診療分に対しても政府の公的医療費は支払われない。保険適用分を含めて、全額自己負担となるのである。
これを改め、両診療を併用した場合に「保険適用分は政府の公的医療費で支出するべきだ」というのが、混合診療推進派の主張だ。
それに対し、日本医師会などは「患者が受けられる医療サービスに、金銭的事情から格差が生じる」と反対している。
筆者はもちろん混合診療の解禁には反対で、
「単に自由診療を保険適用に組み込んでいけばいいだけの話ではないか」
と、考えている。
外国で実績がある抗がん剤などについては、速やかに保険適用とし、患者の負担を最小限に抑えたまま、国民幅広く先端の医療サービスを受けられるようにするべきという意見である(「速やかに」とはいっても、充分かつ慎重な審査が必要なことは、今さら書くまでもない)。
ところが、こうした主張を口にすると、即座に、
「財政問題があるのだから、そんなことができるはずがない! 自由診療を次々に保険適用にしていたら、財政がもたない。公的医療費を抑制するためには、混合診療解禁という改革を遂行するしかない」
という反論が飛んでくるわけである。
だが、この手の反論は極めて「奇妙」だ。混合診療を解禁したところで、別に政府の医療費が抑制されるわけではない。
落ち着いて考えてみれば、誰でもすぐに理解できるはずだ。
混合診療を全面解禁すると、政府の公的医療支出はむしろ拡大する。
これまでは自由診療と保険診療を混合させた場合に、保険診療分についてまで公的医療支出が実施されなかったのだ。
すなわち、両診療を併用した場合、患者が全額自己負担をするか、もしくは治療を諦めていたはずなのである。
自由診療と保険診療を混合させた場合に、保険診療分については政府の公的医療費でカバーする。これが混合診療の解禁であり、当たり前だが、
「これまでの政府は自由診療と混合された保険適用分の診療費を支払っていなかった。混合診療が解禁された場合、これまで払っていなかった保険適用分の診療費について、政府が公的医療費の支払いを求められる」
という話になり、どう考えても政府の公的医療費は拡大する。
混合診療の解禁の理由に「財政問題」を上げる人は、頭が悪いのか、それとも全てを理解し、混合診療解禁を「誰かのためのビジネスチャンス」として見ているかのいずれかだろう。
現実に「経済界」が全面解禁を求めている以上、「ビジネスチャンス」として見ている人が多いのだと思うが、実際に混合診療を全面解禁すると、
「国内の医療格差が拡大し、なおかつ政府の公的医療支出は増大する」
という事態になる。
最終的には、我が国の医療サービスはアメリカ的に、医療費の自己負担分が一方的に膨れ上がっていく構造になるだろう。
「おカネがあれば、命が助かる。おカネがないと、助からない」というアメリカ型の社会を、日本国民は本当に望むのか。
もちろん、最先端の自由診療を審査し、次々に保険適用にしていくと、混合診療解禁以上のペースで公的医療支出が増えていく。
とはいえ、我が国はデフレである。デフレが継続している以上、我が国に財政問題などない。政府はデフレ期には国債発行、通貨発行による財政出動で公的医療費の伸びを賄えばいい。
デフレから脱却し、日本経済が健全なインフレ率の下で成長を始めれば、税収が伸びる。
デフレ脱却後は、税収で公的医療費をカバーしていけば済む話だ。
混合診療に限らず、日本の医療サービスの改革を求める人たちは、果たして「誰のために」それを叫んでいるのか。
日本国民はよく見極めなければならない。
三橋貴明(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、わかりやすい経済評論が人気を集めている。