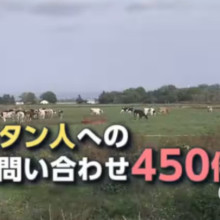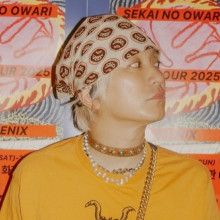生い立ち、環境、何ひとつ過不足のない人間が逆境にさらされることもなく一生を終わるなどは、宝クジの1等に当たるようなもので“奇跡”以外の何物でもない。富める者、貧しき者、強者、弱者の誰にでも、神サマは平等にそれなりの逆境を与えるように世の中はできている。生き抜くための勝負はその逆風に吹き飛ばされてしまうか、踏ん張りどころでもがきつつも前へ出られるかで決まる。後者の人物の一人が、今日の日本の経済大国を端緒に就けた池田勇人元首相である。
池田はエリートとして大蔵省に入って5年目、全身からウミが吹き出すという『落葉性天疱瘡』なる難病を得、生死をさまよう闘病の中で退転をよぎなくされた。この先どうする。絶望の淵に立った池田だったが大蔵省の先輩から愛すべき人間性と強い精神力を買われ、奇跡的に同省への復職を許された。その後、同期に大きく出遅れながらも仕事ぶりの卓抜さから、主税局長、次官と上り詰めた。
その大蔵省時代の池田に目を付けたのが時に権勢を誇った吉田茂元首相で、同省退官後、池田が衆院選出馬、初当選を飾るや第3次吉田内閣でこの1年生議員を大蔵大臣に抜擢した。池田は吉田のバックアップもあってその後も通産大臣などの要職を踏み、やがて「安保」で退陣した岸信介首相の後を受け、昭和35年7月、ついに首相の座にすわったのだった。首相としての池田は「寛容と忍耐」をモットーとし、「所得倍増計画」を推進する中で経済の高度成長を演出、戦後日本の立ち直りへ向けて国民に自信を蘇らせることを目指した。
その池田のリーダーシップの特徴は、豪放磊落、ヤンチャめいた稚気と陽気さの合い間に繊細さが絶妙に綾なすという性格から来た人間的魅力、これに部下が集まり、彼らの英知を結集して結果を出すというものだった。なるほど、大蔵大臣時代には「5人や10人の中小企業の業者が倒産、自殺してもやむを得ない」「貧乏人は米を食わずに麦を食べていればよろしい」と放言連発だったが、愛される人柄からすんでのところで辞任を免れた。通産大臣になると「役人から即大臣になったので人間の修業ができていなかった」と蔵相時代の放言にあっさりカブトを脱ぎ、首相になるや「私はウソを申しません。経済のことはこの池田にお任せ下さい」など茶目っ気たっぷりの自信を示したものであった。国民の多くは苦笑を交えつつ、こうした池田を容認したということだった。そうした中で、表題の「開き直り」の言葉があった。生死をさまよう難病体験という逆境の中から学んだ運命論、人生哲学を物事の判断と自らの行動基準としたということだった。
首相時代の池田は世論による政治家のゴルフと料亭通い批判を受け入れ、私邸で夜毎の酒を堪能した。まずはビールをグラス2杯、次いで郷里広島の銘酒『賀茂鶴』を3合ほど、さらにウイスキーのハイボールを2、3杯、シメはブランデーというのが“定番”だった。とてつもない酒豪であった。酔うと取り巻きを前に持ち前のガラガラ声で唯一の持ち歌、「〜花も 嵐もォ、踏み越えてェ〜」と『愛染かつら』を聴かせるのがこれもまた“定番”だった。歌はとてもうまいとはいえなかったが、義理と人情にもろい一面丸出しで、周囲はそんな池田の人柄を愛したということだった。
そんな池田は首相就任中に喉に癌の病いを得、名神高速道の一部と新幹線開通などで経済大国への道が目に見える形になった中、昭和39年10月24日の東京五輪の閉会式を待って、翌日、退陣を表明した。五輪の火が消えた象徴的な退陣日の演出は、池田を慕ってやまなかった側近の大平正芳(後の首相)によるものだった。翌年8月13日死去、享年65であった。妻・満枝は、「最後まで“ガキ大将”でしたね」と振り返っている。
政治家の人の集まりはその実力度に正比例するといわれている。人が集まらぬ政治家は、その程度の実力にすぎないと見られている。これは一般社会でも同様で、稚気と陽気さ、人間的魅力に溢れた人物には人、英知が集まるが、いくら仕事ができてもムッツリ型の気難しい人物には人も英知も集まりにくいのが通例。逆境の捉え方でその後の人生が変わるとともに、人間的魅力を磨けと池田は教えている。=敬称略=
■池田勇人=第58、59、60代内閣総理大臣。大蔵大臣(第55、61、62代)、通商産業大臣(第2、7、19代)、自由党政調会長・幹事長などを歴任。「所得倍増計画」を打ち出し、高度経済成長の進展に大きな役割を果たした。
小林吉弥(こばやしきちや)
永田町取材歴46年のベテラン政治評論家。この間、佐藤栄作内閣以降の大物議員に多数接触する一方、抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書多数。