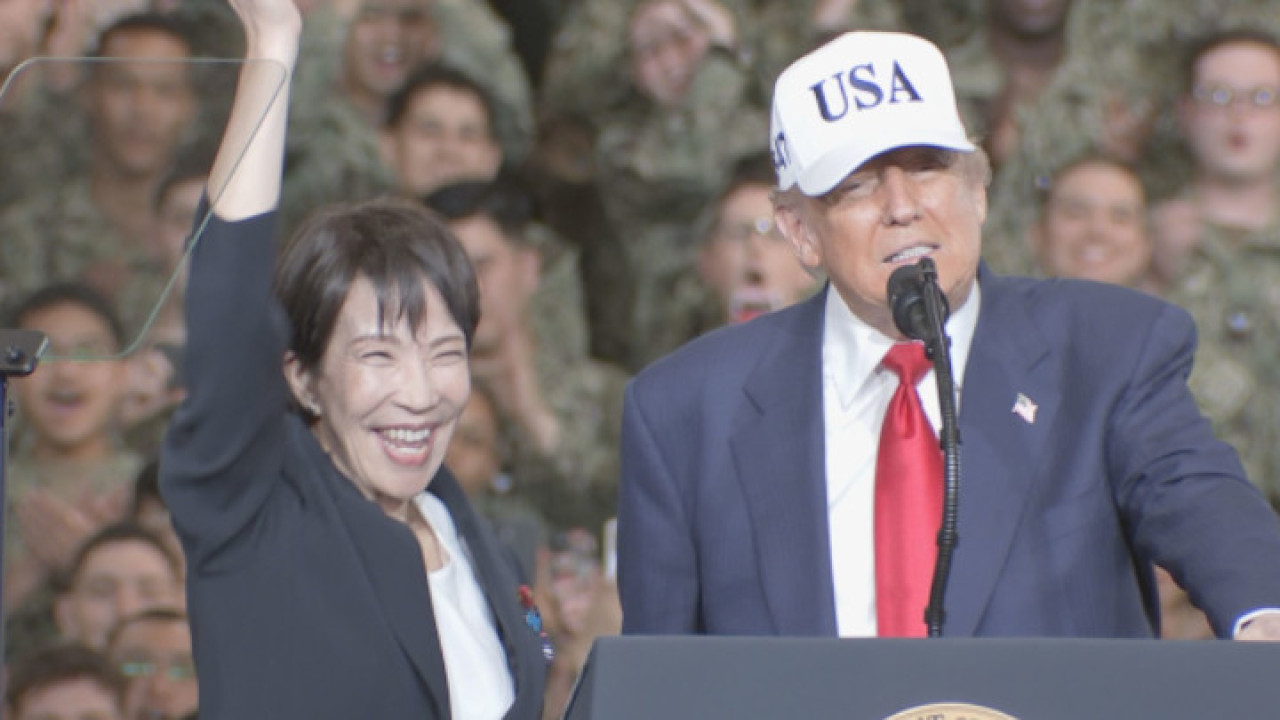神奈川県に住む43歳の会社員、小田高志さん(仮名)は奥さん(専業主婦)と5歳の娘との3人暮らし。奥さんは産後うつと育児ストレスの状態が長く続いて心療内科に通院しているという。
「最近はヒステリックな状態がひどくなるばかりで、先日は娘が妻の腕時計を誤って壊したときには怒鳴ってたたいていました。妻をなだめても逆切れします。このままでは娘への虐待が起こるのではないかと心配です。妻は離婚には同意していますが、娘の親権は争う覚悟です。彼女の両親が入れ知恵しているのです」(小田さん)
離婚問題に詳しい都内の弁護士はこう話す。
「相手が離婚に同意しなくても、民法で定められた条件のいずれかに該当する場合は、離婚訴訟を提起できます。その1つとして『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき』と明記されています」
しかしながら、うつ病のみを理由に離婚請求しても、「強度の精神病」で「回復の見込みがない」とは認められないことが多いという。
「強度の精神病ではなくとも、うつ病が原因で夫婦関係や共同生活に著しい支障をきたしている場合、『婚姻を継続し難い重大な事由』に該当することはありますが、これが認められるハードルも高く、名古屋高裁の判例では次のように判断されており、離婚は認められませんでした」(前出の弁護士)
《名古屋高裁の判例:うつ病が治癒し、あるいは控訴人の病状についての被控訴人の理解が深まれば、控訴人と被控訴人の婚姻関係が改善することも期待できるところである。以上の諸事情を考慮すれば、控訴人と被控訴人との婚姻関係は、現時点ではいまだ破綻しているとまではいえない》
小田さんの場合、奥さんが離婚に同意しているので、離婚自体は問題なさそうだが、問題は親権だ。公平に見て、精神疾患のある母親が親権者となるのは弊害が大きいような気もする。
「小さい子どもの親権は、母親が得ることが多く、仮に母親がうつ病になっていたとしても、子どもを育てることにさほどの支障がないと認められれば、親権者は母親になると考えられます。うつ病を患った母親が家を出て別居に至った事案について、神戸地裁は、離婚理由ありと認めた上で、子どもらの福祉のためには、その親権者をいずれも母と定めるのが相当であると判断しています」(前出の弁護士)
どの判例もそうだが、親権者の指定では、あくまでも子どもの福祉が第一に考慮される。小田さんのケースでは、現実的に虐待の可能性があるか、離婚後の子どもの生活環境が整っているか、両親のサポートが受けられるかなども総合的に考えて親権者が指定されることになるだろう。