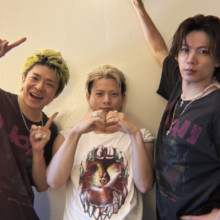同じアパレル企業で、明暗が分かれる結果となった原因はどこにあるのか。
まず、アパレル業界のトレンドの変化を経営アナリストが、こう分析する。
「アパレル業界をけん引してきた若い女性たちが、リーマンショックによる経済不況、東日本大震災による災害によって、衣服に対する価値観が大きく変化し、ファッション性よりも機能性を重視する女性が増えました。現在の服は実用的で、なおかつ安いことが求められているのです」
そういったアパレル業界の潮流にうまく乗れたのが冒頭で紹介したワークマンだ。
「作業着が大半を占めていたワークマンの品ぞろえは、今やカジュアルなスポーツウエアが半分ほど。働く男のための店というイメージが強かったのですが、今では20〜30代の女性を中心に人気を集めています」(業界関係者)
実際、業績は好調で、2018年4〜6月期は、前年同期比で営業利益が14%増の30億円。
同社の人気の理由を業界アナリストは、こう分析する。
「ワークマンは、実用性の高いワーキングウエアに関して、歴史も実績もあります。例えば、真夏の屋根上作業時の暑さにも耐え、真冬の豪雪時でも熱を逃しません。さらに大雨時、生地にしみ込もうとする水の力を抑える耐水圧は、放水で水をかけても弾くほど高いです。こうした過酷な気候、条件に耐えられる衣類は一般的なスポーツウエアだと1万円を軽く超える。ところが、ワークマンの技術で作られた実用性が高いウエアは3000円。これがヒットしないわけがないんですよね」
破格の価格で提供できる秘密はどこにあるのか。
「中国やミャンマー、ベトナムなどの大規模工場で10万点単位で大量生産、これに加え、トレンドにとらわれないシンプルな見た目のため、在庫を大量に抱えても問題ない。つまり、工場の隙間時間を利用して生産できるんですよ。さらに、店舗では目的買いの客が圧倒的に多いため、一等地である必要もなく、華美な演出も不要です。一般的な衣料店と比べても、コストを抑えられるポイントが多いんですよ」(同)
低価格といえば、デフレの優等生、しまむらもそのファッション性と低価格で多くの若い女性を中心に支持されてきた。
有名モデルである益若つばさが、しまむらの衣服の愛用を広言したことでも有名だ。
「しまむらが支持された理由は、値段が安いわりによいデザインの服があるという点と、在庫数も少ないため、他人と被らないオリジナリティーが出せるところです」(業界関係者)
しかし、現在はその牙城が崩壊寸前だ。
2018年2月期の連結売上高は、前期比0.1%減の5651億円、連結純利益は同9.6%減の297億円となり、9年ぶりの減収となったのだ。
しまむらが業績を悪化させた原因を前出の業界関係者はこう指摘する。
「元々しまむらは、様々なメーカーの不良在庫を安く引き取って、オリジナリティーある衣服を提供していました。しかし、しまむらが商品開発した『裏地あったかパンツ』が2015年に、『素肌涼やかデニム&パンツ』が2016年に当たり、ともに100万本前後の大ヒットとなった。これでは大量仕入れは無理だと判断したしまむらは、自社生産にシフトして、他社の不良在庫寄せ集めの『売り切れゴメン商法』から自社企画製品を大量生産する方向に大転換したのです。すると、リピーターが一気に減少した。企画が当たらなかった今年は、売り上げが一気に減ったのです」
しまむらに行けば、以前は宝物探しのようにオンリーワンの商品を探し当てる楽しみがあったが、今はそれが喪失。“しまむららしさ”がなくなり、ファンは減少してしまったのだ。
不況のアパレル業界で、自社の強みを活かしたワークマンが業績を伸ばし、方向転換したしまむらの業績が悪化した。
トレンドが激変したアパレル業界で明暗を分けることになった2社だが、いずれにしても、同業界が大きな転換点に立ちつつあるのは間違いないのかもしれない。