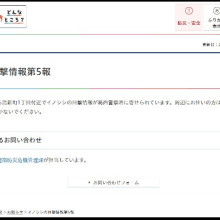そもそも優良企業だった大塚家具が、ここまで苦境に陥ったのはなぜなのか。
大塚家具は借金もなく、2001年に営業利益75億円を記録する家具業界の超優良企業だった。ところが、大塚久美子社長と父・大塚勝久前会長が経営方針をめぐり対立。経営権を巡って親子で激しいバトルを展開する。その対立を発端に内部は混乱が続き、売り上げも低迷してしまったのだ。
「2015年に久美子社長が経営権を獲得し、父の高級路線を否定する改革を行いました。しかし、2016年度は45億円の赤字、2017年度には72億円という過去最大の赤字を出してしまう結果になりました。その後は、創業地である埼玉県春日部市の大型店舗を閉鎖したのをはじめ、2018年10〜11月には、投げ売りに近い大規模セールも行った。しかし、一時的に業績が上向いたものの、通年での販売不振から抜け出せず、売上の減少は止まりませんでした」(経営アナリスト)
そして2018年は冒頭のとおり、32億4000万円の赤字となったのだ。
3年連続で赤字となったことで、潤沢だった内部留保も底をつきかけ、久美子社長は、資金調達に奔走。しかし、これまで10数社と交渉を重ねてきたがまとまらず、暗礁に乗り上げかかっていた。苦闘の末、今年2月にまとまったのが中国関連企業と米投資系ファンドによる増資だ。
中国ECビジネスを手がける「ハイラインズ」がとりまとめる日中企業連合から18億円、米系ファンド「イーストモア」から20億円、合計38億円を第三者割当による新株発行で調達。それに加え、新株予約権を発行して38億円、手数料などを引き、トータルで約74億円の資金を工面した。確保した資金は、自社物流倉庫の自動化や物流システムの効率化に投資するほか、ブランドを再構築するためのマーケティング費用、EC事業に投資してネット販売に力を入れるという。
大塚家具の再建策はこれだけではない。大手家電量販店「ヤマダ電機」と業務提携し、新たな市場開拓を目指す。
「ヤマダ電機は、今や家電だけではなく住宅、家具、雑貨など、住環境全体の商品販売に踏み込んでいる。大塚家具からは家具と家具販売のノウハウを提供してもらい人的交流を進めるという。さらに、一般住宅だけでなく、ホテルなど宿泊施設への家具納入や物流面でも協力関係を構築するという。大塚家具にとってヤマダ電機は、増収に向けた新たな拠点づくり、ミニ販売店という位置づけです」(同)
業務提携はヤマダ電機だけではない。大塚家具は昨年12月、中国の家具販売大手「居然之家(イージーホーム)」との提携を発表した。
イージーホームは1999年創業で今や年商1兆円。中国全土に240店舗を持ち、中国では業界で三指に入る。しかも中国の電子商取引最大手の阿里巴巴集団(アリババグループ)から900億円の出資を受ける超優良企業だ。
「大塚家具は、当然ながら昨年末に業務提携を結んだイージーホームとの資本提携を探りました。超優良企業のイージーホームと資本で提携を結べば、大塚家具も2019年は安泰だったでしょう。しかし、イージーホームは、株式上場の準備などを理由に見送ったのです。上場準備があるためというのは言い訳でしょう。イージーホームも、大塚家具に魅力を感じていれば即資本提携したはずですから」(金融アナリスト)
結局、増資に応じたのはイージーホームの取引先であり、日中間のEC事業を手がけ、イージーホームと大塚家具の業務提携を担ったハイラインズだった。
大塚久美子社長はマスコミに「中国でのネット販売に精通するハイラインズの協力が得られるので、販路開拓などの可能性が高まる」と答え、中国でのネット販売に希望を見い出している。
確かに大塚家具の2018年12月期決算におけるEC事業の売上高は、前期比69・1%増の3億960万円となり、急激に伸びている。
今後の大塚家具の展望を、流通関係者はこう語る。
「今回の調達資金で中国人の爆買いにつなげられるか、あるいは、日本の家具が、イージーホームの200店舗以上の売り場で高く評価される可能性はまだあるのです。それがかなえば、大塚家具も復活する可能性があります。ただ、これがうまくいかなければ、もう打つ手はないかもしれません」
ヤマダ電機と中国のイージーホームという2本の手綱を新たに得た、かぐや姫こと大塚久美子社長の綱渡り経営は、今年こそが正念場のようだ。