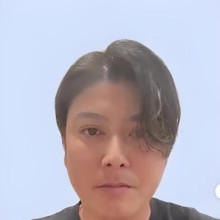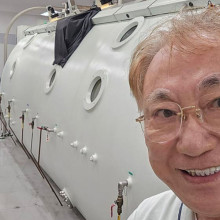プロレスには通常のシングル、タッグ戦以外にも、さまざまな試合形式がある。完全決着をうたったデスマッチや、選手の顔見世的なバトルロイヤルがその一例。また、長期の抗争アングルでは目先を変えて新鮮味をもたせるため、これまで変則ルールもたびたび採用されている。
有名なところでは、新日と国際軍団の抗争におけるアントニオ猪木vsラッシャー木村、アニマル浜口、寺西勇の1対3変則タッグマッチ('82年、'83年のいずれも国際軍団の勝利)。ほかにも猪木と木村は、ランバージャック・デスマッチや髪切りマッチなどで対戦している。
また、目新しさということでは'83年、新日正規軍vs維新軍による4vs4綱引きマッチも記憶に残るところ。絡み合った4本の綱がリング上に用意され、つかんだ綱の両端が一致した選手同士が対戦するという、くじ引き方式だった。
このときは坂口征二vsアニマル浜口(坂口のフェンスアウト反則負け)、前田日明vs長州力(長州がサソリ固めでレフェリーストップ勝ち)、藤波辰巳(現・辰爾)vsキラー・カーン(両者リングアウト)、猪木vs谷津嘉章(猪木が延髄斬りからのフォール勝ち)の組み合わせとなった。
もちろん、事前に対戦者は決まっているのだが、くじ引きの偶然を装うことで藤波vs長州の“名勝負数え歌”の再現や猪木vs長州の頂上決戦を後回しにつつ、ファンの関心を惹こうという試みである。
ほかにも変則ルールの試合は、相手チーム全員を敗退させるまで続くイリミネーションマッチや3人(3組)同時に闘う3WAYマッチなど多種多様だが、いずれにおいても勝負というよりゲーム性が高く、そもそも完全決着を目的としていないこともあって、いわゆる名勝負とはなりにくい。
そんな中、今なお語られるのが'86年3月26日、新日vsUWF5対5イリミネーションマッチである。同大会では、当初、猪木vs前田がメインイベントとして発表されてはいたものの、これを猪木が「UWFリーグ戦を勝ち抜いた藤原に勝ったばかりで、なぜ2番手の前田とやる必要があるのか」と、前田戦の中止を宣言したことで急きょ決まったものだった。
「これについて“猪木が逃げた”とする声もありますが、猪木の右腕だった新間寿氏は〈前田の取り巻きが猪木の腕を極めたら折ると言いふらしていたため、いまシュートマッチでやっても前田の将来に傷を付けることになる〉と、回避を決めたわけを著書に記しています。それに加えて、UWFとの抗争を長く続けたいとの考えもあったのでしょう」(プロレスライター)
長州率いるジャパンプロレス軍は全日へ移籍。鳴り物入りで獲得したアブドーラ・ザ・ブッチャーは振るわず、マシン軍団も立ち消え状態。WWFとの提携も解消となり、当時の新日にとってはUWF以外に目ぼしい話題がなかった。
発表された出場選手は、新日が猪木、藤波、木村健吾、星野勘太郎、上田馬之助。UWFが前田日明、藤原喜明、高田伸彦(現・高田延彦)、木戸修、山崎一夫。
「メンバーで目を惹いたのは、これまでUWFと絡んでいなかった上田の存在でした。試合形式の珍しさとヒールの上田が新日正規軍入りした意外性への興味から、猪木vs前田が消滅したにもかかわらず、ファンからの事前の評判はおおむね良好。当日の会場も満員となりました」(同)
試合のキーマンとなったのも、その上田であった。新日勢は星野、木村、藤波が、UWF軍は山崎、藤原が脱落していく。
「新日で残ったのは因縁深い猪木と上田。ここで“上田の裏切り”を思い浮かべたファンも多かったでしょう」(同)
だが、そんな予測はいい意味で裏切られる。それまで目立った動きのなかった上田は、前田と対峙するやミドルキックやハイキックを打ち込まれたが、倒れるどころか避けたりガードすることもなく受け切ったのだ。
そうして蹴り脚をつかみグラウンドに引きずり込むと、自ら場外へ飛び降りるようにして前田を道連れに“心中”してみせた。この試合は場外転落=敗戦の特別ルールが付け加えられており、これは「場外カウントを短縮しろ」というUWF側の要求に対し、新日側が「だったら場外はナシで」と決まったものだった。
上田の闘った時間はわずか3分ほどであったが、それでも新日ファンからは救世主として、またUWFファンからはそのタフネスさをたたえられ、大歓声を浴びることになった。その後、猪木が高田と木戸を連続で下して新日軍の勝利となったが、この日の主役は紛れもなく上田だった。
この盛り上がりに味をしめてか、同年5月には両軍のシングル5vs5勝ち抜き戦が組まれたが、猪木と上田がメインのタッグマッチに回ったこともあり(相手はアンドレ・ザ・ジャイアント&若松市政)、特に目立つ波乱もないまま大方の予想通りUWF軍の勝利に終わっている。