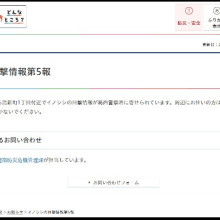集中豪雨の基準に注目すると、3時間と48時間の雨量と土砂災害の危険度を示す「土壌雨量指数」が、その地域で「50年に一度」の数値になると予測された場合に発表となる。最近では今年7月28日に、島根、山口両県を襲った記録的な雨量がこれに当たるという。
「警報の基準は、地域によってばらつきがあります。48時間の場合、雨の少ない北海道は200ミリ、下水道や側溝の大きさにも十分な対策が講じてある西日本の太平洋側は1000ミリ。台風の場合は、930ミリヘクストパスカルで風速50メートルとなっています」(全国紙記者)
運用開始は8月30日。すでに現時点でゲリラ豪雨などによる被害が多発しているが、本当に怖いのは9月〜10月半ばまでの台風シーズンで、集中豪雨が猛烈化するのもこれからなのだ。果たして警報だけで事足りるのか。
防災に詳しいジャーナリストの村上和巳氏が言う。
「地下水脈があって大量の降雨が土壌に浸み込み、地盤が緩んでいるところは非常に危険です。特に、日本海側は雪解け水の対策はできていますが、台風やゲリラ豪雨の対策が手薄なんです。瞬間的に想定外の豪雨が降った場合、にっちもさっちもいかなくなります」
村上氏が指摘するのは、一級河川と比較すると二級河川や中小河川の周囲が非常に危険なことだ。
「日本の河川は、上流と下流に高低差があるため、流速が非常に速いのが特徴です。一級河川は水量も流速もさまざまな場合を想定して厳格に調べてありますが、中小の河川は非常にアバウトなんです。よく氾濫することで知られる東京の神田川などはその典型。水害の多発の原因は、温暖化やラニーニャなどいろいろな説が唱えられていますが、基礎データが不足しているため、原因がはっきりしない。警報も大事ですが、河川の整備なども急務です」
9月以降、「50年に一度」は何度起きるのか。