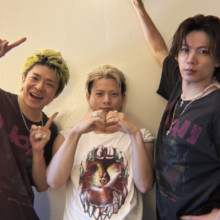ゾンバルトは、ヒトラーに協力したのではないかという嫌疑をかけられたこともあって、戦後しばらくの間、歴史から名前を消された。
だから、戦後の我々は、ウェーバーの教えに従って勤勉に働き、貯蓄に励んだ。その貯蓄が、銀行を通じて企業に融資され、活発な設備投資と生産能力拡大をもたらしたことが、戦後の経済基盤となった。
その意味で、ウェーバーの経済学は、戦後復興期には実に大きな役割を果たしたと言える。しかし、いまはどうだろう。資金不足で設備投資がままならず、生産能力が足りないということは、まったくない。モノもカネも溢れかえっている。足りないのは、供給ではなく、需要の方だ。
ゾンバルトは、フランス革命前、アンシャン・レジーム時代の貴族の家計簿を徹底分析して、重大な発見をする。それは、ガラス製の鏡や絹織物やレースなど、それまでの欧州には存在しなかった商品は、貴族が高等娼婦を喜ばすために莫大な私財を投じて開発させたという事実だ。
そうした商品が、その後、大量生産されて、資本主義が発展したというのだ。ゾンバルトは、経済を需要側から見ており、現代の経済状況に適した経済学だと、私は考えてきた。
実は最近、『恋愛と贅沢と資本主義』の漫画版が発行された。私が原書を読んだのは10年以上前だが、漫画は原書の10分の1くらいを切り取って、ストーリーを描いている。ただし、その分、論点が浮かび上がって、大きな発見があった。それは、アンシャン・レジーム期のフランス社会が、いまの日本に酷似しているということだ。
第一は、当時のフランスでは、金持ちは税金をいっさい支払わず、すべて低所得の庶民が負担をしていたという事実だ。いまの日本は、そこまでひどくはないが、税・社会保険負担率は、年収100億円の富裕層のほうが、年収300万円のサラリーマンより低いというのが現実になっている。
第二は、都市の形成だ。貴族の贅沢を支えるため、アンシャン・レジーム時代に都市に住む庶民が増えて、都市化が進んだ。いまの日本を見ても、まったく同じ理由で東京一極集中が起きている。
第三は、貴族階級の恋愛三昧だ。いまの新富裕層も、考えていることは恋愛と贅沢ばかりだ。もちろん現代に娼婦は存在しないが、実質的に同じことをする女性が、富裕層に群がっているのだ。
第四は、貴族と庶民の格差がどんどん拡大していったことだ。ただ、18世紀のフランスでは、あまりに浮世離れした貴族の贅沢が庶民の怒りを爆発させ、その後のフランス革命によって、アンシャン・レジーム時代は、終わりを告げた。
いまの日本人が、当時のフランス市民と同じような怒りを共有できるのか、私はそこが一番心配なのだ。