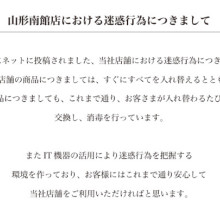「そこで次に注目されていのが、大分から東方に向かって中央構造線の延長線上にある愛媛県なのです。伊方原発に最も近い活断層、あるいは中央構造線の断層帯全体が一度に動き、予想される最大規模のM8の地震が起きた場合、原発周辺は震度7の揺れに見舞われる可能性があるといいます」(サイエンスライター)
歴史を紐解けば、この中央構造線付近では震源が移動する巨大地震が発生している。
「1596年9月1日、愛媛の中央構造線の川上断層で慶長伊予地震(M7.0)が発生し、その3日後には、豊予海峡を挟んで対岸の大分で慶長豊後地震(M7.8)が発生しています。豊後地震の震源とされる別府湾−日出生断層帯は、中央構造線と連続、あるいは交差している可能性がある。注目すべきは、さらにその翌日の9月5日、専門家の間でこれら二つの地震に誘発されたと指摘されている京都を中心とした慶長伏見地震(M7〜8)が発生していること。さらに、その歴史が再び繰り返されるという見立てもあるのです」(同)
慶長伏見地震は、京都・伏見付近の有馬−高槻断層帯、六甲−淡路島断層帯(いずれも中央構造線が隣接)を震源として発生した直下型地震だった。死者は京都や大阪の堺で1000人以上と伝えられ、完成したばかりの伏見城も倒壊したとされる。
「特に、中央構造線の北側付近は日本で最も活断層が多い地域の一つとされています。特に、近畿周辺は太平洋プレートとフィリピン海プレートが陸側のプレートの下に潜り込むことで、二重に強い圧迫を受け続けている。この地に活断層が多いのは、その力で押されて硬い岩が割れてずれ動いたため。上下にずれる断層では、片側が隆起し、もう一方が沈降する。地震のたびにこれを繰り返し、長い歳月をかけて一帯の山地と平野が造られてきたのです」(同)
死者6000人を超える大都市での直下型地震となった1995年の阪神・淡路大震災(M7.3)。このときも、中央構造線の北側に位置する前述の六甲−淡路島断層帯の一部が動いたとされている。
琉球大学理学部名誉教授の木村政昭氏が言う。
「今回の地震で問題視されているのは、大陸側のプレートとフィリピン海プレートの境界。その一部が動いたためにクローズアップされている。しかし、その大本は太平洋プレートからの圧力。そのため太平洋プレートとフィリピン海プレートの境では年間10センチのひずみを重ね、相当ストレスが溜まっているはずです」
そのフィリピン海プレートが沈み込む先は、政府が“最悪の場合死者33万人”と想定した巨大地震と大津波を引き起こすとされる南海トラフがある。
「今回のように内陸型の地震が頻発した場合、その後に東南海、南海巨大地震が起きているのは歴史の示すところ。そのため地震研究者の間では、南海トラフ巨大地震との関連性も指摘されているのです」(前出・サイエンスライター)
“連鎖”は始まったばかりなのかもしれない。