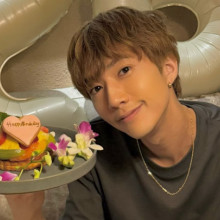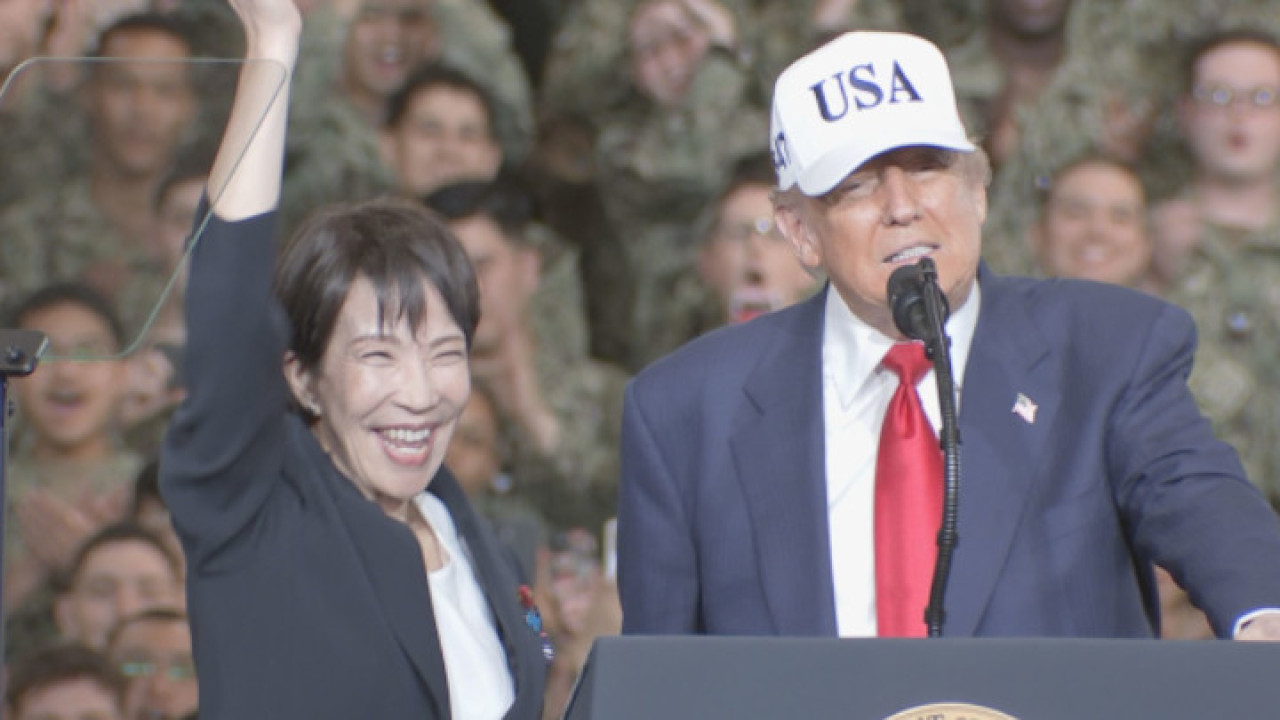というわけで、ギリシャの名目GDP(所得の合計)、インフレ率、そしてPBを左図(※本誌参照)にグラフ化した。ギリシャのPBは、バブル崩壊後の'09年に360憶ユーロで赤字のピークに達し、その後は容赦なき緊縮財政により削減されていった。
'16年には、ついにPBが黒字転換。ギリシャ政府がPB赤字削減に懸命になる、つまりは緊縮財政が継続した結果、ギリシャ国民の所得の合計は、'08年の2500憶ドルから、'16年には1845憶ドルに激減。GDPが8年間で26%も減ってしまった。
ギリシャの経済規模が、4分の3に縮小してしまったのである。日本でいえば、GDPが375兆円に減ってしまうようなものだ。インフレ率の方も、延々とマイナス状況が続き、'16年にようやく+0.013%となった。
バブルが崩壊した国、あるいはデフレ化した国がPB黒字化を目指すと、国民が貧困化する。ものの見事に、ギリシャが実証してくれたわけである。
何しろ、ギリシャ政府はPB黒字化のために「国民からより多くの税金を取り、支出を削った」わけである。所得創出のプロセスにおいて、増税や政府支出削減がなされた場合、「誰か」の所得が減るのは自明の理だ。そして、所得の合計こそがGDPなのである。
ギリシャはユーロ加盟国だ。ユーロ加盟国には金融主権がないため、「国債発行+国債買取」により政府が支出を増やすことはできない。しかも、ギリシャ政府におカネを貸しているのは国際機関、ドイツやフランスの銀行などの「外国」になる。デフォルト(債務不履行)を回避するためには、ギリシャ政府は「国民」からユーロを搾り取り、返済するしかなかったわけである。
というわけで、ギリシャ政府はPB黒字化を強要され、国民はひたすら貧乏になっていく。特に、若年層失業率47%のギリシャでは、緊縮財政とGDP縮小により、現在の所得はもちろん、将来の成長をも犠牲にしてしまった。現在の若者が社会の中核層を成す頃、その半分近くが「働いたことがない」という状況になってしまう。普通に発展途上国化である。
ギリシャの問題については「解決策がない(ユーロに加盟している限り)」が、日本は違う。日本の場合、PB黒字化目標を破棄し、国債を発行。日銀が国債を買い入れ、長期金利を調整しながら支出を拡大すれば、普通にデフレ脱却や経済成長が実現する。ギリシャと日本は違うのだ。それにも関わらず、わが国の政府は相も変わらず「PB黒字化目標」に固執し、国民の貧困化と経済規模の縮小に余念がない。
最新報道によると、日本政府は、
●PB黒字化目標の達成時期を'23年以降に遅らせる。
●政府の負債対GDP比率の数値目標を掲げる。
との見込みである。
現在の日本は、デフレや日銀の量的緩和政策で、金利が極めて低迷している。名目GDPを成長させていけば「名目GDP成長率>国債金利」の状況を維持することが可能で、政府の負債対GDP比率を着実に引き下げていくことができる。
国債を増発し、政府の負債を増やしたとしても、それ以上に名目GDPが増える。分かりやすい例を出すと、現在、
●政府の負債 900兆円
●名目GDP 500兆円
だとしよう。つまりは、政府の負債対GDP比率は180%である。ここで、政府の負債を10兆円増やし、有効需要として支出したとする。(乗数効果は無視する。また金利はゼロと仮定する)
●政府の負債 910兆円
●名目GDP 510兆円
政府の負債対GDP比率は、178.4%に「改善」する。実際には乗数効果があるため、名目GDPは10兆円以上、増えるだろう。無論、PBは10兆円分、赤字が増えることになるが、本来の財政健全化の定義である「政府の負債対GDP比率の引き下げ」は達成されるのだ。
もっとも、名目GDPを成長させるためには、財政出動が必須である。特に、医療、介護、教育、防衛といった公共サービス、さらには防災インフラ、交通インフラといった公共投資への支出を拡大することが肝要だ。この種のGDPになる需要(有効需要)に政府が支出しようとすると、途端にPB黒字化目標が邪魔をしてくる。
黒字化目標の達成時期が'20年から'23年に延びれば、大丈夫なのでは? などと思うなかれ。PB黒字化の「目標」がある限り、政府はデフレ脱却に足る十分な財政拡大が不可能だ。結果、名目GDPの成長率が低迷し、政府の負債対GDP比率が「上昇する」形の財政悪化が続く。
一つだけ「逃げ手」があるとすると、PB目標から「建設国債」を外すことだ。建設国債に限らず、投資系の財源として「教育国債」「防衛国債」「科学国債」などを発行する。建設国債によるインフラ整備。教育国債による教育強化。防衛国債による防衛力増強。科学国債による科学研究費拡大。これらは明らかに「長期の支出」が必要な分野だ。
今年6月の『骨太の方針2018』において、建設国債を含む「投資系の支出」の財源については、PB目標から外す。最低でも、これが実現できない限り、結局、わが国はデフレ脱却に足る財政拡大は不可能であろう。
改めて記しておくが、日本とギリシャは違うのだ。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。