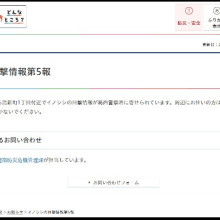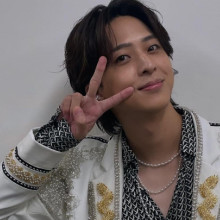「騒動の背景としては、ウォルマート自体の海外戦略の見直しが一番の理由。つまり、先進国からの撤退・縮小、中国、インドへの進出、小売業態からEC(電子商取引)へのシフト。最近ではイギリスのスーパーマーケット・アズダを売却し、その後、すぐにインドのネット通販大手・フリップカートを買収するなど、その動きは加速度を増しているのです」(流通業界紙記者)
しかし、西友は今年1月に楽天と新会社・楽天西友ネットスーパーを立ち上げたばかりで、その新会社で夏から秋にかけて本格営業を開始する予定だ。楽天の三木谷浩史社長はネットスーパーに積極的に関わる方針で、年内にも専用の物流拠点を設置するとも言われるが、本格展開を目指すならば、さらなる投資が必要とされる。
「楽天は携帯電話事業への基地局をはじめとした投資が控えているが、資金的に先行きの見通しがおぼつかない。そのため一部では、目立ちたがり屋の三木谷社長がウォルマートと提携するという事実だけが欲しかったのでは、などうがった見方もされているのです」(経済部記者)
スーパーマーケットのEC対応も、所詮、ネット企業の宣伝の一部にすぎないと見なされているあたりが、ECに押される小売業界の状況を象徴している。
「西友売却騒動で引受先として候補に挙がっている企業も、提携実績のある楽天をはじめ、ドン・キホーテホールディングス、中国のアリババグループと、いわゆるIT企業が多い。GMSをはじめとした、国内のスーパーマーケットが候補に名乗り出ていないのは、少々寂しい限りです」(前出・流通業界誌関係者)
かつてない環境の変化に、小売業界がどう対応していくのか注目だ。外資参入の限界が見えてきたとも言える。 バブル期前後、日本に進出した世界第2位の仏スーパーのカルフールは'05年に、英スーパー最大手のテスコは'13年に日本市場から撤退。そして今回、ウォルマートもとなると“小売業世界ビッグ3”が日本市場から姿を消すことになる。 “消費”と“小売”の新時代を迎えているのかも知れない。