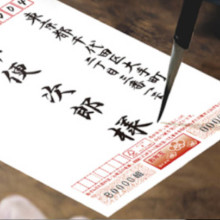さらに徳次は、幸の薄かった幼少時代や自らに降りかかった災難を恨(うら)むのでなく、むしろ、その苦難の日々に自分が受けた“恩”に感謝し、自己の不幸を他の人々に対する共感へと高めた人物だった。
人とのつながりや信頼が、いつの場合でも最優先された。「幸せや喜びを分かち合う」ことを実践し、分かち合えたことがまた自らの幸せや喜びを生むと感じていた。社員に「真似される商品を創れ」と繰り返した。
何かを開発するということは苦労を重ねることである。しかし、その労を惜しむことなく、“真似されることは、結果的には競争を生み、会社の技術を向上させ、それは社会を発展させることにつながる”という考えを持っていた。
他社に真似されることも、結局は自社の、さらには社会の発展につながると発想したのだ。秘密にして自分だけのものにしておこうとならないところに、徳次のスケールの大きさがある。
幸せや喜びを他者と分け合おうとすることも、商品を真似されることを自社の発展につなげて捉(とら)えることも、実際にはとても難しいことだ。しかし徳次にとってそれは言葉だけではなく、常に行動を伴うものだった。
昭和55(1980)年6月24日、午前0時20分、早川徳次は86年間の生涯を閉じた。シャープ株式会社によって行われた社葬には、国の内外から1万人を超す会葬者が詰めかけて、会場の東本願寺難波別院境内を埋めつくした。そしてその中には、多くの一般市民の姿があったという。徳次が、人間として尊敬され、愛された証(あかし)の一つといえるだろう。