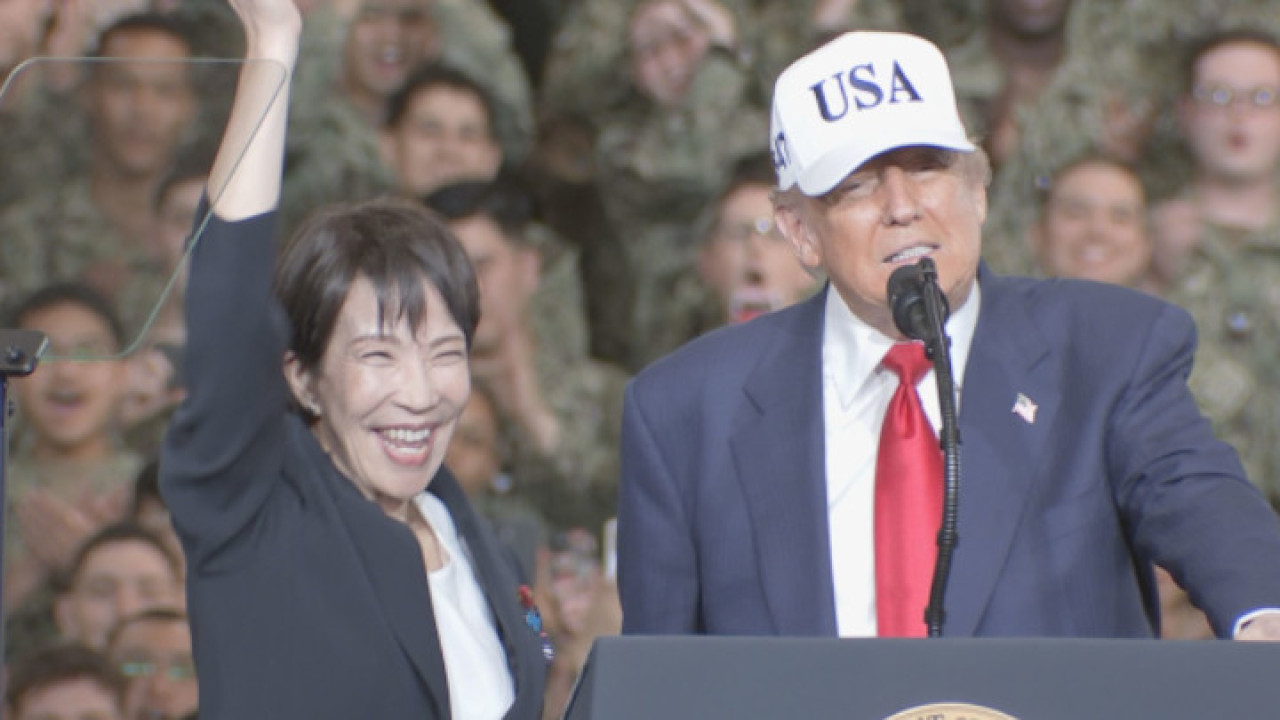これだけ人手不足が深刻化しているにも関わらず、実質賃金は何と「マイナス」で推移。
12月22日に厚生労働省が発表した10月の毎月勤労統計調査確報値によると、物価の影響を加味した実質賃金(現金給与総額)は前年同月比0.1%減。これで、5カ月連続のマイナスである。筆者が重視する「きまって支給する給与」は、速報段階では+0.4%だったのだが、確定値は±ゼロ%に下方修正された。
恐ろしいことに決まって支給する給与は、昨年の9月を最後に、一度もプラス化したことがない。過去13カ月間、日本国民の「決まって支給される」実質賃金は、横ばいもしくはマイナスが続いているのだ。実質賃金が低迷しているということは、生産性の向上が起きていないという話になる。もしくは労働分配率が上がっていないのだ(※実質賃金は「生産性」と「労働分配率」により決定される)。
現在の有効求人倍率は、バブル期をすら上回っている。それにも関わらず、生産者の実質の所得は減少。「おかしい」と、思わない方がおかしいというものだ。
人手不足が深刻化しているのは、もちろん少子高齢化に端を発する生産年齢人口比率の低下によるものだ。しかも、現在は人口のネックである団塊の世代が退職時期を迎えており、退職者が激増している。反対側で、少子化の影響により若者が労働市場に入ってこない。
しかも、いまだにデフレマインドを払拭できない企業は、労働分配率を引き上げる、あるいは生産性向上を追求するのではなく、
「高齢者を短時間低賃金労働者として再雇用し、さらに女性を短時間低賃金労働のパートタイマー・アルバイトとして雇用し、穴を埋める」
という雇用スタイルを採っている。結果、有効求人倍率の異様な上昇と、実質賃金の低迷が両立しているのだ。
左図(※本誌参照)の通り、第二次安倍政権が始まった2013年1月と比較すると、高齢者の就業者数は199万人増加、女性が225万人増加、そして生産年齢の男性就業者が、何と40万人の減少。
日本の就業者数の増加をアベノミクスの「金融政策」のおかげだと主張する人には、是非とも「生産年齢の男性就業者が減少しているにも関わらず、就業者数全体は増えている」現実と、金融政策の関係を説明してもらいたいものだ。一体全体、金融政策がいかに波及すれば、「生産年齢男性の就業者数が減り、高齢者女性が増える」などという結果をもたらすのか。
どう考えても、「人口構造の変化」「団塊の世代の退職」「企業のデフレマインド」「高齢化による医療福祉(主に介護)の需要増」の影響の方が大きい。
もっとも直近の数字を見ると、生産年齢男性の就業者数減に歯止めがかかったかもしれない。'17年10月以降は、3190万人台を回復している。生産年齢の男性が「正規雇用」で雇われ始めた可能性があるのだ。すなわち、これから人手不足は「さらに深刻化していく」という話でもある。
この人手不足を、生産性向上のための投資で解消しようとしたとき、わが国は「経済成長の黄金循環」に入ることになる。
逆に人手不足を外国人労働者で埋めてしまうと、生産性向上は起きず、国民の実質賃金はさらに落ち込んでいく。やがて、わが国は移民国家と化す。あるいは、人手不足解消を諦め、「廃業」が相次ぐと、我が国は発展途上国型のインフレに向かうことになる。まさに、現在の日本の目の前には「チャンスとリスク」が同時に存在していることが分かる。
問題は日本国民の多くがデフレ(人手過剰)に慣れすぎ、人手不足解消法を忘れてしまっていることだ。
なぜ、企業は生産性向上の投資や、フルタイムの正規労働者を「高く」雇おうとしないのか。もちろん「パートタイマー・アルバイト」であれば、いざというときに簡単に解雇できるためだ。つまりは、企業が将来的な需要の継続に全く自信を持てていないのである。
生産性向上のための投資は、効果が出るまである程度は時間が必要だ。とはいえ、フルタイム正規雇用を高く雇うことは、すぐに可能なのである(労働分配率は下がるが)。ところが、企業は生産性向上の投資にも、労働分配率の(継続的な)引き上げにも踏み出せず、短時間労働者の数を増やして補おうとする。当たり前だが、パートタイマー、アルバイトを増やしたところで、「人材」は育たない。
企業はフルタイムの正規雇用を増やし、社内に人材を育成するのではなく、短時間労働者により「その場しのぎ」を選んでいる。これは、将来に禍根を残す。
すでに「氷河期世代」の「蓄積不足・人材不足」が問題を引き起こしている。
先日、旭化成社長が「30代後半から40代前半の人員が少ない」と発言し、批判を浴びた。'90年代後半に就職氷河期に新入社員を雇用せず、育成を怠った結果が「今」なのだ。今、生産性向上のための投資や人材育成を怠ることは、将来を壊す。
今、人材投資をすることで、現在の人手不足を補うと同時に、将来的な生産性向上も達成できる。もっとも、政府が緊縮路線を改めない以上、企業経営者が「将来的な需要の継続」に自信を持てないのも無理もない。
緊縮財政、すなわちプライマリーバランス黒字化目標は、国民の貧困化を招き、日本を小国化していると同時に、「将来の人材」をも潰している。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。