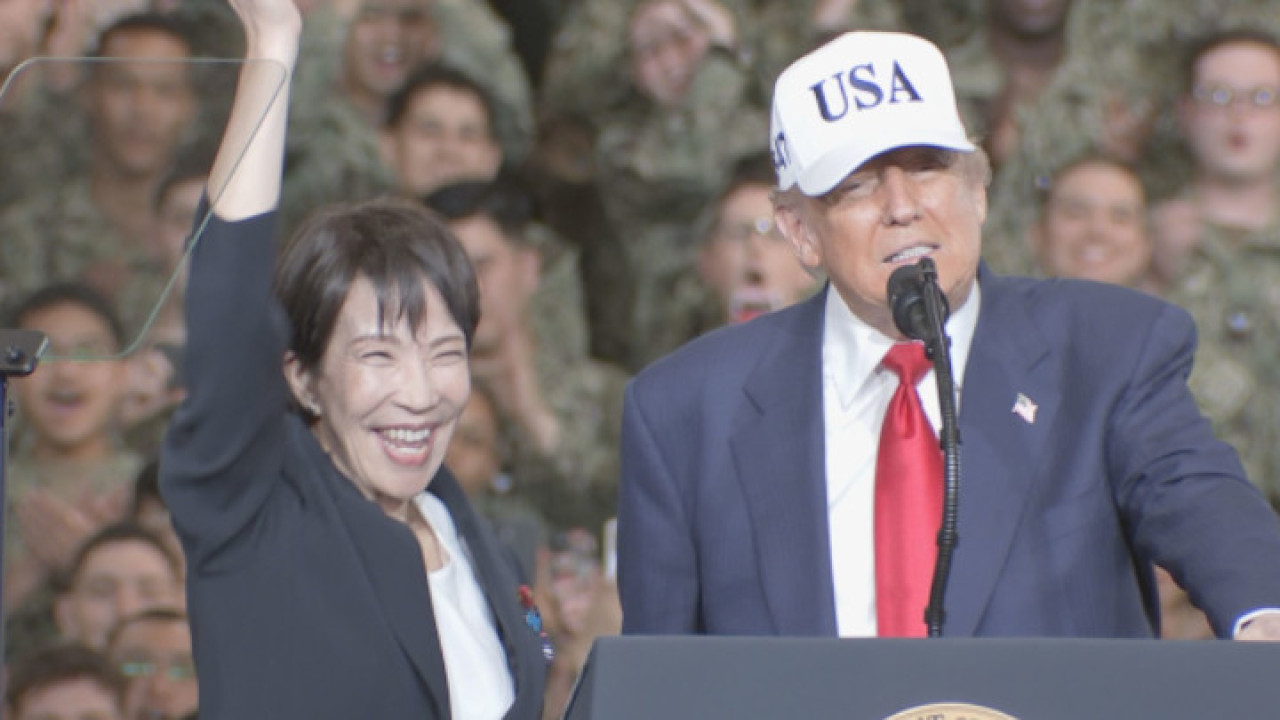現在の年金支給開始は原則65歳だが、これは60歳から70歳の間で自由に選べる仕組みになっている。もちろん、60歳から繰り上げ支給を受ければ、給付は30%減額になる。一方、70歳からもらえば42%増額になる。今回の改革は、年金の上積み率をさらに高めて、80歳程度まで支給開始年齢を繰り延べることを可能にしようというものだ。
選択制なのだから、この動きは庶民に何の影響もないと思われるかもしれない。だが、私は今回の改革が、年金の支給開始を原則70歳へと繰り延べるための布石だと考えている。
一つの理由は、繰り延べをする人がほとんどいないと考えられることだ。厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業統計」によると、平成27年度末で、老齢基礎年金を原則通り65歳から受給している人は63.0%、繰り上げ受給している人が35.6%となっている。一方、繰り下げ受給している人は1.4%にすぎない。なかでも、70歳からの受給を選んだ人はわずか0.4%にすぎないのだ。
これから見ても分かるように、生活が苦しいから、早めに年金をもらうことはあっても、先送りできる人は、ほんの一握りにすぎないということだ。
それにもかかわらず、政府が年金支給開始を80歳まで選択できるようにしようと固執するのは、支給開始年齢の原則を、現在の65歳から70歳へと変更したいという強い欲求があるからだろう。
年金支給開始が60歳から80歳までの間で選択可能ということになれば、なんとなくその真ん中の70歳が原則でもよいような錯覚に陥るためだ。
もう一つ、新しい高齢社会対策大綱では、現状63.4%となっている60〜64歳の就業率を2年後の2020年に67%に高める目標が掲げられる予定となっている。つまり、3分の2の人が、65歳まで働く世の中に今後2年という短期間で持っていき、65歳まで働くことをスタンダードにしようというのだ。
どうやら、役人の頭のなかでは、3分の2まで普及すれば、それが標準になるという感覚があるらしい。
ここで思い出すのが、'14年に行われた公的年金の将来見通しを試算する厚生労働省の財政検証だ。
この推計では、労働市場への参加が進むケースとして、'30年の65〜69歳男性の労働力率が67%に設定されている。そうなれば、現行水準並みの年金給付が維持できるというのが推計の結論だ。つまり、3分の2の男性が70歳まで働き続けることが、年金制度の崩壊を防ぐための絶対条件なのだ。そうした状況を踏まえると、政府が考えている年金改革の方向性が見えてくる。
'20年の東京オリンピックまでに65歳までの継続就業を完成させてしまい、その後、10年程度で一気に70歳までの継続就業を普及させる――。それができた時点で、支給開始年齢を70歳に延ばすのだ。
現在、男性の健康寿命は71歳まで伸びているが、残念ながら、このままいけば老後の悠々自適生活は風前の灯だ。