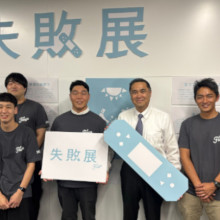羽田の父・武嗣郎は旧〈長野2区〉選出で8期を務めた代議士だったにも拘らず、「世襲政治」を嫌った。これもあって、長男の孜は小田急バスに入った。成城大学ではジャーナリスト志望だったが、朝日と日経の両新聞、“押さえ”としてサッポロビールを受験したがいずれもハネられ、父親の縁故でなんとか小田急バスにもぐり込んだのだった。
小田急バスでは吉祥寺営業所に配属され、車掌が持ち帰ってきた売上金の精算が主な仕事だったが、羽田は算盤がニガ手で、たまたま見回りに来た社長にアキレられたこともある。
「当時の吉祥寺営業所は社員が150人ほどいたが、半数が車掌などの女性で“環境に恵まれていた”にも拘らず、そちらのほうはマジメというかオク手だったと、かつて羽田自身から聞いたことがある。信州育ちの羽田は大の蕎麦好き。安月給で旨い蕎麦屋巡りばかりしていたそうだ」(羽田と親しかった元政治部記者)
文学ゆかりの地を巡る観光バスによる「文学散歩ツアー」なる企画は、羽田社員コンシンの“ヒット作”だったそうだ。
一方の妻・綏子は、“コンドーム”でおなじみのオカモト(旧・日本理研ゴム)の副社長の長女で、マガジンハウス(旧・平凡出版)でのアルバイトを経て花嫁修業中に、羽田と出会うことになる。“見合い”であった。
「その席で羽田はノーネクタイ、カーキ色のジャンパーにグレーのズボン姿で飾り気なし。綏子夫人はのちに『なんとなく親戚の人に会ったような親しみを感じた』と言ったそうです。羽田は2回目のデートで、こう言った。『まあ小田急バスにいれば、最後は重役にはなれると思う』と。生マジメな羽田の精一杯のプロポーズだったようだ。綏子夫人は聞いたそうです。『それでお父さまの跡をお継ぎになることは?』と。綏子夫人は東京生まれ。万が一、羽田が選挙に出、長野県住まいをよぎなくされるのはまっぴらということだった。羽田はキッパリと言ったそうです。『僕は親父の跡は継ぎません』と」(同)
羽田30歳、綏子25歳の結婚だったが、事態は急変した。昭和43年(1968年)7月、羽田の父親が病に倒れたのをキッカケで引退を決意した。羽田は「親父の跡は継がない」としていたが、長く世話になっていた後援会が収まらなかった。結果、羽田家の家族会議は「長男が継ぐしかない」との結論を出した。父親が長く世話になった後援会の強い意向で、羽田は小田急バスの企画調査室課長を最後に退社、言うならば避け難い運命を背負った形で翌44年12月の総選挙に出馬することになったのだった。よもやの選挙戦に巻き込まれた綏子の心境が、次のようなインタビュー記事で明らになっている。
「すべてが、“怖いもの知らず”でした。しかし、『電柱にも頭を下げるつもりでやりなさい』と義父(羽田武嗣郎代議士)に教えられるまま、右向け右、左向け左の選挙。個人講演会などでは人前に立つだけで足はガクガク、涙までこぼれてくる始末でした」(『代議士の妻たち』文藝春秋・家田荘子=要約)
結果、羽田は旧〈長野2区〉でトップ当選を飾った。このときの選挙で自民党の指揮をとったのが田中角栄幹事長で、森喜朗(のちに首相)、小沢一郎(のちに自民党幹事長。現・自由党代表)、梶山静六(のちに自民党幹事長)、渡部恒三(のちに衆院副議長)などその後の政界の第一線で活躍した者が多々当選、彼らを称して「花の44年組」との声もあったのだった。
一方、綏子はその初当選の感想を求められ、「サラリーマンだったら、こんな感激は味わえなかったと思います」と嬉しさを率直に述べたが、たちまち地元から「エラソーなことを言うなッ」の苦情が殺到、改めて“代議士の妻”のムズカシサを思い知ったのだった。
その後、羽田は順調に政治キャリアを積んでいった。農政には熱心で「総合農政の羽田」の名前をほしいままにし、農水大臣、大蔵大臣、副総理兼外相と重要ポストを歴任していく。派閥は田中派、竹下派と歩み、竹下派では幹部として「七奉行」の一人に位置づけられたものだった。
その頃は、綏子も“代議士の妻”に成り切り、「選挙はスポーツ。そういう感覚でやるとストレスもないから」と口にするようになっていた。しかし、その綏子は「ストレスもないから」から打って変わり、とんでもないストレスを取り込むことになる。羽田に、突如、総理のイスが舞い込んできたからであった。
=敬称略=
(この項つづく)
小林吉弥(こばやしきちや)
早大卒。永田町取材48年余のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『決定版 田中角栄名語録』(セブン&アイ出版)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。