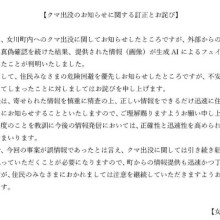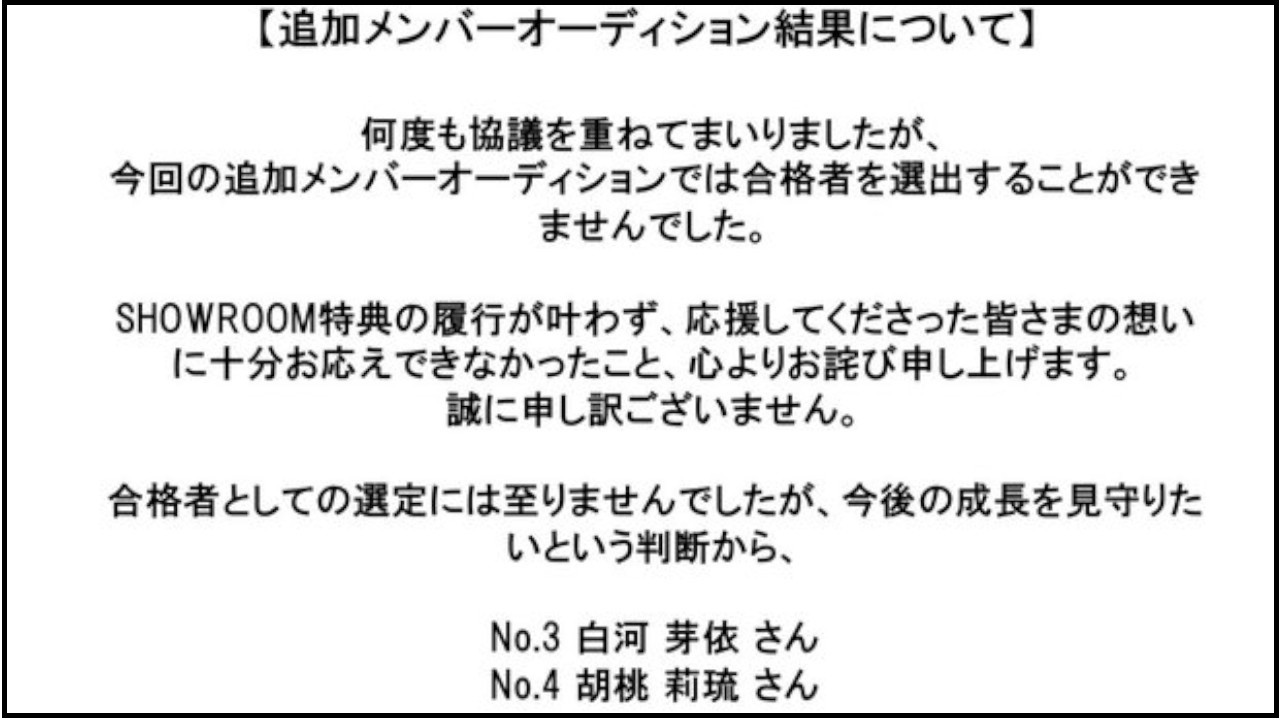「昭和56(1981)年の東京都議会選挙で、自民党はかろうじて勝利した。時に、田中は首相を退陣、ロッキード事件を引きずっていた。結果を見て、後藤田が田中に言った。『こんな結果じゃ、とても自民党が勝ったとは言えませんな。大体、田中さん、あんたがあちこち遊説に動いたのがよくなかった』と。田中はさすがに渋い顔をしていたが、何も言葉を返さなかったそうだ。後藤田が言うんじゃしょうがないということのようだった」
いずれも元田中派担当記者の証言だが、元警察庁長官の後藤田正晴という人物は、田中角栄の長い政治生活の中でも特別な存在のようであった。政界の実力者への階段を駆け上がり、やがて首相の座に就いて圧倒的権力を手にした田中だったが、言うなら後藤田の話はことごとく“正論”で、言葉を返せぬ相手ということであった。
田中は自分の政治的能力には絶対の自信を持っていたが、自分の欠点もよく知り抜いていた男でもあった。短気、自信過剰、攻めには強いが守りには弱い、時に「情」に左右され、物事の判断を狂わされることもある等々であった。後藤田はそうした田中の隙間に、正鵠を得た直言で迫ってきた。そこには、お互いに全幅の信頼感があったことは言うまでもなかった。
2人の出会いは、昭和27年の暮れにさかのぼる。東大を出て、内政の中枢官庁だった旧内務省入りした後藤田は、時に38歳の国警本部(警察庁の前身)警備部警ら交通課長であった。一方、後藤田より4歳年下の田中は当選3回、陣笠ながら衆院予算委員会のメンバーであり、すでにバリバリの若手として与野党に知られていた。
その当時は池田勇人通産大臣が、「中小企業の倒産、自殺者が出ることもやむを得ぬ」などと放言、終戦から7年目の政界は大揺れが続いていた時期である。
このとき、後藤田は「第二機動隊構想」の腹案を持っていた。当然、人件費の増大などが必至のことから、翌年度の予算では警察予算の増額をあえて田中に陳情したのだった。
後藤田は内務省の先輩にして代議士でもあった町村金五(のちに北海道知事。故・町村信孝元外相の父)から、「戦後タイプのメリハリのきいた代議士で、将来性がある」との田中評を耳にしており、それではということで予算陳情に田中を頼ってみたのである。結果的に、警察予算の増額は果たされた。
★100%実現した予算陳情
その後、二人はこれを機に陳情なども含めて親交を重ねた。後藤田は筆者のインタビューで、この頃の田中について、こんな話をしてくれたことがあった。
「田中さんは当時、自民党内での序列はまだ低かったが、先輩の政治家、官僚には気に入られていた。気さく、明るい、物事ののみ込みは早い。一を言えば、すぐ十をのみ込んでくれた。陳情も、それで『わかった、わかった』と言う。他の代議士なども同じことを言うが、田中さんがこうした人たちと違うのは、『わかった』と言ったことは、100%実行してくれたことだった。
加えて、陳情を受けたあと『あの件は君の言う通りになったよ』と、必ず電話をくれた。こうしたことも極めて事務的に処理し、押しつけがましいことが微塵もなかった。ために官僚は、そんな田中さんを信用していたということだ。それから歳月が流れても、こうした“田中評”は一貫して変わるところがなかった。実行力、決断力において、以後、田中さんを超える人は、少なくとも私は一人も見てこなかった」
二人の間に、さらに“あうんの呼吸”が成立したのは、田中が43歳で自民党政調会長になった頃であった。その当時、後藤田は警察庁から自治省に出向し、税務局長のポストにあった。後藤田は「3割自治」と言われた地方自治体の実態を憂い、地方税だけでは財源が苦しいため、大蔵省の徴収した国税から、できるだけ財源を回してほしいと田中に陳情したのだった。
ここでも田中は「わかった」と言い、自民党の予算要求の中に自治省の要求項目をもぐり込ませ、後藤田の要求をのんだのであった。
こうした関係から、それから約10年後に田中が天下を取り、田中首相・後藤田官房副長官という強固な関係ができ上がっていった。後藤田は自他ともに、田中の「懐刀」を任じることになっていくのである。
人間は“怖いもの”があったほうが、人生で失敗が少なくて済みそうである。親、先輩、友人、向こうに怖い目が光っているとなると、悪いことはなかなかできなくなる。ブレーキを踏む術を知るのである。田中もこの強力な「懐刀」を傍らに、政権運営などで度々ブレーキを踏まされるのだった。
(本文中敬称略/この項つづく)
***********************************************
【著者】=早大卒。永田町取材49年のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『愛蔵版 角栄一代』(セブン&アイ出版)、『高度経済成長に挑んだ男たち』(ビジネス社)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。