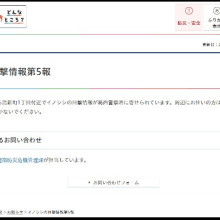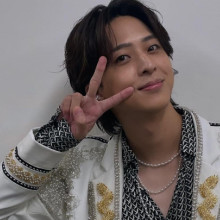それをよそに、日本列島には“いつ起きてもおかしくない”とされる南海トラフ巨大地震、関東直下型地震の前兆現象とも取れる揺れが起き続けている。3月1日午後10時24分頃、沖縄県の竹富町西表島付近を震源としたマグニチュード(M)5.6の強い地震が発生し、同町では震度5弱を観測。その後も余震が相次いだ。
「沖縄県内で震度5以上が観測されたのは、'10年2月27日に糸満市で震度5弱を記録して以来、8年ぶり。不気味なのは、西表島付近から九州の南にかけては琉球海溝があり、その北端が、南海トラフにつながっていることです。この海溝は、近年の研究において数千年に一度の確率でM9クラスの巨大地震が発生する可能性が指摘されている。また、それが南海トラフ巨大地震と連動するとも言われているのです」(地震担当記者)
西表島からわずか約280㎞の台湾では、2月4日に東部の花蓮市付近でM6.5の地震が発生したばかりだ。
これまで数多くの地震と噴火を予測、的中させてきた、琉球大学名誉教授の木村政昭氏はこう話す。
「沖縄には私が名付けた海嶺、日本列島構造線が走り、プレートの境界になっていると考えています。日本列島構造線は、大西洋を引き裂く大西洋中央海嶺から始まり、北極、シベリアを経て、樺太の西側を通り、日本海にまで続いている。さらに新潟県沖を経て富山湾に入り、琵琶湖、瀬戸内海を通って沖縄、台湾にまで至っているのです。ここでは地殻が激しく引き裂かれる状態にあり、近辺で地震が発生しても何ら不思議はないのです」
木村氏の言う構造線とは別に、日本列島には九州から関東までを中央構造線という大断層が貫いており、付近で起きた地震が別の構造線付近で起きる地震を誘発させることも指摘されている。
1596年9月4日、その中央構造線付近の大分県別府湾口で、推定M7.0規模の地震(慶長豊後地震)が起きた。その規模は、別府湾にあった瓜生島と久光島と呼ばれる2つの島が沈んだとも言われるほどだ。同月は1日にも、同じく構造線付近の現在の愛媛県を震源とした慶長伊代地震(M7.0程度)が発生しており、9月5日、今度は京都府を震源とした推定M7.2が発生して伏見城や東寺などが倒壊。1000人以上の死者が出たとの記録もあり、これらもまた、構造線を介した連動性が指摘されているのだ。
「最近では、熊本地震から1年余りが経過した昨年6月20日、大分県南部で震度5強、その5日後には長野県南部でも震度5強の地震が起きている。距離は離れているが、これらも中央構造線近くで発生しており、関連性が指摘されている。周辺の地震によって構造線が刺激され、構造線を伝って離れた場所の活断層まで反応してしまうことを考えれば、今回の沖縄の地震もあらゆる地震の引き金になりうるということ。それが、南海トラフ巨大地震、さらには関東直下型地震の場合もあるのです」(サイエンスライター)