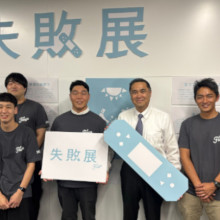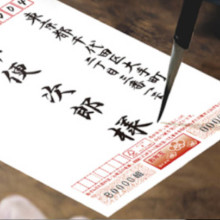女性に優しかった田中は、遊び上手、気っぷもよかったうえ、自民党幹事長など権力の階段をのぼり始めた頃は、芸者をはじめモテにモテた。
その中で、とくに真紀子の胸を痛めさせたのが、花柳界・神楽坂の売れっ子芸者だった辻和子と、田中が陣笠代議士時代から秘書として仕え、のちに「越山会の女王」として田中事務所の金庫番を担い、田中と二人三脚で政治活動を共にした佐藤昭子の2人である。ともに、「愛人」として位置付けられていた。真紀子はこの2人とどう向き合い、そのはざまで父親としての田中はどう真紀子と向き合ったのか。
辻和子と田中は、辻が「円弥」という源氏名で座敷に出ていた19歳、田中が28歳で田中土建工業が戦後の土建ブームでウナギのぼりに業績を上げていた昭和22年(1947年)に出会い、恋に落ちた。神楽坂で戦後真っ先に復活、有数の待合だった『松ヶ枝』で会うことが多かった。
その後、田中は「円弥」を身請けし、神楽坂に一戸を構え、長女は乳児で死亡したが、その後、2男をもうけたのだった。
辻は田中を「おとうさん」と呼び、秘書だった早坂茂三(のちに政治評論家)が明かしたところでは、「正月元日は目白で年始客と会っていたが、2日は神楽坂に行っていた」そうだから、いかに“別宅”のほうも大事にしていたことが窺われる。
しかし、こうした父親の行状に不信感を持っていた真紀子ではあったが、決定的な不信感のピークに達したのは、もう1人の愛人、佐藤昭子の存在だった。昭和49年(1974年)、月刊『文藝春秋』に“田中角栄研究”が掲載され、金脈問題と同時に“淋しき越山会の女王”として田中と佐藤の愛人関係が暴露されたことがキッカケだった。それまで、単なる秘書と認識していたのが、真紀子にとっては屋上屋を重ねる愛人の存在は、とんでもない“ニュース”だったのだ。例えば、佐藤との間にもうけた娘・あつ子は、のちにこう語っている。
「私が4歳か5歳の頃、母と一緒に目白に伺ったら、真紀子さんがメロンを出してくれたり、その後もお花の入った香水を頂いたこともありました。その後も、真紀子さんからの母親の手紙はじつは別れた夫の苗字になっていたから、真紀子さん、家庭を持ちながら父親の仕事を非常によくやってくれている秘書と思っていらしたんでしょうね。だから、本当のことを知ったとき、さすがに、ああ裏切られたんだ、と思われたんだと思います」(『週刊文春』平成24年3月29日号=要約)
しかし、佐藤とのこうした愛人関係の新たな露見は、ついに真紀子を爆発させた。時に、真紀子は結婚した田中直紀との間に、2人の幼児がいた。一方の田中は、金脈、女性問題の追及で、進退極まっていた。その田中の首相辞任の決断は、結局、愛娘の一言だったというのがもっぱらである。
★真紀子の一言が決めた首相退陣
「田中は、真紀子の意見を求めたそうです。真紀子とすれば、子供たちが恥ずかしくて学校にも行けない。『どうするの。何とかしてよ。私も外を歩けやしない』と迫ったとされる。孫かわいさが人一倍の田中は、この一言で辞任を決断したと言われている。田中は、のちに言っていた。『金脈問題も、ちゃんと説明すれば切り抜けられた。しかし、娘の一言には勝てなかった』と」(元田中派担当記者)
真紀子にとっては、政治家として尊敬してやまなかった父親ではあったが、最後まで女の生理として愛人問題は許せなかったようだ。それは、田中が入院中に辻和子との間にもうけた2人の息子の面会を拒否、通夜でも会わせることをしなかったことにも表われている。長兄の京は、通夜の翌日の密葬で、かろうじて一般弔問客に混じっての焼香を許されただけだったのだ。
その後の真紀子は、田中の地盤を引き継ぐ形で政界入りし、父親譲りの頭の回転のよさと弁舌の巧みさで外務大臣に就任した。田中は常に、のちに3人の子持ちとなった真紀子にこう言っていた。
「子供を作るなら3人がいい。1人でも2人でも、親の膝を独占できる。しかし、3人になれば競争が始まる。人間社会が、競争社会であることを教えることが、子供のためになる」
真紀子は、父親のこんな“言いつけ”を守った形になっている。
言葉を失った闘病生活で、車椅子の父親を最後まで“自分のもの”として守り続けたのも、また真紀子であった。長い父娘の愛憎劇に終止符が打たれて、早25年の歳月が流れようとしている。亡き父親の年齢を大きく越えた真紀子に去来するものは何か。_=敬称略=
_(次回は福田赳夫元首相)
***********************************************
小林吉弥(こばやしきちや)
早大卒。永田町取材49年のベテラン政治評論家。抜群の政局・選挙分析で定評がある。著書に『愛蔵版 角栄一代』(セブン&アイ出版)、『高度経済成長に挑んだ男たち』(ビジネス社)、『21世紀リーダー候補の真贋』(読売新聞社)など多数。