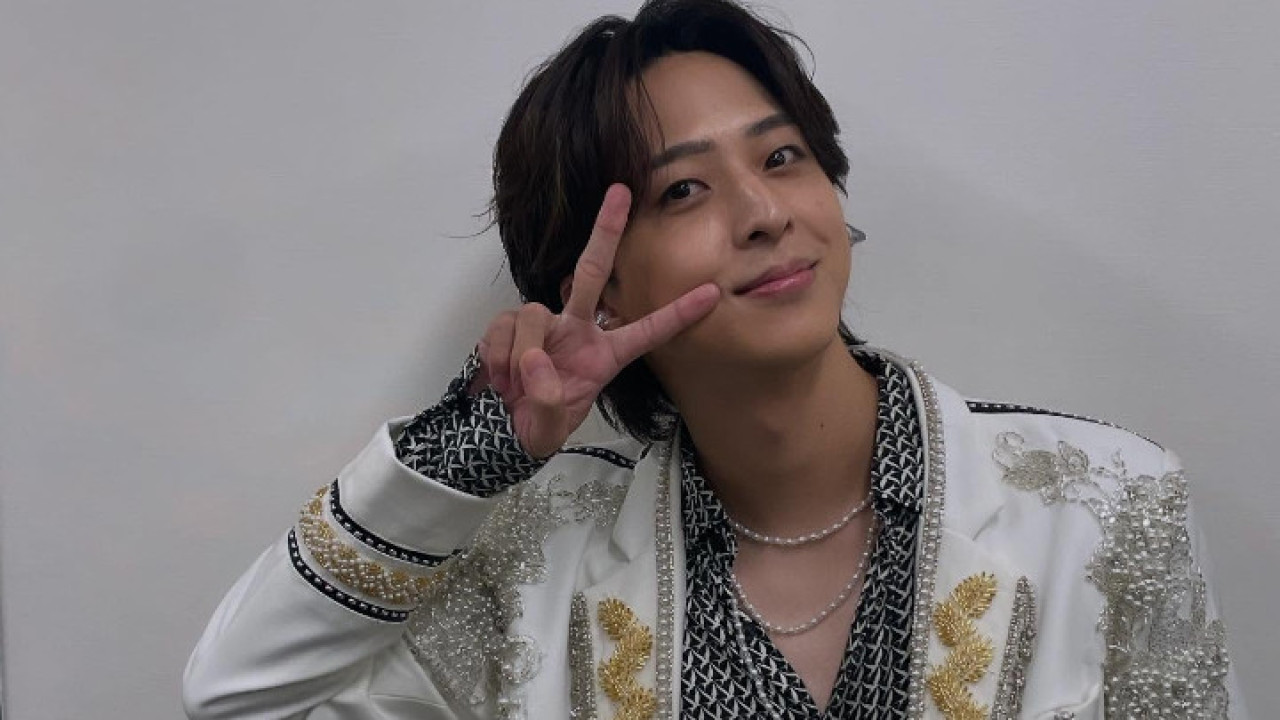「キャバクラ嬢になる前は、けっこうお堅い企業で働いていました。でもある日、このまま女性として見られることなく、ずっと地味な生活を送ってていいのかなって。一度、女としての武器をウリにして働いてみたかったんです」
麻美は女子高から短大に入り、卒業後は有名企業に就職。それからは事務員として働いていた。今まで恋人も出来たことがなかった彼女は、ただ年齢を重ねるだけの毎日に恐怖を憶えたという。そんな思いから会社を退職し、都内のキャバクラで働き始めた麻美だったが、両親には会社を辞めたことを言えないでいた。
「うちの親はかなり真面目というか厳しい人なんです。だから絶対に水商売をしているなんて言えなかったですね」
しかしある日、麻美のことを知る人物が来店する。
「席に着いた身に覚えのないお客さんから『あれ、君、○○中学の子だよな?』っていきなり聞かれたんです。私はうかつにも『そうですよ』と答えてしまったんですよね」
その男は麻美の同級生の父親だった。過去、彼女が自宅に何度か遊びに来ていた時に顔を覚えていたのだという。しかし麻美にはその父親の記憶がまったくなかった。
「それからしばらくして親から電話がかかってきました。『おまえ夜の店で働いているのか』って」
来店した同級生の父親によって麻美がキャバクラで働いていることは瞬く間に広まり、両親の耳にも入ったという。
「さすがに怒ってましたね。キャバは辞めざるを得ませんでした。でもまた地味な毎日に戻るつもりはありません」
麻美はアイドルになりたいという夢が幼い頃からあるのだという。今後は両親を説得し、アルバイトをしながらオーディションを受けたいと目を輝かせながら語った。
(文・佐々木栄蔵)





























 社会
社会