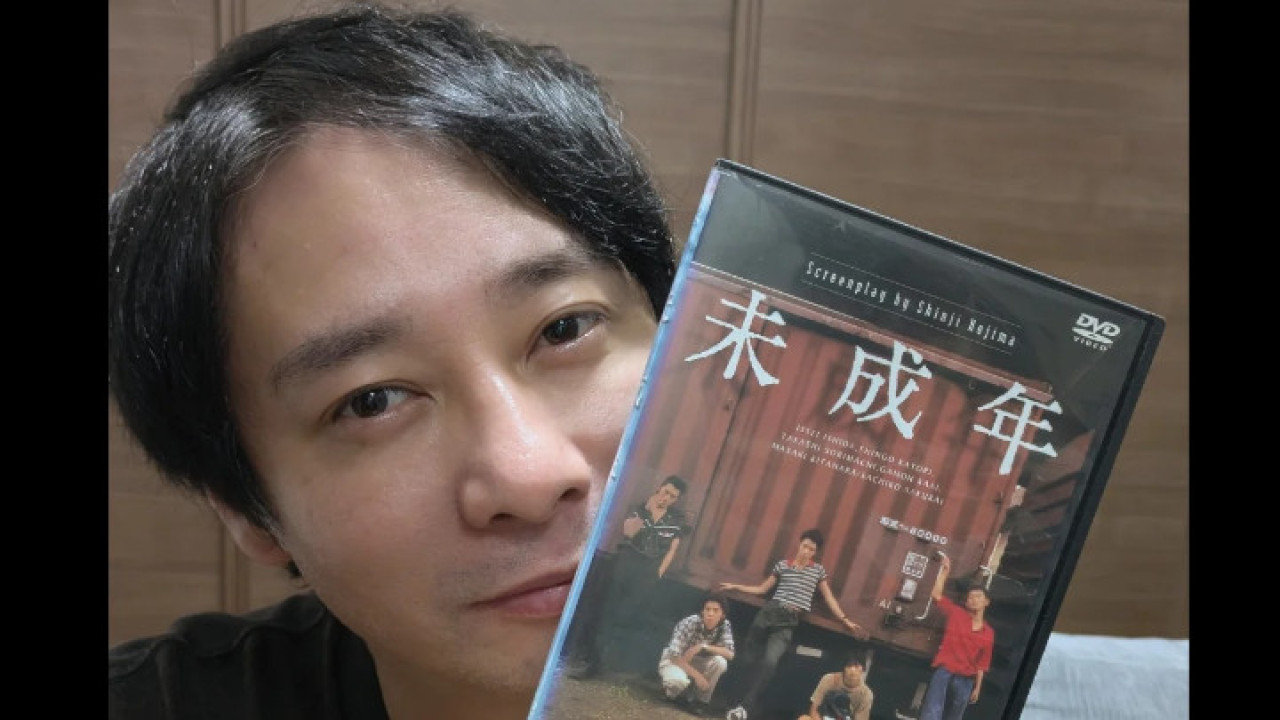患者の多くは、その痛みで「腕が上がらない」「目が覚め眠れない」などと訴える。「放っておいても自然に治る」という“俗説”もあるが、放置は禁物。肩関節が“拘縮肩(肩関節が硬くなる)”にまで進行すると、一生、腕が肩から上にあがらなくなる危険性がある。また、糖尿病罹患者や肝臓、肺に異常がある人は重症化しやすく、甘くみていると取り返しがつかなくなるのだ。
都内の会社員Mさん(47)が右肩に異常を感じたのは、5年ほど前。高い所から物を取ろうとすると、わずかだが痛みが走る。当初は痛みが出る動作を避けて我慢していたが、1年後には歯磨きや洋服の袖に右腕を通すこともできなくなった。激痛で夜中に目を覚ますし、睡眠もままならず、東京・世田谷の東京医療センター整形外科を受診した。
診断は、予想通り肩関節周囲炎で、痛みに加え肩関節の内部が部分的に癒着し、動きが制限される「拘縮」または「凍結肩」と呼ばれる状態まで悪化していると診断された。
「Mさんの肩は、すでに肩関節の稼働域がほとんどない状態でした。1年以上も放置していたことが重症化した一つの要因です」(同センター整形外科主治医)
Mさんを診断する際、主治医は超音波で肩関節を詳しく調べた。肩には四つの筋肉を骨とつなぐ腱の集合体「腱板」がある。これが切れてしまう腱板断裂など、肩痛を引き起こす別の病気が潜んでいないかを見極めるためだ。
「整形外科の現場で超音波が活用され始めたのは、それほど昔ではありません。以前は非常に画質が悪かったのですが、'05年ごろから急速に進歩して診断しやすくなったのです。この装置は元来、腹部の臓器など体の深部を探るのが得意分野で、体表近くを見たい整形外科には不向きな装置だったのです」(同)
従来の手法は、まずレントゲン写真、詳細な診断にはコンピューター断層撮影(CT)や磁気共鳴画像装置(MRI)検査が用いられたが、放射線被ばくや簡便性の問題など、一長一短があった。それが進歩した超音波技術によって、浅い領域でも鮮明な画像を得られるようになった。
Mさんは初診の翌月、肩内部の癒着を取り除く内視鏡手術を受けた。リハビリにも取り組み、今では肩の動きは数カ月で元に戻ったという。Mさんは「もっと早く受診していればよかった」と、痛みに耐えた日々を振り返っていた。
肩に触ると突起があるのがわかる。この箇所を「肩峰(けんぽう)」と呼び、50歳以上になると、殆どの人の肩峰の裏側に“骨のトゲ”ができ、肩の筋肉と骨を繋ぐ「腱板」に傷がつく。それでも、肩の動きを滑らかにする油のようなもの(ヒアルロン酸)が十分あれば傷は治るが、加齢や体質、持病などで油が少ないと治らない。傷が大きくなり炎症が肩に広がると、肩関節周囲炎を起こしてしまうのだ。
整形外科を営む加藤クリニックの加藤達弥院長は、こう説明する。
「肩痛の炎症を放置すると、肩の関節が癒着し、拘縮肩と呼ばれる病型になり痛みが増します。この症状は全身麻酔を施し完全に痛みを取っても、腕が肩の高さまで戻りません。痛くて動かせないのではなく、構造的に動かせなくなってしまうのです」
つまり、拘縮肩まで進行すると自然には治らず、痛みが消えても、治療を受けない限り、固まってしまい腕を肩以上の高さまで一生上げられない。生活の質の著しい低下は、想像に難くないだろう。
五十肩の段階なら、ヒアルロン酸の注射とリハビリ、あるいは注射だけで改善する。しかし痛みは、片方の肩だけの場合と、一方の肩が発症してしばらく経つと、もう片方の肩にも痛みが出る場合がある。この現象はかなり確率が高く、防止するのは難しい。























 社会
社会