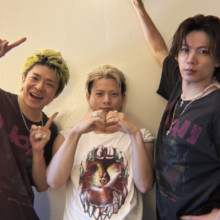四国周辺でも活断層とは別に南海トラフ地震が70%程度の確率で起こるとされている。12月13日、広島高裁は「阿蘇の過去の噴火で火砕流が到達した可能性は十分小さいと評価できず、原発の立地は認められない」として、来年1月に再稼動を予定していた四国電力伊方原発3号機(愛媛県伊方町)の運転差し止めの仮処分を決定した。
高裁では、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇カルデラで約9万年前に起きた破局噴火が発生した場合を検討したという。ちなみに、原子力規制委員会が調査を求めているのは、火山が160キロ内にある原発。海を越えることはないと考えがちだが、火砕流の密度は海水よりも低いために海上を渡る可能性が高いのだ。
地震学の権威で武蔵野学院大特任教授の島村英紀氏はこう言う。
「今回の判決は画期的です。約9万年前に起きた『阿蘇4』(30万年前から4度目の噴火)と呼ばれる噴火は日本最大級のものでした。これで火砕流が九州全域に達したが、同レベルの破局噴火が起きれば、九州にある玄海原発(佐賀県)と川内原発(鹿児島県)も当然、壊滅する恐れがある。それを認めた判決なのです」
伊方原発といえば、すぐそばに日本列島を東西に貫く中央構造線と呼ばれる大断層が走り、阿蘇山も横切っている。しかも、断層付近では巨大地震が連鎖して起きることも指摘されているのだ。
「東日本大震災以降、周辺の火山が誘発されて噴火が相次いでいますが、海外に目を向けても、カムチャツカ地震(1952年=M9)、チリ地震('60年=M9.5)、アラスカ地震('64年=M9.2)、スマトラ島沖地震(2004年=M9.1)では、近隣の火山が例外なく噴火している。M6クラスなら大丈夫でしょうが、M7がぎりぎりで、M8の巨大地震が発生すれば、阿蘇の噴火が誘発されるかもしれないのです」(同)
北海道、九州、四国“同時活動”の恐れと言われているが、マグニチュード(M)9級クラストと言えば原発の危険どころではない。