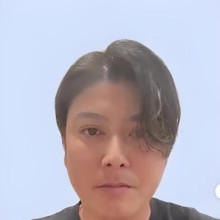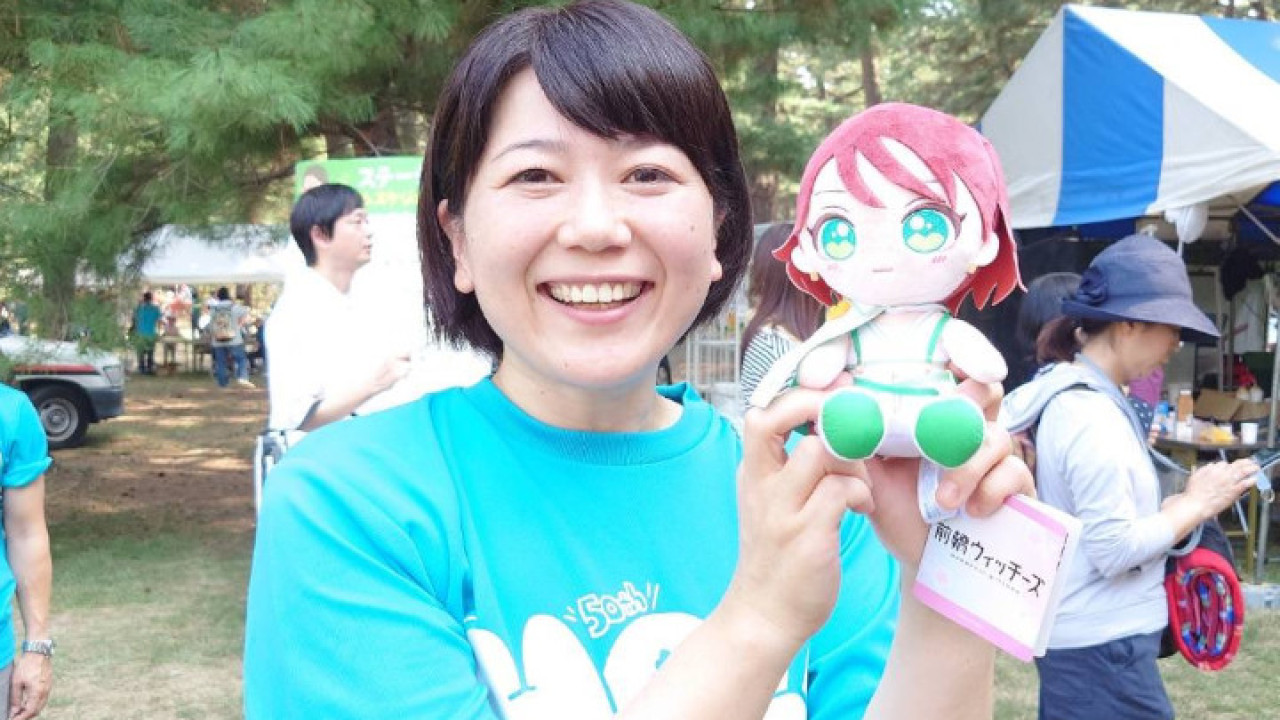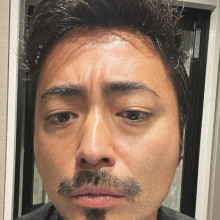さらに日本マットでも、長州力率いる維新軍の参謀役やアントニオ猪木との巌流島決戦で強烈なインパクトを残すなど、まさしく国際派レスラーの先駆けであった。
1999年に現役引退となったその前後からパーキンソン病を発症し、以後は闘病生活を続けてきた斎藤。長らくリングを離れていたが、'16年12月に大阪・城東区で開かれた“斎藤激励”の大会ではメインイベントに出場した。
ただし、メインといっても試合ではなく、斎藤が観客にあいさつするという段取りであったが、そこはプロレスのお約束。アイスホッケーのマスクをかぶった海賊男風のレスラー(中身は武藤敬司)が乱入してきた。
「攻撃を受けたマサさんが立ち上がって反撃しようとするのですが、そのときにプルプル震えていた。それが現役時代の動きを再現したものなのか、病気の影響なのかよく分からない。全盛期には盛り上がりすぎて首が見えないほどだった筋肉も、すっかり落ちてしまっていて…」(当日に会場を訪れたファン)
斎藤の支援をうたうならば、なぜ住まいのある首都圏ではなく移動をともなう大阪だったのかという疑問はある。また、同大会の主催者が“新日本プロレス土下座外交時代”のブッカーで、退社後には前田日明らともめ事を起こしている上井文彦氏と聞くと、どこかいぶかしく感じるファンもいるだろう。
しかし、どんな形であれリングに上がることが闘病に向けての活力になるなら、かつてプロレスに熱狂したファンとしては応援する以外の選択肢はないだろう。
'64年の東京五輪に、明治大学在学中の斎藤はレスリング重量級フリースタイル日本代表として出場し、3回戦まで進出。翌年に大学を卒業すると日本プロレスに入団し、日本人オリンピアンとしては初のプロレスデビューを果たした。
'66年には猪木が旗揚げした東京プロレスに移籍。斎藤はデビューからわずか2年にもかかわらず猪木、豊登に次ぐナンバー3に格付けされ、このことからも期待のほどがうかがえる。
その東プロが崩壊すると、斎藤はフリーランスとして単身渡米する。
「人間関係のもつれに嫌気が差したというのもありますが、加えて東プロ時代、武者修行帰りの猪木から聞いたアメリカマット事情に、興味を持ったというのも大きかったようです」(プロレスライター)
太平洋戦争の記憶がまだ色濃く残っていた当時のアメリカにおいては、日系人でない純日本人ヒールの需要が高かった。また、この頃はプロモーター側がレスリング技術を重視したこともあって、斎藤は長年にわたり全米の主要テリトリーでトップヒールに君臨することとなる。
同時に日本でも、上田馬之助やヒロ・マツダらとともに、フリーランスによる『狼軍団』を結成し、新日本や国際プロレスに日本人ヒールとして参戦するようになった。
「その後、維新軍において参謀格になったことで日本での試合が増えましたが、これは新日側の仕組んだアングルではなく、長州が同じレスリング出身の斎藤に相談を持ち掛けたことがきっかけでした。頼られると断れない人のよさが出たわけです」(同)
長州らとともに全日本プロレスに移籍していれば、ジャンボ鶴田との五輪代表対決なども実現しただろうが、そうならなかったのには理由がある。直前にアメリカで、警官に暴行を働いたとして国外への移動が制限されていたのだ。
「長州ら維新軍の移籍については『好きなようにやればいい』と背中を押したマサですが、しかし、仮に暴行事件がなかったとしても果たしてこれに同調していたか。義理堅い人だけに、猪木の新日をそうそう裏切るとも考えづらい」(同)
真相はどうあれ、結果的に斎藤は1年6カ月の刑期を終えると、アメリカマット界がWWFの一人勝ち状態になっていたこともあり、新日本に本格参戦。伝説の巌流島決戦をはじめ猪木と死闘の数々を繰り広げることになる。
さらに斎藤は、長州復帰の際の橋渡し役となり、ビッグバン・ベイダーやスコット・ノートンら、のちにエース外国人となるレスラーたちをブッキング。自身が第一線から退いてからもテレビ解説を務め、この時期の新日本を陰に日向にと支えたのであった。
「まだキャリアの浅い時期に、アメリカでの試合中に眼球を負傷し、それ以来、片目が見えない状態だったそうですが、現役時代はそんな様子を少しも見せることはなかった。そんなマサさんであれば根治法が確立されていないパーキンソン病にも、決して屈することはないはずです」(同)
自身の出場した東京五輪から半世紀以上がすぎ、再びの東京五輪が2年後に迫った今、斎藤は「聖火ランナーとして参加する」ことを目標に掲げているという。
マサ斎藤(本名:斎藤昌典)1942年8月7日、東京都出身。身長180㎝、体重120㎏。得意技/ひねり式バックドロップ、監獄固め。
文・脇本深八(元スポーツ紙記者)