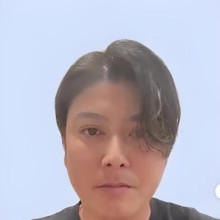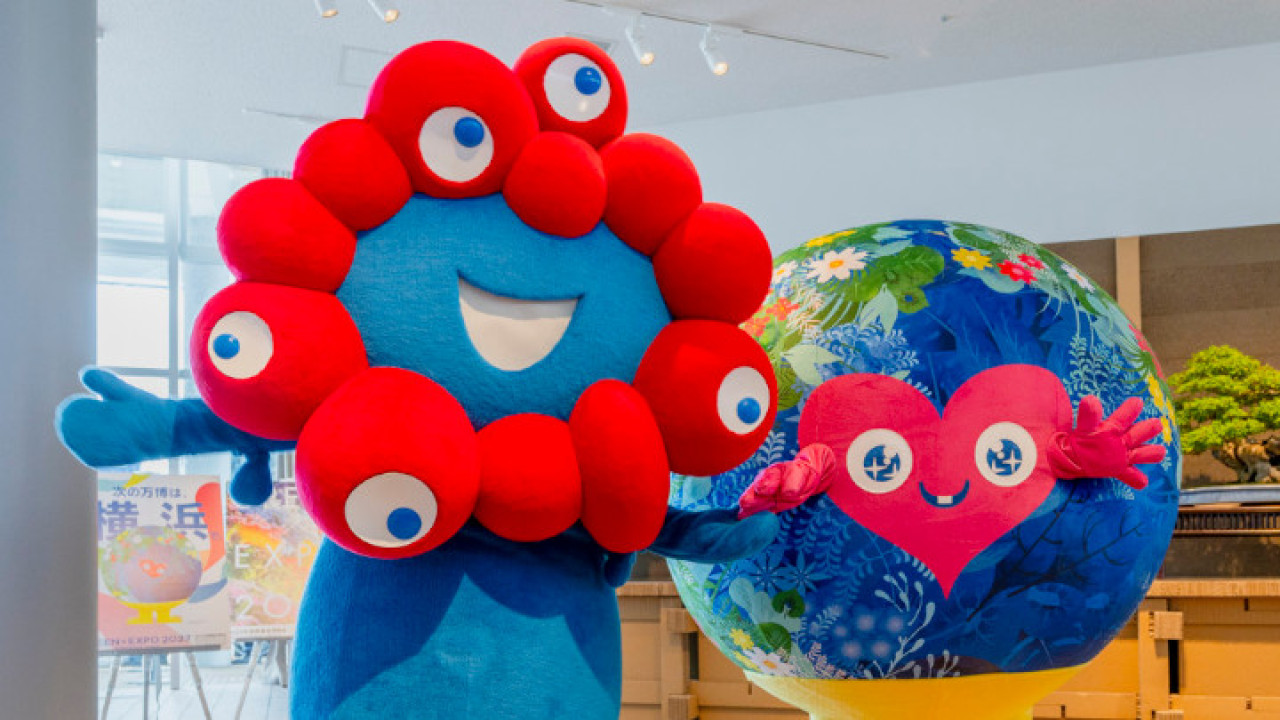特に被害が大きかった広島市の安佐南、安佐北両区に流れ込んだ土砂は、市の推定で50万立方メートルに達している。
昨年10月の伊豆大島の土砂災害の際の土砂量は、約17万5000立方メートルであった。今回の広島市の土砂災害は、土砂量が伊豆大島の災害の3倍に達したことになる。
さらに、現地では救助活動中の消防隊員の方までもが犠牲になってしまった。二次災害の危険が高いため、救援活動は難航した。
広島市では、1999年6月にも崖崩れや土砂災害により20人が亡くなり、結果的に2001年に土砂災害防止法が施行された。
土砂災害防止法は、国民の生命を守るため、土砂災害の可能性がある区域について、
「危険の周知」
「警戒避難体制の整備」
「住宅等の新規立地の抑制」
「既存住宅の移転促進」
など、主にソフト的な対策を推進することを目的としている。
土砂災害防止法は各都道府県に対し、危険個所を事前に調査し、警戒区域や特別警戒区域に指定した上で、市区町村がハザードマップを作成し、配布することを義務付けているのだ。
特別警戒区域に指定された地域では、宅地開発が規制されることになる。
今回、被害にあった地域の多くは、警戒区域に指定されていなかった。一部の報道によると、市役所の人員不足により、警戒区域、特別警戒区域の指定作業が遅れていたとのことである。
'90年代以降、日本政府及び日本国民は、ひたすら「効率化」を追い求め、例えば「防災」という安全保障のために必要なリソース(予算、人材、企業等)までを切り詰めてきた。
広島市の市役所の人員不足により、今回の被災地域の警戒区域・特別警戒区域の指定作業に遅延が生じていたとすると、まさに上記「効率化追求」の結果として被害が拡大したとしか言いようがない。
そして、地方自治体の人員不足が理由で、十分な「防災という安全保障」が確立していない地域は、別に今回の被災地に限った話ではないだろう。
大変残念なことに、安全保障の強化と効率性の追求は、少なくとも短期的にはトレードオフ(一方を追求すれば他方を犠牲にせざるを得ない状態のこと)の関係にある。
安全保障を強化すればするほど、システムは次第に効率的ではなくなり、余計なコストがかかる。理由は、安全保障が、
「いつ、起きるかわからない、あるいは、起きるかわからない非常事態」
に備えるという性質を持つためだ。
起きるかどうか、未確定の非常事態に備える以上、ある程度の「無駄」が生じるのは、これはもう仕方がない話だ。
逆に、無駄を削り取り、最小のリソースで非常事態に備えようとすると、当たり前の話として安全保障は弱体化する。
この世に「最低のコストで、最高の安全保障を実現する」などという、魔法は存在しないのだ。
また、今回の土砂災害では、広島市の避難勧告の発令が遅れたのではないか、との指摘が出ている。
避難勧告が出たのは、土砂崩れが相次いだ「後」のことだった。広島市の松井一実市長は、8月26日に、夜間に対応する避難勧告のマニュアルがなかったことを明らかにし、勧告の遅れについても認めた。
もっとも、筆者は現時点で広島市の避難勧告の件や被害想定の件を批判したいわけではない。広島市の避難勧告の遅れについて取り上げたいのは、例えば、
「被害想定範囲を極めて広くとっていたため、必要のない住民までもが避難させられた」
「避難勧告が早すぎ、結局、土砂災害は発生しなかった」
といったケースを、住民(国民)側がいつの間にか「無駄なことを!」と非難するようになってしまい、自治体側が、
「避難想定範囲の設定や、避難勧告は、できるだけ、効率よく、できるだけ住民から苦情が来ないように」
という空気になってはいないか、という問題を提起したいためである。
バブル崩壊とデフレ化により、日本国民は貧困化し、無駄を許容する「余裕」を失っていった。結果的に、我々日本国民は効率化のみを「善」とし、安全保障の強化という「非効率」な行為を「悪」と認識してはこなかっただろうか?
答えがYESだったとすると、有権者(国民)から選ばれる政治家は、
「行政の無駄を削ります!」
「公務員の効率化(非正規雇用への切り替えなど)により、税金を効率的に使います」
などと叫ぶことで喝采を浴び、かえって票を獲得できるという話になってしまう。
「行政の無駄を削ります。抜本的に行政を改革します」
などと、中身のない綺麗事を主張して当選した政治家たちが、防災など安全保障の強化という「非効率」な政策を推進することができるだろうか。筆者は、不可能だと思う。
長期にわたりデフレが継続し、日本国民は「節約こそ善」「効率化こそ善」「切り詰めこそ善」、そして「無駄は悪」という、偏った価値観を持つに至った印象を受けるのだ。昔の諺にならえば、貧すれば鈍する、である。
現在、我が国の防衛、防災といった安全保障が危機に瀕している。日本国民を守る安全保障を強化するためには、まずは日本国民が、
「安全保障を強化し、自分たちを守るためには、ある程度の無駄が発生しても当たり前」
という、普通の認識、つまりは「常識」を取り戻す必要があると思うのだ。国民が無駄を許容する心を持ち得ない国で、安全保障を強化することなどできるはずがない。
もちろん、
「安全保障強化のためには、どれだけコストを費やしてもいい」
というわけではない。要は安全保障強化と、効率化の間のバランスを取らねばならず、現在の日本はバランスが「効率化」「コスト削減」「無駄の排除」に傾きすぎてはいまいか? という話なのである。
三橋貴明(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、わかりやすい経済評論が人気を集めている。