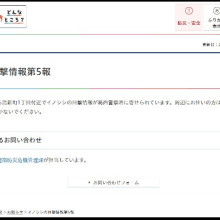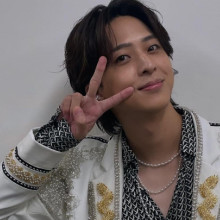気象庁が正式に命名した今回の「平成30年7月豪雨」は6月28日以降、西日本を中心に北海道、中部地方など広範囲にわたり被害をもたらした。
「まず太平洋高気圧の影響で北海道に停滞していた梅雨前線が大雨をもたらし、この梅雨前線が7月5日から南下。九州から中部地方に停滞したところに、東シナ海からの湿った南東風、太平洋高気圧回りの湿った南風が合流したことが、大雨をもたらしたのです」(気象庁関係者)
各自治体の集計によれば、住宅の全半壊などは16府県で776棟、床上・床下浸水は29道府県で2万3374棟。土砂崩れや橋が流されたことにより、鉄道や高速道路なども各地で寸断が続いている。豪雨時、愛媛県などの6府県のダムでは、水量が満杯に近づいたことから緊急的に放流する「異常洪水時防災操作」も行われていたことが分かっており、想定を越えた雨量だったことが窺える。
「これだけの広域被害が出たのは、東日本大震災以来のこと。降雨を原因としたものでは初めてのケースではないでしょうか」
とは、防災ジャーナリストの渡辺実氏。
死者100人超えは、平成での豪雨災害としては最悪。昭和まで遡っても、1982年の長崎大水害(死者・行方不明者299人)以来最悪となったが、気象状況の面では、昨年7月に起きた福岡県・大分県を中心に被害が出た九州北部豪雨とメカニズムは同じだという。
「湿った空気の通り道が今回の方が広かったことで、広域にわたり被害が出てしまったのです。はっきりしていることは、地球温暖化により、こうした大雨は確実に増え続けているということ。日本では過去に何度も水害が発生し、その度に治水対策を行ってきましたが、もはや追いつけない状況に来ているのが実態なのです」(前出・気象庁関係者)
'14年8月にも広域にわたって豪雨が襲い、広島市安佐北区では土砂崩れが多数発生、隣の安佐南区を含め77人の犠牲者が出た。しかし、今回もその経験は生かされず、被害者が続出した。
「4年前の被害を経験に、広島県では土砂災害の危険区域を特別警戒区域に指定することを決めていたが、公表に至ったのが今年5月。8月から地元説明会を開き、その後、指定する予定でした。今回、土砂災害が発生した場所は警戒区域内にも入っており、一歩遅かったわけです。調査や地元住民の説得も含め、時間はかかるものの各自治体のスピーディーさが求められている」(地元記者)
いずれにせよ、降雨量、その範囲ともに、気象庁が発表した「数十年に一度、これまでに経験したことのない」想定外の大雨は、今後も増え続けるだろう。
「できるなら、国民全体が生きていく心持ちとして、常に災害モードのスイッチをオンにしておくべきです。今回で言えば、例えば、岡山県倉敷市の真備町。ここは2本の川に挟まれ、背後に崖を背負っている非常に危険な地域です。避難準備情報で逃げている方は助かったが、“うちは大丈夫”と構えていた方が多く亡くなっているそうです。私は天地動乱の時代という言葉をよく使います。東日本大震災を例にとるまでもなく、いつこうした豪雨や地震、火山の噴火に見舞われても不思議ではない」(渡辺氏)
その地震でも、6月18日には大阪北部地震が発生し、7月に入ってからも7日に千葉県北東部で震度5弱が発生、いつ起きてもおかしくないとされる巨大地震に向け、予断を許さない状況が続いている。
「大阪北部地震、千葉北東部での地震の震源地は、ともに中央構造線付近で起きている。この流れは一昨年の熊本地震から続いており、今年は5月25日にも長野県北部で震度5強、6月17日にも群馬県南部で震度5弱が発生している。こうした地震が、やがて巨大地震につながる可能性が指摘されているのです」(サイエンスライター)
中央構造線は、九州から関東まで、日本列島を縦断する大断層だ。この付近のどこかで大きな地震が起きると、離れた別の場所でも大きな地震が起きるとも言われている。
例えば、1596年に京都府付近で起きた慶長伏見地震(M7)の前日に起きた大分県を震源とする慶長豊後地震(M7.0〜7.8)、その3日前に愛媛県を震源として発生した慶長伊代地震(M7.0)などで、これらはすべて中央構造線を介した連動型の地震の可能性が指摘されている。
「中央構造線は、関東地方では群馬県の下仁田から埼玉県中部の比企丘陵で地上に露出し、茨城県の鹿島灘まで抜けていると見られていますが、その間の関東平野では地中にあり、埼玉県岩槻の南を走っていること以外は詳細が分かっていない。そのため周囲の活断層との関係から、首都直下型の巨大地震を引き起こす可能性も指摘されています。さらに、中央構造線付近など、内陸部で発生する大きな地震の後に南海トラフ巨大地震が起きるとされ、今はまさに危険な状態にあると言われているのです」(同)
最近の南海トラフ巨大地震では、1944年の昭和東南海地震(M7.9)の前年に鳥取地震(M7.2)や長野県北部地震(M5.9)などが起きている。さらに、そうした南海トラフ巨大地震の前に発生した内陸地震の一つとして、'95年の阪神・淡路大震災(M7.3)を挙げる地震学者もいるほどだ。
そうした中、地震学が専門で武蔵野学院大学特任教授の島村英紀氏は、こんな不気味な指摘をする。
「雨が降ると地震が起きやすくなると言われますが、これは世界的に見ても本当のことです。大西洋中央部のポルトガル領、アゾレス諸島という火山島では、雨が降ると地下のひずみになっている部分に水が浸み込んでいき、それが地中で水蒸気爆発を起こし地震がよく起こることが知られています。つまり、雨が地震を誘発するということ。日本では水害と地震が重なるという例は過去にありませんが、起きたとしても何ら不思議ではないのです」
島村氏が指摘するほか、専門家の間では地震と雨の関係について、2009年の台湾での地震(M6.4)と7カ月前に襲った台風、'10年にハイチで起きた巨大地震(M7.0)と18カ月前のハリケーン襲来、日本では'04の新潟中越地震と直前の台風による大雨などが当てはまると言われている。
その仕組みについては、水の浸み込みの他にも、台風の場合、気圧の変化が引き金となって地震のエネルギーが放出されるとの見方もある。
「集中豪雨が襲った山間部の地域で、もし大地震が発生したとすると、土石流が止まって住民が安心しているところへ、地震の揺れによる新たな土石流が発生し、犠牲者が出る。溜池などは、何とかもっている堤防が決壊して水が流れ出す。平地でも、豪雨によって建物の基礎の部分がよれよれの状態だとすると、そこへ大地震が加わり潰れてしまうでしょう」(渡辺氏)
そうした光景が起こりうることを、肝に銘じておかなければならない。