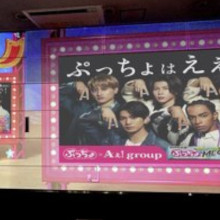知らぬ間に多額のカネをつぎ込んでしまう携帯電話ゲームの「コンプガチャ」(コンプリートガチャ)と呼ばれる仕組みに対し、松原仁消費者相が規制対象にする方針を明らかにしたのは先月18日のこと。その法律の規制施行日である7月1日が迫ってきた。
発表後、DeNAやグリーなどゲームサイト運営会社6社が、相次いで対象ゲームを中止にしたのは記憶に新しいところ。散々ユーザーからむしり取った揚げ句、度重なる批判をも飄々と受け流していた業界だが、法規制されると決まるや一転、自主規制に踏み切る変り身の早さには呆れるばかりだ。
そもそもコンプガチャとは、1回数百円のガチャと呼ばれるくじでカードを集めるゲーム方式だが、問題なのはその中にめったに出現しないレアカードを組み合わせたこと。このカードは希少性が高いことからユーザーの中でも幻のカードとして扱われ、所有すること自体が自慢の対象になるという“神アイテム”。それ欲しさに100万円単位の課金をした人もいたというから恐ろしい。しかも極めて悪質なのは、その出現率がきちんと表示されていないことだ。極端なことをいえば、100万円課金しようが出ないときは全く出ない。いわば、何の根拠もない可能性を信じてカネを使い続けなければならないのだ。小学生までがこのゲームにハマり、高額な請求を受けていたことが社会問題にまで発展した。
一方、くじのバグ(システムの欠陥)を利用してレアカードを難なく大量に入手し、それをオークションサイトで転売して2カ月間で3000万円も荒稼ぎした悪いヤツがいたのも、不透明さが残るシステムの脆弱な一面だった。
もはやパチンコ以上に“射幸心”をあおっているとしか思えないコンプガチャ。ゲームの数は腐るほどあるが、その名前の頭に“CR”をくっつければ、確かにすぐにでもパチンコ台に変身できそうだ。ともあれ、異なる絵柄を集めて別の景品をもらえる仕組みが景品表示法で禁じる「カード合わせ」に抵触することが明確になった今後、未成年者への高額課金問題などは本当に解消されるのだろうか。
「確かにコンプガチャ自体は廃止となります。しかし、業界が一度手にした打ち出の小槌を、そう安易に手放すはずありません。各社いかに法律に触れないようシステムを変えていくかに躍起となっていますが、早くも新方式のガチャが導入され始めています」(ゲーム誌ライター)
どうやら法律を巧みにかわす、新しいくじ引き方式のようだが…。
「今までのコンプガチャは、たとえば10種類のカードが揃った時点でレアカードがもらえるとすると、ダブりカードが出現するために1回300円のくじを何度も引かないといけなかったんです。今回、ある会社が導入したシステムは、このダブりカードが出ない仕組みになっています。要は10回引けば必ずレアカードがゲットできる。これなら偶然性は絡みませんから法的にも大丈夫だと考えたのでしょう」(同)
しかし、これではユーザーが落とす課金額が減少してしまう。そこで1回あたりのくじ引き代金を1000円とし、コンプリート(全種類揃えること)までにかかる費用を1万円(1000円×10回)に抑えているという。これなら300円のくじを30回以上引くのと同等の売り上げになる。いくらかかるかわからないと思って最初から諦めてしまっていた人が、10回きっかりならと課金する可能性は高いだろう。
「今まではコンプリートの報酬として得られていたレアカードを、普通のガチャの中に組み込んできたパターンもあります。これなら必ずしもコンプリートの必要はありませんから、気軽にガチャを引こうとしますよね。ただし、これにもカラクリがあって、目玉カードだけになかなか出現することがなく、やはり出現率は明確にしていません」(同)
ほかにもビンゴのように同じ絵柄3つを並べることで獲得できたり、ポイントカードのように特定回数以上ガチャをやると、希少のカードを引く確率が上がるなどの仕組みがあるという。
今回の規制は、あくまでも「景品表示法」で禁じられている“カード合わせ”商法に触れるかどうかであり、消費者庁は「これらは該当しない」と見ている。結局、何回もくじを引かなくてはならないという意味では、今までと大差ない。あの手この手で絞り上げようとする体質は何ら変わっていないのだ。
これでは法規制も効果ゼロなのではないか…。実際、コンプガチャこそ廃止になるものの、相変わらず課金を続けながらゲームにハマっている人は後を絶たない。社会問題化してからも、請求書に驚いた親が消費者相談センターなどに足を運ぶケースはいまだに増加しているという。
そんな彼らは今、一体どんなものに夢中になっているのだろうか。実はここに、ゲームサイト運営会社のしたたかさが隠されている。