ネット上では、映画『図書館戦争』を引き合いに出し“リアル図書館戦争”などと話題になった。
問題の発端は、図書館の指定管理者制度導入だ。指定管理者制度とは図書館の管理運営を民間に委託するもので、2003年に始まったもの。その狙いは「経費削減」と「サービス向上」で、全国に広まりつつある。
「図書館に限らず、公営施設にはさまざまな問題があります。昨年11月にはママタレの熊田曜子が、5歳、3歳、4カ月の女の子3人を東京・墨田区の児童館に連れていったところ、入り口にいるスタッフから『お子さんは大人1名につき、子供2名までなのでは入れません』と断られたことが、ワイドショーでも取り上げられたました。区は断った理由を『大人1人が子供の安全を見ていられるのは2人が限度だから』と説明していましたね」(週刊誌記者)
公共施設の場合、住民の安全やサービス向上をうたいながら、現場とのそごや、利用者にかえって負担を生じさせてしまうことがままある。高齢社会の日本では、2065年には約3.9人に1人が75歳以上になるというデータが公表されている。そんな日本を反映するように、公共図書館には高齢者の姿が目立つようになり、今までならありえないトラブルが起こっている。
毎朝新聞を奪い合い、負けてキレる、徘徊する、失禁してしまう老人…。このようなシニア利用者を巡って頭を悩ませる図書館は少なくない。高齢者の生きがいを育む場として本来有効な図書館には、中高生が勉強したくても入場制限されるなどの問題も浮上しており、有効なインフラでもあるはずの図書館にさまざまな問題が浮上している。その1つが前述したような高齢者の利用問題だ。
「図書館では、本のような印刷物を読むことが困難な人々でも利用できる分野を一般的に『バリアフリー図書』と呼んでいます。文字が大きい『大活字本』や朗読を収録した『オーディオブック』などがそれにあたりますが、そのカテゴリーには高齢者も含まれています。実際、公共図書館には高齢者、ハッキリ言って認知症の方という利用者区分はありません。足が悪いとか目が悪い、耳が遠いといった不具合を抱える高齢者のニーズは、障害者ニーズと重なっているという考え方なのです。高齢者の図書館利用については、自動ドアや階段のスロープ、エレベーターなど施設の整備といったハード面は充実していますが、元気な高齢者へのサービスや、認知症への応対といったソフト面に対する大きな課題が残されているのです」(公共政策アナリスト)
人生100年時代といわれる現代で、高齢者が生き生きと生活できる居場所づくりは、今後、永続的な課題となる。地域社会とつながり、自発的に新しい目標を立て、豊かな生活ができる、そんな高齢者の生活を支えるには図書館の現実に即した充実が必要ではないか。


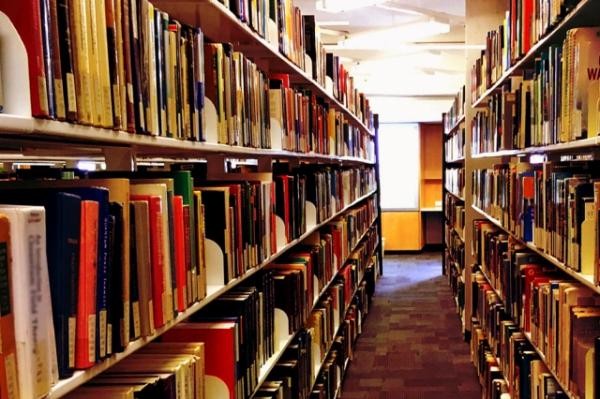






















 芸能
芸能







