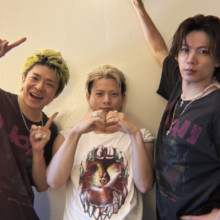新規制基準の施行に先立って、7月5日に東電の廣瀬社長と泉田知事の会談が行われた。その席で泉田知事が廣瀬社長に「原発の安全とお金のどちらを優先するのか」と迫った。地元自治体に十分情報を提供してこなかった東電に不信感を募らせた泉田知事は会談を打ち切り、結局会談は物別れに終わった。
東電に対する泉田知事の怒りはわかる。しかし、安全と経営の二者択一を迫るやり方に違和感を覚えたのも事実だ。安全も経営も大切なことは明らかだからだ。
東電は、昨年の値上げ申請の際に柏崎刈羽原発の再稼働を前提に料金を設定している。そのため、もし再稼働ができなければ3期連続の赤字に陥ってしまう。そうなれば、再び電気代が値上げされるのは明白だ。
いま原発を一基再稼働すると、電力会社の損益がおよそ1000億円改善するという。私はその利益を全て電力会社に渡すのではなく、一部を政府が課税して、原発事故による避難者の生活再建と新エネルギーの開発に振り向けるべきだと思う。たとえば、自宅に住むことができなくなってしまった被害者に対しては、安全な地域に家を建てる資金を補償すべきだろう。避難者が仮に10万人として、1人あたり2000万円を支給したとしても、必要な財源は2兆円で済む。この費用を10年分割で支払うとしたら、1年間の負担は2000億円だ。仮に原発50基すべてを再稼働すると、年間5兆円電力会社の利益が増えるから、2000億円くらいを避難者支援に回しても問題はないだろう。
さらに必要なのは、脱原発のための新エネルギー開発だ。それも太陽光発電や風力発電のような不安定な電源ではなく、安定して利用できる大規模エネルギーの開発だ。私は、地熱しかないと考えている。
日本は、アイスランドに次いで世界第2位の地熱資源を持っている。ただ、地熱は安定した蒸気を掘り当てるのが難しいので、なかなか開発が進んでいない。しかし、良い方法がある。マグマ発電だ。
日本は火山国だから、掘り進んでいくとマグマに当たる場所がたくさんある。マグマの近くの岩盤は高熱になっているから、パイプをその近くまで持っていき、地上から水を注入すれば蒸気になって戻ってくるのだ。夢物語ではない。室蘭工業大学とグンゼが共同開発した1600℃の超高温に耐えられるセラミック複合材のパイプを使って、すでにマグマ発電の実証研究が始まっているのだ。
問題は、商業ベースで成り立つかどうかだが、大きな資金を注ぎ込むことができれば、商用レベルで実用化できるかもしれない。仮にマグマ発電の開発に年間3000億円の資金を投じたとしても、先の住宅再建資金と合わせて5000億円のコストで済む。
原発のリスクは、廃炉にしなければなくならない。だから、廃炉を確実に進めるためにも代替エネルギーの確保が不可欠なのだ。