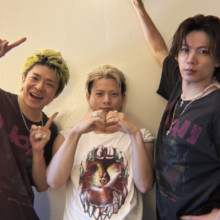太陽光や風力など、再生可能エネルギーで発電した電力の買い取りを大手電力会社に義務付けた「FIT(固定価格買取制度)」が、7月1日に一周年を迎えた。
読者の多くは気がついていないだろうが、このFITという制度は、実に恐るべきシステムなのだ。何しろ、再生可能エネルギー(特に太陽光発電)に投資した事業者は、「生産」した電気を「高い価格で、最大20年間」電力会社に購入してもらえる。
例えば、太陽光10kw以上の単価は、当初は1kwあたり42円だった(現在は38円)。再生可能エネルギー固定買取制度で先行しているドイツは18円〜24円である。風力発電は、日本が23.1円〜57.75円に対し、ドイツは5円〜9円。日本の固定買取価格は「異常」に高い。
日本の買取価格がなぜ高いかといえば、FIT開始時に経済産業省が、新たに再生可能エネルギーの発電事業に参入する新規企業などの「要望」を受け入れたためである。
FITの買取価格は、法律では、
「電力の供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用等を基礎に、経済産業大臣が調達価格等算定委員会(経産省内の委員会)の意見を聴き、決定する」
となっている。費用等を基礎に価格を決定した場合、日本の太陽光発電の買取価格がドイツの2倍であることの説明がつかない。
実は、一年前、FIT制度が日本で開始された際に、調達価格等算定委員会が太陽光発電の1kw時当たりの買取価格について、42円とするべきとの原案を経済産業大臣に提示しているのだ。
なぜ、42円なのか。単に、民間の太陽光発電事業者の業界団体である太陽光発電協会が、調達価格等算定委員会に、
「1kw時あたり税抜きで42円」
と要望し、再生可能エネルギー特別措置法の「事実上の生みの親」であるソフトバンクの孫正義社長も、
「最低でも税抜き40円」
と主張したためなのである。
FIT初年度の異様に高い太陽光の買取価格(今も高いが)を決定したのは、経済産業省でも調達価格等算定委員会でもなく、民間の事業者である。
太陽光発電による電気を買い取ってもらう側が「価格を決定した」という、俄かには信じがたい話だ。
「別にいいじゃないか。それで再生可能エネルギーが普及するならば」
などと思うなかれ。何しろ、高い固定価格で買い取られた再生可能エネルギー(厳密には電気だが)の費用を払っているのは、読者自身なのだから。
電力会社が太陽光や風力等で発電された電気を固定価格で買い取るとはいっても、別に自腹を切るわけではない。電力会社は法律に則り、買い取った再生可能エネルギーの代金について、消費者(家計、企業)が払う電力料金に「賦課金」として上乗せしている。電力料金の領収書の明細を見ると、料金内訳に「再エネ発電賦課金等」が載っているはずだ。
ここで「そもそも論」をしたいのだが、そもそも蓄電技術の大々的なブレイクスルーがない限り、日本のエネルギー供給の分野で、太陽光発電や風力発電が主役になる日は訪れない。理由は、我が国の国土的条件による。
日本は欧州のように、一定な西風が吹くわけではない。さらに、台風が来るため、そもそも風力発電を大規模に展開できるような国土ではないのだ。
台風が来れば、風力が増すため、その分だけ多く発電できる、という話ではない。風力発電は想定以上の風が吹いた場合、風車の破損を回避するために、運用を停止しなければならないのだ。
太陽光パネルも同じである。太陽が陰ると発電量が落ち(雨や雪の日でも、一応、発電はできるが)、日が沈むと全く発電できなくなるのに加え、そもそも発電容量が小さすぎる。原子力発電1台分の電力を太陽光で発電するには、太陽光パネルを山手線の内側の広さに敷き詰める必要があるのだ。
再生可能エネルギーについて「原発の代替」と勘違いしている人がいるが、太陽光や風力は原子力発電の代わりにならない。
電力サービスとは「電気」の特性上、在庫がほぼ不可能な「商品」だ。読者が使っている電気は、まさに「今」発電され、送電網、配電網を経由して届けられている。
天候や時間帯によって発電がストップするタイプの太陽光や風力による発電は、「いつ発電が止まるかわからない」という性質を持つため、電力会社にとっては極めて厄介な代物なのである(だからこそ、普及していなかった)。
さらに、電力サービスとは「需要」に合わせ、電力が供給されなければならない。電力が過小になると停電を引き起こすのはもちろん、「電力の供給が過剰」になるのも問題なのだ。
需要を上回る電気を送電網に流すと、サービス網全体のバランスが維持できなくなる。結果的に、「電力供給が多すぎたため、停電する」という異常事態を引き起こしてしまう。
たとえば、日本のゴールデンウイークなど、電力の需要がそれほど大きくない時期に、太陽光や風力で発電された電気が送電網に過剰に流れ込むと、大規模な停電を引き起こす可能性がある。
とはいえ、電力会社側はFITの法律の特性上、自社の送電網に対する発電会社による電気の供給を制止するすべはない。
需要といえば、FITによる再生可能エネルギーの買取には「上限」がない。事業者側は、とにかく投資して電気を「生産」すれば、電力会社に「需要と無関係に」「固定価格」で買い取ってもらえる。
FITの買取価格は、毎年変更される。新規の申し込みについては、価格を引き下げられる可能性はある。が、既存の稼働中の発電設備については、価格は契約終了まで一定だ(最大20年)。
すなわち、我々日本国民は(電力会社ではなく)電力サービスを不安定化する電気を、高い価格で、長期に渡り、需給と無関係に、高い価格で買い取らされ続けるのである。
不思議なことに、常日頃は「市場競争が重要だ」と主張するマスコミは、このFITの問題点を指摘しようとしない。
三橋貴明(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、わかりやすい経済評論が人気を集めている。