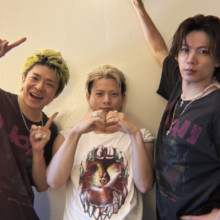2017年9月の完全失業率は2.8%、有効求人倍率は1.52倍。共に主要先進国の中で「最高」の水準だ。実は現在の日本の雇用環境は、先進国で最もよいのである。それにも関わらず、実質賃金は下落が続いている。
'17年9月(速報値)の日本国民の実質賃金は、現金給与総額で対前年比▲0.1%、決まって支給する給与は▲0.3%。恐ろしいことに、日本の実質賃金は、現金給与総額で'16年12月、決まって支給する給与は'16年9月以降、対前年比でプラス化したことがない。日本国民の貧困化は、今でも続いている。
第二次安倍政権が発足した'12年以降、わが国の実質賃金はすでに5%も下落してしまった。人手不足が深刻化していく最中に、実質賃金が下がり、国民の貧困化が続いているのである。
異様だ。異様だがデータを普通に見れば、今日本で何が起きているのかが理解できる。左図(※本誌参照)の通り、第二次安倍政権発足後の就業者数を見ると、
●高齢者 212万人増加
●女性 212万人増加
●生産年齢男子 49万人減少
と、働き手の主力たる生産年齢(15〜64歳)男子の就業者が減少する反対側で、高齢者と女性の就業者が激増しているのだ。
第二次安倍政権下において、生産年齢人口比率の低下を受け、「企業が引退する団塊の世代の穴埋めとして、短時間労働(パートタイム・アルバイト)の高齢者、女性を雇用した」結果、日本の就業者数が増加したことは、誰の目にも明らかである。
何しろ生産年齢の男性の就業者数は、50万人近く減ってしまっているのである。短期労働が増えた結果、実質賃金も当然ながら低迷した。生産年齢男子の就業者が減少し、反対側で高齢者と女性の就業者数が増えた結果、就業者の総計が増えているわけだが、これが、「安倍政権の金融政策のおかげ」と、主張するのであれば、「金融政策」から「生産年齢男子の就業が減り、高齢者と女性の就業者が増える」までの政策の波及プロセスをきちんと説明してもらわなければならない。
現在の日本の雇用環境を決定付けているのは「人口構造の変化」であり、安倍政権の金融政策ではない。もし、金融政策の影響だというならば、
「なぜ金融政策をすると、生産年齢の男子という主力の働き手の仕事が減るのか?」
という問いに、答えてもらう必要がある。人口の瘤である団塊の世代が生産年齢人口から離脱し、それを埋めるだけの若い世代が労働市場に参入していない。それ以外の説明ができるならば、是非、披露してほしいものだ。
それはともかく、過去の日本の雇用改善は、フルタイム雇用から短期雇用への切り替えにより生じたものである。すなわち、国民の賃金は上がらない(むしろ、平均では下がる)。とはいえ、さすがに人口構造の変化(生産年齢人口比率の低下)の圧力はすさまじく、人件費にもプラスの影響を与えつつある。
宅配便最大手のヤマト運輸は、インターネット通販繁忙期(12月)を控え、運転手について一部の地域において時給2000円で募集を始めた。また、Amazonジャパンも、倉庫作業について時給1850円を提示している。
人口構造の変化を受けた人手不足は、ついに「時給」にまで大きく影響を与え始めているのである。これは、もちろん日本国の国民経済にとってはいいことだ。人手不足による賃金上昇。真っ当な動きが、運送サービスから起きているのである。ヤマト運輸にしても、Amazonジャパンしても、人件費上昇を「サービス単価」にきちんと反映してほしい。そうすることで、中小の運送業者も追随することができる。
ところで、人手不足を報じる新聞報道は、外食産業における時給引き上げの動きについても伝えている。例えば、日本経済新聞は、
『特に厳しいのが忘年会や新年会を迎える居酒屋業界だ。「備長扇屋」などを運営するヴィア・ホールディングスは12月のアルバイトの平均時給を約1000円と、同社としては過去最高額を提示。前年同月比で約2%上昇するが、「人が集まらないとかきいれ時を乗り切れない」としている。
チムニーも12月のアルバイトの時給は前年同月比で1%超高い平均1100円とする。つぼ八も12月のアルバイトの時給に50円上乗せする』(日本経済新聞 '17年11月15日)
と、報じている。居酒屋業界の時給は現在の日本の人手不足を考えると、異様に安いという印象を持ったわけだが、なぜ運送業界では時給2000円という話が出ているにも関わらず、居酒屋業界ではいまだに1000円前後で推移しているのだろうか。もちろん、運送業界は(免許の関係で)外国人労働者を使いにくい。居酒屋は「留学生」と称する外国人労働者を使える、という違いがあるためだ。
本来、留学生は日本に「学び」に来ているはずだ。とはいえ、現行法では留学生は資格外活動許可を受けることで、アルバイトとして働くことが可能になっている。資格外活動許可とは、アルバイト先に風俗営業または風俗関係営業が含まれていないことを条件に、週に28時間以内を限度とし、包括的な労働許可(事実上の)を与えるという仕組みになる。もちろん、資格外活動の許可を受けずにアルバイトに従事すると、不法就労となる。
現実には20万人を超す留学生が、日本でアルバイト(外国人労働者)として働いている。技能実習生同様に、外国人留学生が日本における「外国人労働」の抜け道になっているのは間違いない。それだけならばまだしも、運送業界と居酒屋を比較する限り、
「外国人を雇える業界は時給が上昇せず、雇えない業界は時給が上昇する」
結果となることは明らかだ。
日本の移民受入は、
「日本国民の実質賃金を引き下げ、国民を貧困化に追い込み、生産性向上のための投資を抑制する」
という理由で、決定的に間違っているのだ。
みつはし たかあき(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、分かりやすい経済評論が人気を集めている。