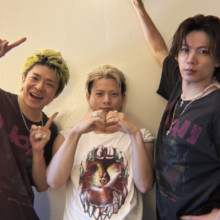前年首位のプリウスを破ってトップに立ったのは、ホンダのN-BOXだった。それだけではない。3位のダイハツのムーヴ以下、ダイハツ・タント、日産デイズ、スズキ・ワゴンR、スズキ・スペーシアと、ベスト10の中で、軽自動車が6車種を占めたのだ。
しかも、この6車種は、いずれも軽自動車の高さ制限をギリギリまで活かした、トールタイプの車だ。このことは、一体、何を意味するのだろうか。
かつて軽自動車は、2台目、3台目のサブカーとしての役割を果たしていた。しかし、家計が苦しくなる中で、普通車を持たず、軽自動車だけですべてを賄おうとする家庭が増えている。だから、たっぷり荷物を積めるトールタイプが人気を集めているのだ。
消費者が軽自動車を主役に据えた最大の理由は、維持費が安いからだ。1年当たりの自動車税と重量税の合計は、軽自動車の1万3300円に対し、排気量1000㏄のリッターカーは3万7000円と、実に3倍近い。その他に、タイヤも軽自動車の方が大幅に安いし、高速道路料金もおよそ3割引きだ。
最近の軽自動車は、加速もよいし、室内も広い。また、安全性も大幅に向上している。つまり、経済合理性で選ぶなら圧倒的に軽自動車が有利なのだ。日本の自動車メーカーが、軽自動車という規格の中で必死に改善努力を積み重ねてきた結果だ。
ところが、軽自動車とリッターカーで、ほとんど変わらないものがある。それが燃費だ。本来であれば、車体が小さく重量も軽い軽自動車の方が、燃費がよくて当然なのに、なぜそうしたことが起きるのか。それは、550㏄という排気量が燃費をよくするためには小さすぎるからだ。また、軽自動車の規格の中で室内空間を確保しようとすると、空気抵抗を減らすデザインを採用しにくいという事情もある。
もちろん、軽自動車規格の中で最大限の成果を生み出す日本の技術は、飛び抜けている。だから、軽自動車の規格に挑戦してくる海外メーカーはどこもない。ただし問題は、軽自動車は輸入されていないけれど、輸出もほとんどされていないという事実だ。いまの日本の軽自動車では、例えば、アメリカの衝突安全性能基準をクリアできていないし、欧州で売るにも小さすぎる。
もし、このまま日本車メーカーが軽自動車の開発ばかりに注力していくと、日本の自動車産業は、日本だけでしか通用しない独自の進化、つまりガラパゴス化してしまうだろう。
それを防ぐために、私は軽自動車の排気量や大きさの制限を、いまのリッターカー並みに拡大すればよいと思う。
そうすれば、世界を相手にできるコンパクトカーの開発に国産メーカーが注力できるからだ。
そんなことをしたら、ますます軽自動車シフトが起きて税収が減ると思われるかもしれないが、富裕層はリッターカーにはほとんど乗らない。いまのリッターカーの分だけが税収減になるのだから、実害はさほど大きくない。いますぐ、軽自動車の規制緩和をすべきだ。