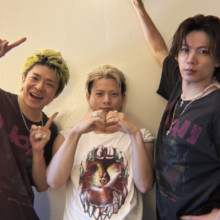ラインハート氏とロゴフ氏の論文の主旨は「公的債務(政府の負債)の対国内総生産(GDP)比率が少なくとも90%に達すれば、GDP伸び率が減速し始める」「公的債務対GDP比率が90%を超えている国家の平均実質成長率はマイナス0.1%」というものであった。本論文は日本でも『国家は破綻する−−金融危機の800年』というタイトルで、日経BP社から2011年3月に出版されている。
ラインハート氏とロゴフ氏の「説」は世界中に拡散し、各国の緊縮財政派を後押ししてきた。何しろ、公的債務が増えれば増えるほど、経済成長率が(両氏の説によると)落ちるのだ。逆に言えば、公的債務を減らせば、経済成長率が高まるはずなのである。
公的債務が減れば、経済成長率が高まる。これは果たして、いかなる理屈によるのだろうか。
左ページにある図(本誌参照)の左側の状況に国、すなわちインフレギャップがある国は、「需要過多、供給能力過小」になっている。名目GDPが潜在GDPを上回っているわけだ。
インフレギャップがある国にとってのソリューション(解決策)は、「政府の需要を抑制し、潜在GDPを引き上げるために企業投資を促進する」になる。政府が歳出や公的債務を減らし、国債発行を抑制すると、「需要抑制」と「潜在GDP拡大」が同時に達成できるはずなのだ。なぜ、潜在GDPが拡大するかといえば、政府が国債発行を抑制し、財政健全化を目指すことで「金利」が下がり、企業がおカネを借り入れ、設備投資に乗り出しやすくなるためである。
というわけで、ラインハート、ロゴフ両教授の「説」にも裏付けられ、緊縮財政で成長を目指すという思想が世界中に広まってしまった。各国の緊縮財政主義者たちは、事あるごとに両氏の論文を引合いに出し「経済成長を達成するためには、緊縮財政で財政赤字や公的負債を削減するしかない」と、国民を苦しめる緊縮路線を推進していったのだ。
ところが、この両氏の論文に「誤り」があった。というよりも、筆者に言わせれば「ウソ」である。両氏は「公的債務対GDP比率が高い国は経済成長率が低い」という結論を「造る」ために、データを恣意的に操作していたのである。
具体的には、
(1)「大きな公的債務と平均的な成長」の年のデータを選択的に除く
(2)各国のデータについて、「議論のある」重みつけをする
(3)「大きな公的債務と平均的な成長をしている国々」を除くコーディングエラーをする
の三つである。何というか、完全に詐欺的手法にしか思えない。上記の「手法」に寄らず、普通にデータを分析すると「公的債務対GDP比率が90%を超えている国家の平均実質成長率は2.2%」というのが真実だったのである。
「誤り」を指摘された両氏は「誤りは偶発的なものだった」と釈明しているが、それでも「中心的なメッセージは有効だ」と強弁している。両氏は「中心的なメッセージを有効に見せる」ために、明らかに恣意的にデータ操作を行ったにもかかわらず、である。
そもそも、政府の歳出や公的債務の削減が経済成長に結びつく「可能性がある」のは、前述の通り、インフレギャップがある国のみである。デフレの国は、いずれにせよ「公的債務の削減=経済成長率アップ」にはならない。何しろ、デフレの国は潜在GDPが名目GDPを上回っており、供給能力は余っているのだ(本誌図の右側参照)。
デフレの国にとって必要なのは、潜在GDPではなく需要(名目GDP)の拡大だ。そして、政府の公的債務削減は「イコール需要縮小」になってしまう。
しかも、デフレの国(注:正しいデフレの国)は長期金利が下がっていく。政策金利については、中央銀行がゼロに近づける。とはいえ、どれだけ金利が下がっても、企業が設備投資に乗り出さないのがデフレ期なのだ。理由は単純に、儲からないためである。
ロゴフ教授らの論文に「誤りがあった」となると、現実の世界では、インフレ期であろうとも「公的債務の削減=経済成長率アップ」になっていない可能性があることになる。もちろん、インフレ率によって変わってくるのだろうが、各国の政策担当者たちまでもが、素直に両氏の論文を信じ込んでいたわけだから呆れた話だ。これまでは、緊縮財政政策への取り組みを正当化するため、世界中の政策担当者たちが頻繁に両氏の論文や研究内容に言及していたのである。
現実には、日本にせよアメリカにせよ、イギリスにせよギリシャにせよ、公的債務対GDP比率の上昇に「煽られ」、政府が緊縮財政政策を採った結果、GDPがマイナス成長になり、税収が減り、財政がかえって悪化している。公的債務を削減するための緊縮財政は、成長率を高めるどころか「マイナス成長と財政悪化」を引き起こしているのだ。
それにしても、情報を操作し、自己に都合が良い結論を導こうとするのは、何も日本のマスコミに限った話ではないわけだ。
ラインハート、ロゴフ両氏の情報操作は「誤った情報を流し、間違った解決策を導く」という点で、やっていることが国内マスコミと同じだ。しかも、情報操作が「世界規模に影響を与えた」という点で、極めて罪深いと断ぜざるを得ないのである。
三橋貴明(経済評論家・作家)
1969年、熊本県生まれ。外資系企業を経て、中小企業診断士として独立。現在、気鋭の経済評論家として、わかりやすい経済評論が人気を集めている。