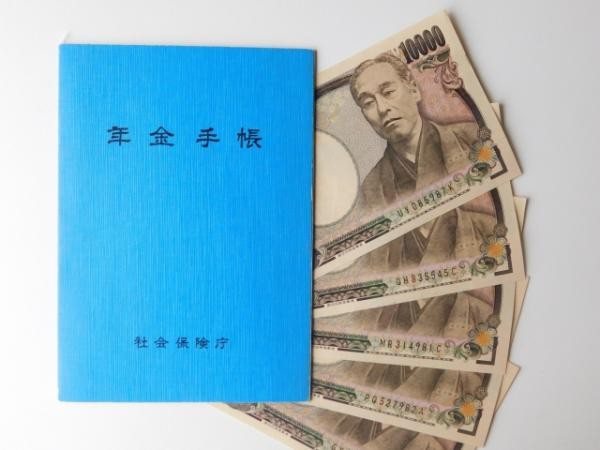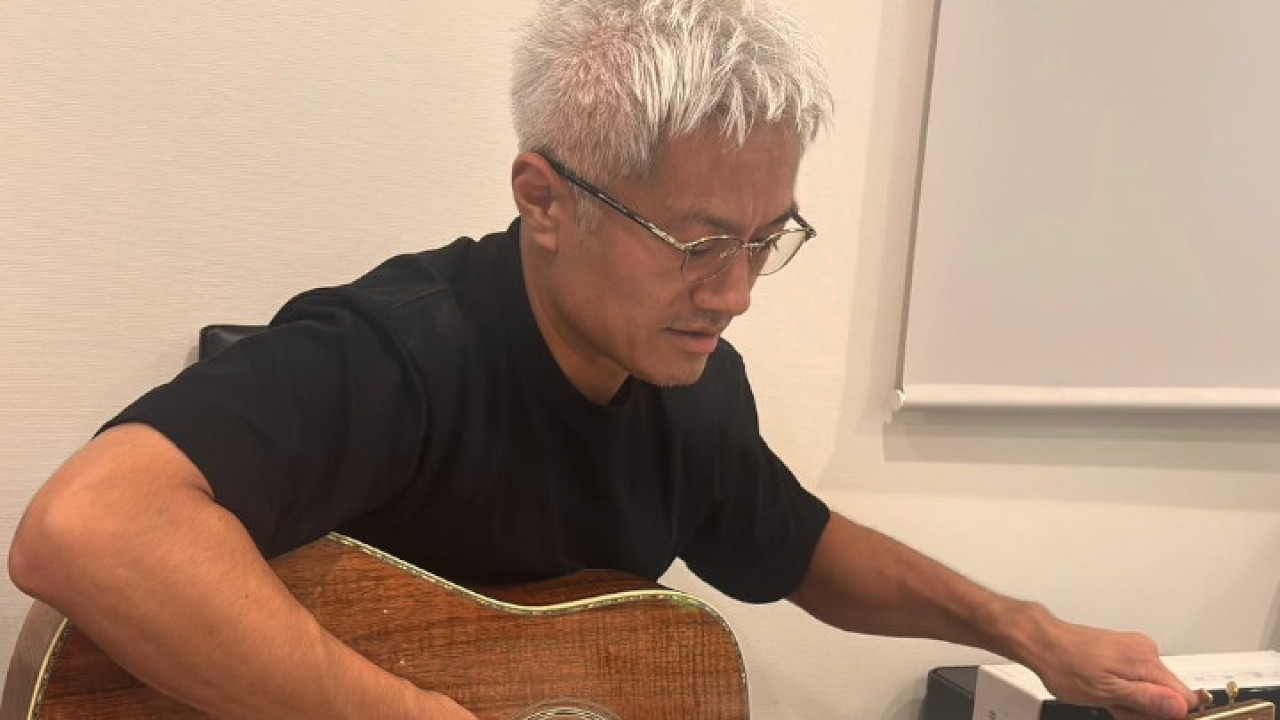日本の年金制度は、現役世代が支払った年金保険料を、その年の高齢者が分かち合う「賦課方式」で運営されている。そのなかで、現在2.1人の現役世代で1人の高齢者を支えているのが、2065年には1.3人で1人を支えることになるのだから、放っておけば、年金の給付水準はいまより4割も減少する。さらに、00年代に就職活動をした就職氷河期の若者の4割は、いまだに非正社員のままであり、国民年金の未納期間がある人も多いから、彼らが高齢期を迎える頃には、日本が貧困高齢者であふれてしまう。健康で文化的な最低限度の生活を保証した、憲法25条の規定に反する状況が生まれるのだ。
それを防ぐ手立ては、税金を財源に、最低保障年金を支給するしかない。しかし、そのためには、消費税率を2倍にしても足りないほどの財源が必要になる。
そのため私は、参議院選挙特集で、新聞2社、ラジオ1社の取材を受けるなかで、MMT(近代貨幣理論)の採用の必要性を取材時間の半分程度を費やして、強く主張した。ところが、3社は私の主張からMMTの部分を完全カットした。どうやら日本のメディアは、MMTを妄想だとみているようだ。
そこで、MMTをきちんと説明しておこうと思う。
MMTは、高率のインフレになるまでの財政赤字を許容する。赤字国債を中央銀行が買い取ってしまえば、その時点で事実上借金が消えるからだ。経済学ではこれを「通貨発行益」と呼ぶ。通貨発行益は、これまで世界中で利用されており、日本でも明治維新の改革費用や太平洋戦争の戦費は、通貨発行益で賄われた。
しかし、通貨発行益の活用はやりすぎると、2つの問題が発生する。インフレと、国債金利の上昇だ。なので、MMTは高率のインフレになるまでという財政赤字に歯止めをかけている。
そこで、第2次安倍政権の6年間で、何が起きたのかを振り返っておこう。日銀の国債保有は、353兆円増えた。1年当たり57兆円だ。その結果、消費者物価上昇率は’11年の0%から’18年の0.8%まで上昇した。物価は上昇したが、上昇幅は思いのほか小さかった。一方、国債金利は0.8%からマイナス0.2%へと、むしろ下がっている。
このことをどう評価するかが、経済学が直面する最大の課題であることは、間違いない。私は、この6年間の経験を踏まえれば、少なくとも、安倍政権が行ってきた年間57兆円程度の国債買い入れでは、高率のインフレにならないということだと思う。となると、毎年57兆円程度の通貨発行益を、日本政府は継続的に手にすることができることを意味する。
それだけの財源があれば増税を一切せずに、消費税の全廃と最低保障年金の導入が可能になる。国民の老後不安も吹き飛び、消費税の全廃で消費が復活し、経済も大きく上向くだろう。
なぜ、そうした可能性を既存政党、政府、日銀、そしてメディアはきちんと考えようとしないのか。もしかすると、彼らは不況と格差拡大を続けようと望んでいるのかもしれない。勝ち組の彼らにとって不況は、彼らのしもべを安く使える絶好の環境となるからだ。