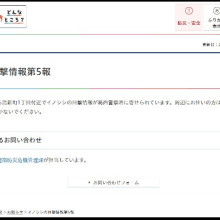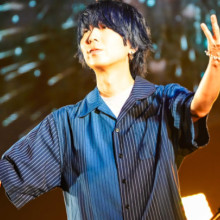国民新党は、郵政民営化に反対する議員の受け皿として、2005年に設立された。それ以来、ずっと小泉・竹中路線に反対の姿勢を取り続けてきた。だから主張する経済政策は、一貫してマクロ経済政策だ。
国民新党のホームページには、「10年以上続いているデフレ不況の下、我が国の経済規模は縮小の一途です。またデフレを脱出し、経済を成長させる事が我が国の財政環境を健全化させる唯一の方法です。国民新党は今後3年間で100兆円規模の財政・金融政策を実現し、5%以上の名目GDP成長の達成を目安とした経済の活性化と経済成長に基づく税収増による財政の健全化を図ります」と書かれている。消費税増税による緊縮型財政再建とは正反対の政策だ。だから、政府が消費増税を強行するのであれば、連立を離脱するとした亀井氏の主張は、筋が通っている。
ところが、連立を維持するとした6人の国民新党議員は、亀井代表を解任して、自見大臣を新代表とする代表変更届けを総務省に提出して受理された。これで、約4億円の政党交付金は、国民新党に残った6人のものになる。亀井氏は代表解任の有効性をめぐって争いを続けることもできたはずだ。しかし、そうはせず、残ったメンバーに「それぞれの人生を歩んで欲しい」と、自ら身を退く道を選んだのだ。
優しさにあふれた人道的な対応だが、亀井氏が成功しない最大の理由が、この優しさなのかもしれない。
いまや国民の期待を一身に集める橋下徹大阪市長は、4月5日、来年度廃止される予定の市音楽団の音楽士36人について「配置転換は、これからの時代、通用しない。仕事がないなら、分限免職だ」と述べて、クビにする意向を示した。
民間企業でも、整理解雇をする前には、会社は配置転換の努力を尽くさなければならないという判例になっている。ところが、要らなくなった社員は切るという冷酷非情な人事が、国民の支持を得ているというのが、残念ながらいまの日本の「空気」なのだ。
国民新党を離れた亀井氏が石原慎太郎東京都知事と新党を作り、国政に進出した大阪維新の会と手を結んで政界のキャスティングボートを握るのではないかという観測もある。ただ、私はそうはならないと考えている。亀井氏は自民党の派閥均衡政治のなかで育ってきた政治家だ。妥協できるものは妥協して、バランスを取ろうとする。橋下氏の独裁型政策運営とは、ソリが合わないのだ。
そもそも亀井氏は、'05年の郵政解散による総選挙で、ホリエモンを刺客に立てられて苦戦した。一昨年6月には、連立合意を破って郵政改革法案を先送りした民主党に抗議して、郵政・金融担当大臣を辞任した。亀井氏の政治家人生は、常に「独裁」に切り捨てられてきたのだ。今回も、石原新党から切り捨てられてしまう可能性もある。筋を通すたびに、ひとりぼっちになっていく。
亀井氏とともに、日本の調和型民主主義も、消えていくのかもしれない。