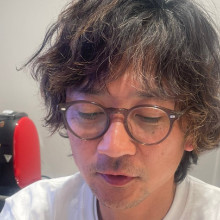アジの種類は世界中に100種以上あるが、日本近海ではマアジ、ムロアジ、マルアジが主流。中でもマアジの漁獲量が圧倒的だが、西日本を中心に水揚げが激減している。
「漁業情報サービスセンターによると、全国主要調査港における産地市場の水揚げ数量の合計は、7月上旬で1024トン。前年同期の約4割減で、8月も不漁が続いています」(東京・豊洲市場水産仲卸業者)
アジの水揚げをけん引してきた長崎県の長崎市や松浦市も、数量低下が著しい。7月上旬の水揚げ数量は長崎が153トン(前年比71%減)、松浦が91トン(同73%減)。6月から続くシケや休漁、さらに海水温上昇の影響で、水揚げが激減している。
「全国シェアの約40%を占める長崎産のアジが不漁続きで、7月後半の豊洲市場への入荷量は前年から15%減少。当然、価格は高くなります。昨年の産地価格は1キロあたり229円だったのが、今年は2割から3割高くなっているのです」(同)
アジは刺し身をはじめ、塩焼き、タタキ、フライと幅広い需要がある。旬の時期に獲れたマアジは干物に加工され、スーパーなどに並ぶが、今年はそうはいかないようだ。
「全国的不漁で、アジは漁獲好調なホッケに“干物の王様”の座を奪われつつある」(都内の居酒屋店主)
サンマに続きアジまでも不漁。不漁の原因は地球温暖化による海水温の上昇だといわれている。せっかくのアジフライブームを終息させないためにも、地球温暖化対策が急がれる。