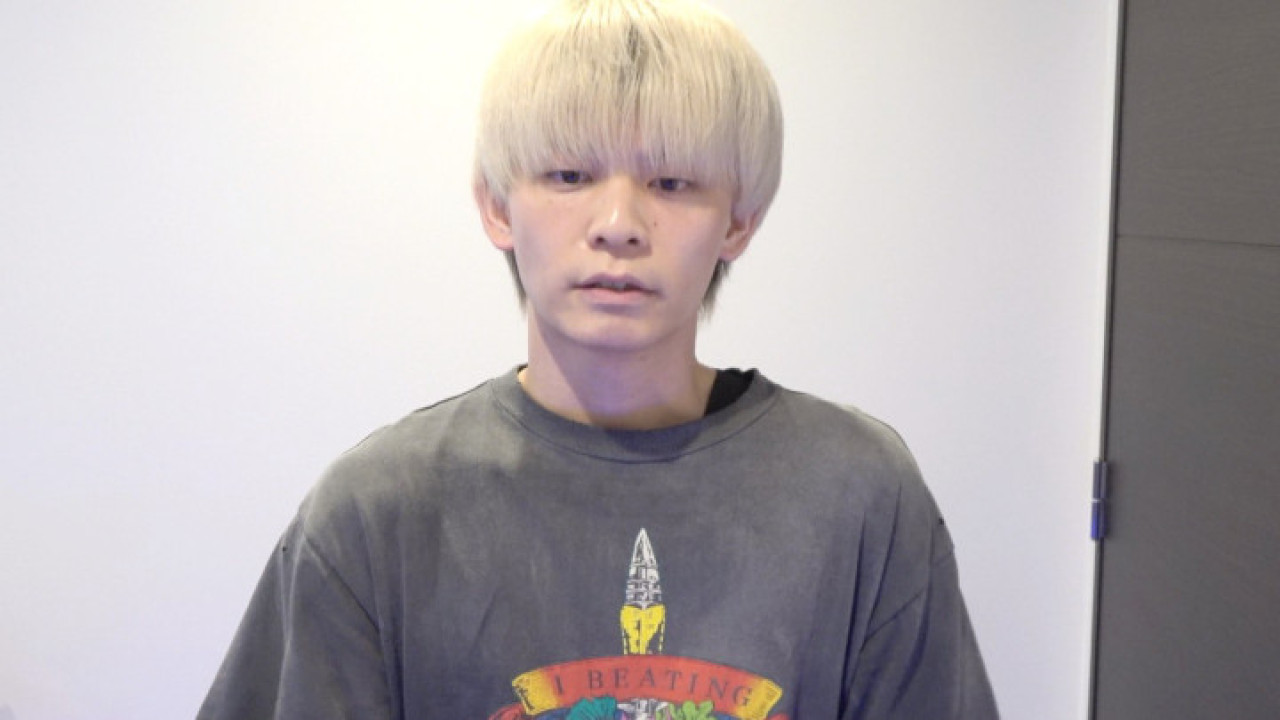「父は曲芸師、芸人として生きることのつらさ、苦しさがよくわかってますから。自分の子供、ましてや女の子に苦労はさせたくないという親心だったんでしょう」
その後も父と娘の葛藤はあったものの、最後は父も娘の背中を押すことになり、ラッキー幸治の一座『ザ・ラッキー』に加わる。『ザ・ラッキー』は、ラッキー幸治が、太神楽を基本にジャグリングなどを取り入れ、よりショーアップした演技で売り出した一座である。この一座の公演スタイルには、ラッキー幸治の進駐軍体験が大きく影響している。戦後派でボードヴィル系の芸人には、進駐軍のキャンプ巡りで腕を磨いたというのが多いが、ラッキー幸治もその一人。
「父によれば、今の日本のジャグリングは、太神楽の投げ物が海を渡ってアメリカに伝わり、それがアメリカ流にショーアップされて逆輸入されたものが基本になっている、というんですね。そのせいか、(ジャグリングは)やっていて少しも違和感はありません」
太神楽もジャグリングも、リズムとタイミングがすべての芸だ。タイミングが一つ狂えば、それまでがいくら完璧でも、一瞬にしてすべてが台無しになってしまう、それだけに、舞台に上がる前には精神統一が欠かせない。
「精神統一というより、呼吸を整えるといった感じですね。舞台が始まったら、頭を切り換えて、あとはもうあるがまま。もし失敗したら…なんて余計なことを考えないで、その時その時を一生懸命に、スマートに務めるだけです。でもそういう気持ちになれるまでには時間がかかりましたよ。以前は、緊張感を引きずったまま舞台に上がって、よく失敗しました」
その失敗の経験で忘れられないのが、『ザ・ラッキー』でやりだした頃のテレビ出演だ。
「NHKに出演したときに、落とす外すで、同じところを何回もしくじってしまって…。失敗したらダメと思えば思うほど手元が微妙に狂ってしまって。しかもその時は公開録画。放送そのものは編集が入りますから、うまくいったところが出るんですけど、会場のお客様には、何度も何度もやり直すところをお見せするという恥ずかしいことになりました。これが寄席なんかの舞台だと、失敗も演技のうち、ということにもなるんでしょうけど、ああいう場合はそうはいきません」
やり直しがきかない厳しさも大変だが、やり直しがきくことの恥ずかしさにもつらいものがある。その恥ずかしい経験が糧になり、その後の「あるがままに」の境地につながったという。
「でも、いつもあるがままに、というわけではないですよ。今でも舞台に出る直前になって、緊張と興奮が入り混じった不思議な感覚に襲われて、不安になる時があります。そんな時は不安と向き合いながら、とにかく初心に帰ったつもりでやるしかありません」
それとは別に、芸への関わり方で生じた不安もある。
「私は曲芸師の娘に生まれたので、自然と曲芸師になりました。生まれた時から目の前にあった道を歩いてきたわけですが、それは私が切り開いた道ではありません。一時はそのことが何となくコンプレックスに感じられたこともありました。でも、これも何かの縁、誰もが縁によって生きていることに気が付いて、何事も前向きに、積極的に考えなければ、と思いましたね」
吹っ切れた気持ちで舞台に向かうことがよい結果に繋がるとの思いは、今も変わりがない。
























 芸能
芸能