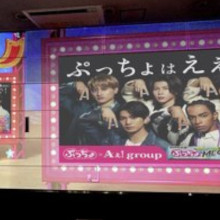そんな中、いまや老舗団体といえる「プロレスリングZERO1」から、主力選手だった佐藤耕平選手や高岩竜一選手が退団することが発表された。コロナ禍によって大会中止が相次いで、団体の財政状況が悪化したことが理由のひとつとなっているようだ。
辞めた選手は、今後はフリーとして活動していくだろうけど、いまどき所属にこだわらなくてもいいという状況もあるんじゃないかな。フリーでも上がれるリングは多いし、日本でも団体を持たないで、興行ごとに選手を集めるプロモーションも増えているからね。
ヨーロッパやアメリカでは、1人のプロモーターがそれぞれの選手と契約して興行を打つというシステムが一般的だった。俺が海外を回ってた1990年代くらいもまだそんな形式が残っていて、ひと試合いくらとか、1週間のシリーズ拘束で、というような契約をその度に行っていた。
それが、WWEのような団体がどんどん大きくなっていき、テレビ中継の視聴率を競う時代になると、人気選手がライバル団体に出ないように契約で縛るようになって「所属」という考え方が出てきた。さらに自前で選手を育成しようとジムや専属コーチも抱えるようになってきて、要するに日本の「団体システム」に近い形になっていった。
団体システムは運営が安定してれば所属選手にもメリットがあるけど、不測の事態で興行が開催できないと、選手は他に出られない分だけ試合数が少なくなってしまうリスクもある。
だからこそ、いまのような興行が限られている状況だと、フリーのほうが身動きが取りやすいということなんだろうね。
こういった選手の動きも含め、コロナの影響によってこれから日本のプロレス業界に再編の波が訪れるのは間違いない。
団体では「新日本プロレス」が規模や収益はトップで、その親会社は女子プロレスの「スターダム」も擁しているブシロード。対抗するのは「DDT」や「プロレスリングNOAH」を傘下に収めているサイバーエージェント。この2グループがお互いに競い合うことで、他の団体や選手の動きも活発化していくと思う。
とはいえ、この2グループの間で無駄な争いはしないほうがいいね。引き抜きや、興行戦争のようなお互いの体力を削り合うようなことをしている間に、世界最大のプロレス団体であるWWEが日本に進出してくるかもしれないからね。
WWEとしてみれば、いちから単独でやるよりも、どこかの団体と提携したほうが話が早いから、その相手を物色しているという話もある。それがサイバーエージェント系なのか、ブシロードなのか。それとも、この2グループが手を取り合ってWWEを迎え撃つのか…。
プロレス界にかかわらず、どの業界でも似たような状況だと思う。コロナによってパワーバランスが崩れて勢力図が変わっていくということが、これからいろんな所で起きてくると思うよ。
***************************************
1963年シアトル生まれ。1984年に新日本プロレスに入団。トップレスラーとして活躍し、2010年に退団。現在はリング以外にもテレビ、イベントなど、多方面で活躍。『ガキの使い大晦日スペシャル』では欠かせない存在。